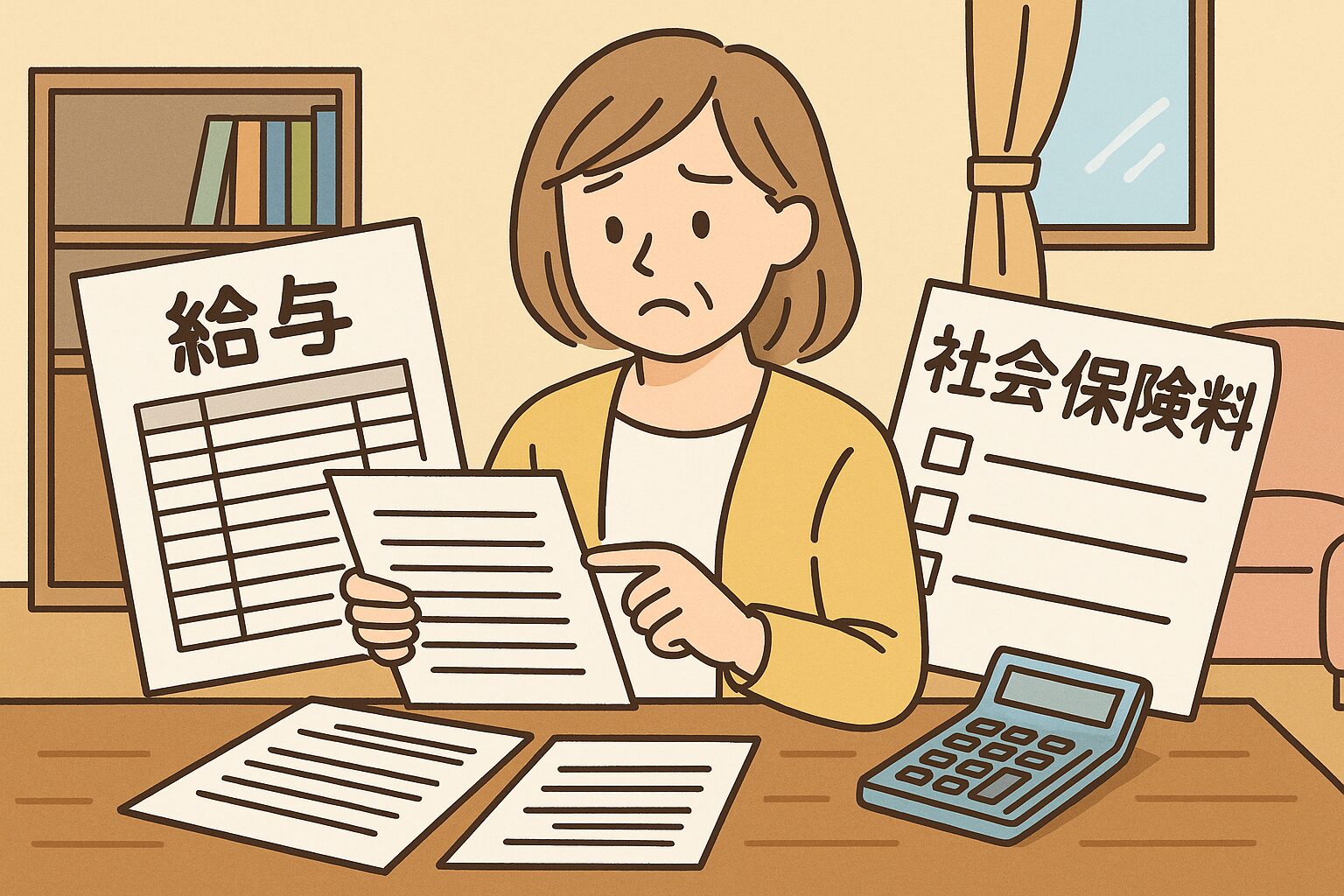退職が決まったとき、「給与はどう計算されるの?」「社会保険料ってどこまで払うの?」と不安になった経験はありませんか。私も退職の直前は、家庭の家計に直結する問題なのでとても気になりました。特に子どもの習い事や生活費があると、手取りが減るのは心配になりますよね。
この記事では、退職時に必要な経理処理について、最終給与の計算方法や社会保険料の精算ポイントをわかりやすく解説します。実際の体験談も交えてお伝えするので、安心して次の一歩を踏み出せるように役立ててください。
退職時の経理処理とは?
退職時の経理処理とは、会社を辞めるときに必ず発生するお金のやり取りの整理のことです。具体的には、給与の締めと支払い、社会保険料や税金の精算、有給休暇の残日数の買い取りなどが含まれます。普段は毎月の給与明細で自動的に処理されるため、あまり意識しない方が多いですが、退職時はイレギュラーな計算が発生しやすいのが特徴です。
たとえば、月の途中で退職する場合は給与が日割り計算になり、思っていたより手取りが少なくなることがあります。また、社会保険料は「前月分を翌月に支払う」仕組みなので、退職時には最後の給与から一括で差し引かれるケースもあります。私も初めて退職したとき、給与明細を見て「えっ、こんなに少ないの?」と本当に驚きました。よくよく確認すると、社会保険料や住民税の控除がまとめて引かれていたのが原因でした。
さらに、住民税についても注意が必要です。前年の所得に応じて課税されるため、退職後であっても支払いが続きます。会社によっては、退職時に最終給与から一括で徴収されることがあり、その月の手取りが大きく減ることもあります。「退職時の給与は通常よりも少なくなる可能性が高い」という前提を持っておくと、慌てずに済みます。
最終給与の計算ポイント
退職時に支給される最終給与は、通常の月の給与とは異なる計算になることが多く、思わぬ差が生じることがあります。普段は毎月一定の金額が振り込まれるため「給与は固定されたもの」と考えがちですが、退職のときには会社の規定や退職日によって細かく調整されるのです。
日割り計算になるケース
月の途中で退職する場合、その月の給与は日割りで計算されます。計算方法は会社によって異なり、「月の暦日数で割る」「出勤日数で割る」などのパターンがあります。たとえば月給30万円の人が15日で退職した場合、暦日数30日で計算すれば15万円となりますが、出勤日数ベースであれば金額が多少前後する可能性があります。
私自身、最初に退職したときは「月末退職」と「月中退職」でこんなに違うのかと驚きました。月末退職なら満額支給ですが、15日で辞めると半分程度になってしまいます。退職日を「月末にするかどうか」で、手取り金額が大きく変わるのは意外と知られていない重要ポイントだと思います。
家庭の立場からすると、子どもの習い事や住宅ローンの支払いなど、毎月決まった出費がありますよね。最終給与が日割り計算で大幅に減ると、その月のやりくりに直結します。あらかじめ計算方法を確認しておくことで「想定より少なくて困った!」という事態を避けられます。
有給休暇の残日数も反映される
もう一つ見落としやすいのが、有給休暇の未消化分です。退職時には残っている有給が給与として買い取られることがあり、この有給消化が最終給与の金額を大きく左右します。
私の場合、最後の1週間をすべて有給休暇で過ごしました。実際には出社していませんでしたが、その分もしっかり給与として支払われたので、収入が減らずに済みました。これは家計的にもとても助かりましたし、気持ちの面でも余裕をもって退職準備ができたと感じています。
会社によっては「退職時には有給を必ず消化してください」と指示されるところもあれば、「買い取り制度があるので出社してもしなくても支給される」というケースもあります。いずれにしても、有給休暇をどう扱うかで最終給与の額が変わるため、事前に総務や人事に確認しておくのがおすすめです。
また、退職日までに有給を消化するか、給与としてまとめて受け取るかはライフスタイルによって選び方も変わります。子どもの入学準備などで出費がかさむ時期なら給与として受け取ったほうが安心ですし、精神的にリフレッシュしたいなら有給を実際に休暇にあてるのも良い選択です。
社会保険料の精算
退職時にいちばん混乱しやすいのが社会保険(健康保険・厚生年金)の取り扱いでした。私も家計簿を開きながら「どの月の分が、いつ天引きされるの?」と夫と一緒にカレンダーで確認したほど。ポイントは「いつの保険料を、どの給与で払うのか」と「退職日の置き方」で大きく変わるところです。
保険料は「前月分」を当月に支払う
社会保険料は原則として“前月分を翌月の給与で”徴収します。たとえば4月に在籍していれば、その4月分の保険料は5月の給与から天引きされる形です。
私が6月末で退職したときは、7月の給与が出ないため「6月分の保険料」は最終(6月)給与からまとめて控除されました。思っていたより手取りが減って、「あ、ここで一気に引かれるのね」と家計を組み直したのを覚えています。
-
例(前月徴収のイメージ)
-
4月在籍 → 5月給与で4月分の保険料を控除
-
6月末退職 → 7月給与がないので、6月分は6月の最終給与で控除(または別途振込の案内)
-
給与が足りずに控除しきれない場合は、会社から振込の案内が届くこともあります。最終出社前に「不足分が出そうか」を総務に確認しておくと安心です。
退職日によって加入月数が変わる
社会保険は“月単位”の考え方で、社会保険料は「月末に在籍しているかどうか」でその月分の負担が決まります。
ここが退職日の決め方で一番効いてくるポイントでした。
-
1日付退職(例:9月1日退職)
月末(9月30日)に在籍していないため、9月分の保険料はかかりません。8月分までの負担で終了します。 -
2日以降の退職(例:9月2日〜30日退職)
月末(9月30日)に在籍している扱いになり、9月分の保険料も負担します。
私はこのルールを知らずに最初は月末退職を選んでしまい、結果としてもう1か月分の保険料がかかりました。家計的には痛かったので、次に転職したときは月初退職にして負担を1か月分減らせました。家庭の固定費や貯金計画を考えると、退職日の置き方は意外と大きな差になります。
退職後の健康保険の選び方(任意継続・国保・配偶者の扶養)
退職日の翌日から、会社の健康保険の資格はなくなります(資格喪失)。このあとどれに入るかで保険料と手続きが変わります。
-
任意継続(最長2年)
退職前に入っていた健康保険をそのまま個人で継続。申請期限は概ね「資格喪失日から20日以内」。会社負担がなくなるため、保険料は“これまでの自己負担+会社負担”に近い額になります(上限あり)。収入が安定している・医療費控除の観点で継続したい人向け。 -
国民健康保険(市区町村)
住民票のある自治体で手続き。原則「資格喪失から14日以内」が目安。前年所得などで保険料が決まるため、収入が下がる見込みならこちらのほうが安くなるケースも。 -
配偶者の健康保険の被扶養者
配偶者が社会保険加入なら、収入要件を満たせば扶養に入れる可能性があります。保険料負担はゼロ(ただし要件・審査あり)。私はパート勤務の時期にこの選択をして、家計の固定費をぐっと抑えられました。
どれが最適かは「今後の収入見込み」「家族構成」「自治体の保険料水準」で変わります。私は夫と試算をして、まずは扶養に、収入が増えたら見直す、という段階的な作戦にしました。
厚生年金からの切り替え(国民年金・第3号)
厚生年金の資格も退職日の翌日に喪失します。退職後は次のいずれかに。
-
国民年金(第1号)
自分で保険料を納付。経済的に厳しいときは「免除・納付猶予」の申請も検討できます。 -
国民年金(第3号:配偶者の扶養)
配偶者が厚生年金加入で、要件を満たせば第3号に。自分での保険料負担はありません。手続きは配偶者の勤務先経由が基本です。
私は出産後しばらく第3号にして、負担を抑えながら将来の年金記録を途切れさせないようにしました。切り替えの“空白期間”をつくらないのがコツです。
保険証の返却と医療費の注意
会社の健康保険証は退職時に返却が必要です。資格喪失後に誤って受診すると、後日10割相当の請求や返金手続きが発生することも。私は不安だったので、退職前に「次に病院へ行く予定」を家族で共有し、退職後すぐに使える保険(任意継続や扶養、国保)の手続きを先回りで進めました。お子さんの定期通院があるご家庭は、特にここを早めに整えると安心です。
標準報酬月額と「日割りなし」の落とし穴
社会保険料は「標準報酬月額」に基づく“月額制”。日割りという概念がありません。極端に言えば、月の2日だけ在籍していても、その月末に在籍していれば1か月分の保険料が発生します。ここを給与の日割り感覚で考えるとズレやすいので要注意です。
もし最終給与で控除しきれないとき
出勤日数が少なくて最終給与が小さい、賞与の予定がなくなった、などで控除不足になるケースもあります。会社によっては「持ち出し振込」「口座振替」「払込票での納付」など対応が異なるので、最終出社の1〜2週間前に総務へ確認しておくとスムーズ。私は振込用紙を前もって受け取り、家計の支払い日と合わせて納付しました。
税金(所得税・住民税)の取り扱い
社会保険料と並んで気になるのが税金でした。家計に直結するので、私は退職の準備をしながら夫と「年末調整はどっちの会社? 来年はいくら納める?」と何度も確認。ポイントを押さえるだけで見通しがグッと立てやすくなりました。
所得税の精算
年の途中で退職すると、その時点までの給与に対して源泉徴収されています。年末調整は「その年の12月に在籍している会社」が行うのが基本。年内に転職して12月の給与が新しい会社から支給されるなら、新しい会社で年末調整(前職の源泉徴収票の提出が必要)/年内に就労がないなら翌年に自分で確定申告、という整理で覚えておくと迷いません。リクルートエージェント
前職の源泉徴収票は、退職後おおむね1か月以内に交付されます。私は年末調整の書類締切が迫って焦ったことがあるので、「早めに発行をお願いする→受け取ったらすぐ転職先へ提出」を家計メモに書いておきました。生命保険料・地震保険料・iDeCo掛金などの控除証明も同封できるように秋ごろから集めておくと安心です。労務SEARCHdoda
確定申告が必要になる主なケースは、(1)年内に再就職していない、(2)転職したが12月給与がない、(3)副業などで別途所得がある、など。私はパートで再開した年は自分で申告して、源泉徴収されすぎていた分の還付を受けられました(申告は例年、翌年2月中旬〜3月中旬)。なお、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)は非課税で、これ自体の確定申告は不要です。リクルートエージェント
住民税の支払い
住民税は前年の所得に基づき、通常は「6月〜翌年5月」に12分割で会社から天引き(特別徴収)されます。退職すると残額の納付方法が変わり、退職の時期で取り扱いが分かれます。**1〜4月退職は原則一括徴収/5月退職はその月分のみ天引き/6〜12月退職は原則普通徴収(本人希望で一括も可)**という整理が実務上の目安です。横浜市公式サイト
バックオフィスの業務効率化なら「マネーフォワード クラウド」+1
-
1〜4月に退職
その年度(6〜翌5月分)の“未徴収分”を、最終給与または退職金から会社が一括徴収します(不足する場合は普通徴収へ切替)。私の知人は3月退職で3〜5月分がまとめて引かれ、手取りが想像より小さくなったので家計の立て直しが必要でした。バックオフィスの業務効率化なら「マネーフォワード クラウド」横浜市公式サイト -
5月に退職
そもそも残りは5月分だけなので、その月の給与から通常どおり天引きして終了。バックオフィスの業務効率化なら「マネーフォワード クラウド」 -
6〜12月に退職
新しい年度のスタート直後〜年末の退職は、原則普通徴収(自分で納付書払い・口座振替)に切替。希望すれば、残額を最終給与や退職金から一括徴収してもらうことも可能です。私は夏に退職したとき普通徴収にして、納付書が届いたら支払日を家計アプリに登録して忘れないようにしました。カシオヒューマンシステムバイトルバックオフィスの業務効率化なら「マネーフォワード クラウド」
実務の注意点としては、(1)一括徴収を希望するかは最終給与の手取りと要相談、(2)普通徴収に切り替わる場合は納付書の到着時期(退職後しばらくして届く)を家族で共有、(3)転職して再び特別徴収に戻す場合は新しい勤務先の手続きが必要——の3つ。私は一度、納付書の支払日を失念して延滞になりかけたので、退職月に「住民税の残額・納付方法・期日」をメモして冷蔵庫に貼っておきました。
家庭での対応と工夫
退職に伴う経理処理は、家計にまとまった影響が出やすいイベントでした。私の家では「今の収入」「来月以降の見込み」「一時的に増える支出」を家族でホワイトボードに書き出し、優先順位を決めていきました。退職月は“収入の凸凹”を前提に、家族で早めに見える化するほど家計は安定します。
家族で情報を共有する
まずは現状共有から。私は夫に「最終給与はこのくらい、ここから社会保険と住民税が引かれるから手取りはこの範囲」と伝え、子どもには「今月は外食を控えめにしようね」とシンプルに説明しました。
-
共有するポイント
-
退職日と最終給与の見込み
-
社会保険料や住民税の控除額の概算
-
健康保険の切り替え時期と医療費の想定
-
ボーナスの有無、退職金のタイミング
家族全員が「なぜ節約が必要か」を理解していると、日々の小さな我慢も前向きに受け止めやすくなります。わが家は冷蔵庫に“今月やめること・続けること”リストを貼り、達成できたら子どもにチェックを入れてもらいました。
-
生活費のシミュレーションをしておく
私はExcelでシートを3つ作りました。
-
キャッシュフロー表(月内の入出金の時系列)
-
固定費の棚卸し(家賃、通信、保険、サブスクなど)
-
一時費用のリスト(住民税の納付書、保険切替費用、引越し予定など)
最終給与の“手取り見込み”を入れると、赤字になる週が一目でわかります。対策として、支出の先送りや前倒し、分割払いへの切り替えを検討。私は通信費のプラン変更を退職前に済ませ、翌月の固定費を2,000円ほど下げられました。
支払いスケジュールを再設計する
退職前後は、住民税の納付書到着や社会保険の切替など、支払いが“いつ来るか”が読みづらい時期。
-
家計カレンダーに記入する項目
-
最終給与の支給日
-
住民税の納付期限(普通徴収になった場合)
-
健康保険の切替申請期限と保険証受領予定日
-
家賃や学費、習い事費の引落日
私は「支払日−3日」を“準備日”として登録し、口座残高を前日までに整える運用に。これで延滞の不安がなくなりました。
-
固定費の一時ダウングレードを検討する
一生の見直しでなくて大丈夫。“退職月と翌月だけ”の期間限定ルールにすると家族も納得しやすいです。
-
サブスクは無料期間やライトプランへ
-
スマホは通話定額を外し、必要なときだけ追加
-
電気・ガスのセット割や見直しを試算
私は動画サービスを一時停止し、電子書籍の読み放題に一本化。子どもには図書館をフル活用してもらいました。
緊急資金とブリッジ資金を分けて管理する
私は封筒を2つ用意しました。
-
緊急資金(医療費や急な修理費)
-
ブリッジ資金(退職月の赤字を埋めるための一時的な補填)
どちらも上限を決めておくと、使いすぎを防げます。退職金が出る場合は、まずブリッジ資金を補充してから貯蓄に回すと、翌月以降が安定します。
子どもの気持ちに寄り添う
節約は家族の協力があってこそ。私は「今月だけおやつを手作りにしよう」「週末は公園でピクニックにしよう」と代替案を用意しました。子どもが自分で選べる余地をつくると、節約が“楽しい自分ごと”になります。
医療・保険の“空白”を作らない
退職後の保険証が使えるようになるまでの間、子どもの通院が入らないか確認。私は、任意継続や扶養への切替の提出期限をカレンダーに登録し、保険証の受取予定日まで家族LINEに固定メッセージで掲示しました。必要に応じて薬の処方は退職前に余裕を持って受け取っておくと安心です。
収入の“次の一歩”を小さく始める
私の場合、退職翌月はパートで短時間勤務をスタート。最初からフルで働けなくても、“毎週〇曜日の午前だけ”のように小さく始めると気持ちも家計も安定します。履歴書や必要書類の準備を退職前に進め、面接日程も退職後すぐに組めるようにしておくとスムーズでした。
書類とToDoを一枚に集約する
離職票、源泉徴収票、保険の資格喪失証明、住民税の案内など、退職前後は紙が増えます。私はA4クリアファイル1冊を“退職ファイル”にして、
-
表紙にタイムライン(退職日→保険切替→納付→再就職)
-
付箋で「申請済」「待ち」などのステータス
-
最後に問い合わせ先一覧(総務・健保・自治体窓口)
を整理。探し物の時間が減り、手続き漏れも防げました。
退職金・還付金の使い道ルールを決める
退職金や確定申告の還付が見込める場合、使い道をあらかじめ3区分にしておくとブレません。
-
生活防衛資金(3か月分)
-
ブリッジ資金の補充
-
将来投資(資格取得や仕事道具、学習)
私は“お祝い枠”も少額で用意し、家族で回転寿司に行きました。節約のなかにも小さな楽しみがあると、次のステップに気持ちよく進めます。
まとめ|退職後の生活を安心してスタートしよう
退職時の経理処理は、最終給与の計算や社会保険料・税金の精算など、普段意識していない部分で大きな差が出ます。事前に理解しておけば「思ったより少ない!」と慌てることも減らせます。家族と共有しながらシミュレーションを立て、必要に応じて退職日を調整するのも有効です。退職後の新しい生活を安心して迎えられるよう、今のうちに準備を進めていきましょう。