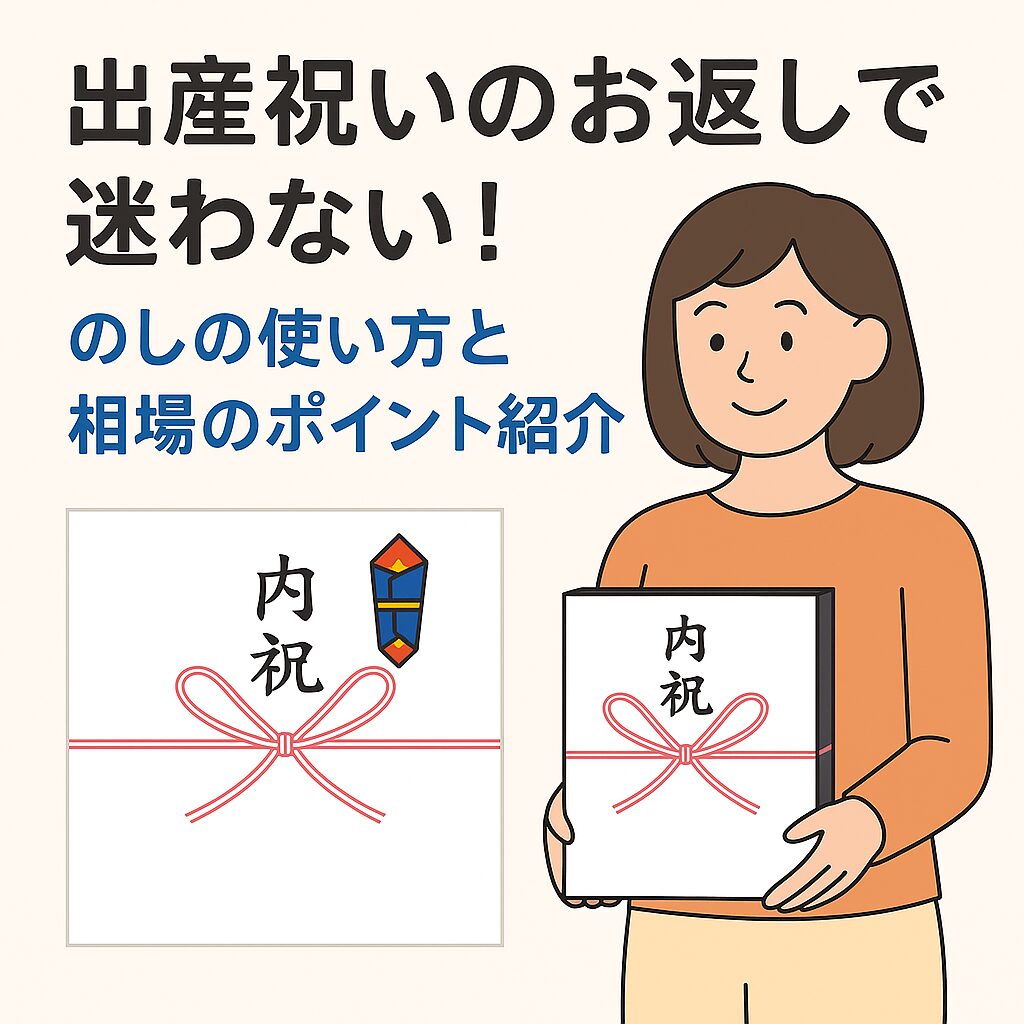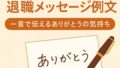出産祝いのお返しを準備する際、「のしの種類は?」「書き方は合ってる?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
実は、のしの選び方や水引の結び方には、出産祝いならではのマナーがあるのです。
この記事では、出産祝いのお返しで迷わないために、のしの正しい使い方や相場の目安、表書きのルールなどをわかりやすくご紹介します。
初めての方でも安心して準備ができるよう、実例やポイントを交えて丁寧に解説していますので、ぜひ参考にしてください。
出産祝いのお返しのしの選び方
出産祝いとは?
出産祝いとは、赤ちゃんの誕生という人生の大きな節目を祝って、親しい人やお世話になった人に贈るプレゼントのことです。親族や友人、職場の同僚など、さまざまな立場の人から贈られることが多く、贈り物の内容は多岐にわたります。現金を包む場合もあれば、スタイやおむつケーキ、哺乳瓶などの実用的なベビー用品、お菓子や紅茶の詰め合わせといった家族向けのギフトも人気です。
また、近年では贈る側がオンラインショップなどを利用して、直接配送するケースも増えており、個人だけでなく企業や取引先から贈られることもあります。贈るタイミングは、生後7日(お七夜)から1か月以内が一般的とされています。
お返しをする理由
いただいた出産祝いへの感謝を込めて贈るのが「内祝い(うちいわい)」です。本来「内祝い」とは、身内の喜びごとをおすそ分けする意味合いがありましたが、現在では「お返し」としての意味合いが強くなっています。
お祝いをいただいた方に対して、きちんとした形でお礼を伝えることで、感謝の気持ちを示すとともに、相手との関係を良好に保つことができます。特に職場や親戚付き合いにおいては、適切なタイミングで丁寧なお返しをすることが社会人としてのマナーとも言えるでしょう。相手の立場や関係性に合わせた品物選びも大切です。
のしの重要性と役割
出産祝いのお返しには、品物とともに「のし紙」をかけるのが基本です。この「のし」は、日本の贈答文化における礼儀を表すもので、形式的ながらも心を込めた感謝の証となります。のし紙があるだけで、「感謝の気持ちをしっかり形にした丁寧なお返し」という印象を相手に与えることができるのです。
特に出産祝いのお返しでは、紅白の「蝶結び」の水引を用いたのしを使用します。これは「何度あっても良い慶びごと」という意味を持ち、繰り返しの幸せを願う縁起の良い結び方です。また、のしの表書きには「内祝」と記し、贈り主である赤ちゃんの名前を入れるのが一般的です。
のし紙は贈り物の第一印象を決定づける大事な要素。だからこそ、正しく選び、丁寧に書くことが求められます。
のしの種類と使い方
内のしと外のしの違い
「内のし」と「外のし」は、のし紙のかけ方の違いによって、相手に与える印象やマナーの度合いが異なります。
-
内のしとは、包装紙の内側にのし紙をかける方法です。贈る側の控えめな姿勢が表れるため、親しい友人や家族、気のおけない相手に贈る際に選ばれることが多いです。また、のし紙が内側にあることで、配送時などに汚れにくいという実用的なメリットもあります。
-
外のしは、のし紙を包装の外側にかける方法で、のしの表書きが一目で見えるのが特徴です。相手にしっかりと「感謝の気持ちを伝えたい」「丁寧に対応したい」という意思が伝わりやすく、特に目上の方や職場関係など、きちんとした印象を大切にしたい場合に適しています。
贈る相手との関係性や贈る場面に応じて、内のし・外のしを使い分けることが大切です。
水引の種類とその意味
水引とは、のし紙に使われる装飾的なひもであり、日本独自の贈答文化を象徴する存在です。結び方や色の組み合わせには意味があり、シーンによって適切な選択が求められます。
出産祝いのお返しでは、紅白の「蝶結び(花結び)」が基本とされています。これは、「何度あっても良い喜び事」という意味が込められており、出産のような慶びの出来事に最適です。赤と白は祝い事を象徴する色であり、祝意をしっかりと表現できます。
一方で、水引には他にも金銀や黒白など、色や本数にバリエーションがあります。例えば黒白は弔事用、金銀は結婚など格式高い慶事向けとされています。選び方を間違えると失礼にあたるため、シーンに合った水引を選ぶことが非常に重要です。
蝶結びと結び切りの使い分け
水引の結び方には、「蝶結び」と「結び切り」という2つの代表的なスタイルがあります。それぞれに込められた意味が異なるため、用途に応じた正しい使い分けが求められます。
-
蝶結びは、何度でも結び直せる形状から「繰り返しても良いこと」を象徴しています。そのため、出産・入学・新築祝いなど、再び起こってもおめでたいとされる慶事に使用されます。出産祝いのお返しにはこの蝶結びが一般的です。
-
結び切りは、一度結ぶと解けない結び方で、「これきりにしたい」「繰り返したくない」という意味合いを持ちます。結婚やお見舞い、弔事といった、一度きりが望ましいイベントに適しています。
このように、結び方の選択は形式的なものではなく、相手への思いやりや配慮を示す大切なポイントです。
お返しの金額の目安
出産祝いの相場
出産祝いとして贈られる金額にはある程度の相場がありますが、贈る側の立場や関係性、地域によっても多少の差があります。
一般的に、友人や親戚からの出産祝いは5,000円〜10,000円前後が相場です。仲の良い友人であれば5,000円程度、兄弟姉妹などの近しい親族には10,000円以上のこともあります。また、祖父母や兄姉が出す場合には、20,000円〜30,000円といったケースも見られます。
職場から贈る場合には、部署単位で連名になることが多く、1人あたりの負担は1,000円〜3,000円程度が一般的です。部署全体でまとめて5,000円〜10,000円程度のギフトを用意する形が多く、無理のない範囲で喜ばれる品を選ぶのがポイントです。
相手との関係性による金額の変化
出産祝いの金額は、贈る相手との「心理的な距離感」や「社会的な立場」によっても自然と変わってきます。
たとえば、親や祖父母、兄弟姉妹などの親族は、家族としての立場から比較的高額になる傾向があります。また、職場の上司や目上の親族など、礼儀や形式を重んじる相手には、金額だけでなく品の選び方や包装にも一層の配慮が求められます。
逆に、同僚や友人、知人などの気軽な関係であれば、無理のない範囲の金額で気持ちを伝えることが大切です。過度な高額品は、かえって相手に負担を感じさせてしまうこともあるため注意が必要です。
贈り物の内容と金額のバランス
出産祝いのお返しである「内祝い」では、贈られた金額に対して1/3〜半額程度が返礼の目安とされています。
例えば10,000円の出産祝いをいただいた場合は、3,000〜5,000円程度の品物を選ぶのが適切です。ただし、きっちりと金額を合わせる必要はなく、あくまで「感謝の気持ちを表すためのギフト」であることを意識することが大切です。
また、内祝いの品には実用的で日常的に使えるものや、消え物(お菓子・お茶・洗剤など)が好まれる傾向にあります。相手の家族構成や好みを考慮し、喜ばれるアイテムを選ぶことで、お返しの印象も大きく変わってきます。
なお、高価すぎる内祝いは、受け取る側に「また何かお返しをしないと…」という心理的負担を与える可能性があるため、適正な金額設定を意識しましょう。
のし紙の書き方マナー
表書きのポイント
出産祝いのお返しにかけるのし紙には、上段に「内祝(内祝い)」と記載するのが一般的です。「出産内祝」と書く方もいますが、「内祝」だけでも十分に意味が伝わります。
下段には、赤ちゃんの名前を贈り主として記載します。両親の名前を書くのではなく、赤ちゃんの名前で贈ることで「この子の誕生を祝ってくれてありがとう」という意味合いを込めることができます。これは、出産が家族にとって大きな慶びであることを伝える、日本独自の慣習です。
名字は基本的に不要で、名前だけを中央に記すのが一般的です。ただし、名字を入れてもマナー違反ではありません。地域や家庭の慣習によって柔軟に対応するとよいでしょう。
名前の書き方(ふりがな含む)
赤ちゃんの名前は、まだ読み慣れていない人も多いため、ふりがなを添えることをおすすめします。ふりがなはひらがなで、名前の下または横に小さく記載します。
例:
結(ゆい)
悠翔(はると)
心陽(こはる)
名前の読み方が珍しい・難読な場合は特に重要で、相手が迷わず読めるように配慮することがマナーです。ふりがなを入れることで、相手に対しての思いやりや細やかな心遣いが伝わり、印象もぐっと良くなります。
また、毛筆や筆ペンで丁寧に書くと、より格式を感じさせることができるのでおすすめです。
メッセージカードの記載方法
のし紙だけでなく、一言添えたメッセージカードがあると、ぐっと温かみのある印象になります。形式ばった言葉でなくても大丈夫です。大切なのは「感謝の気持ちをきちんと伝える」ことです。
以下は、出産祝いのお返しに適した文例です。
このたびは心温まるお祝いをいただき、誠にありがとうございました。
おかげさまで母子ともに元気に過ごしております。
感謝の気持ちを込めて、ささやかではございますが内祝いの品をお贈りいたします。
また、カジュアルな関係性であれば、もう少し柔らかいトーンでも問題ありません。
このたびは素敵な出産祝いをありがとうございました!
とても嬉しかったです。
ささやかではございますが、感謝の気持ちを込めて内祝いをお送りします。
手書きで一言添えるだけでも、気持ちの伝わり方が格段に変わります。可能であれば印刷+手書きの併用もおすすめです。
職場への出産祝いのお返し
職場でのマナーと注意点
職場で出産祝いをいただいた場合、特に注意したいのが全体への配慮と公平性です。個別にお返しをするよりも、部署やチームごとにまとめてお返しするのが一般的で、実務上もスムーズです。
連名でいただいた場合は、お名前や金額を細かく確認する必要はなく、一律にお礼の気持ちを表す形でまとめてお返しするのがベター。お菓子や飲み物などの「消え物」を選ぶことで、全員で気軽に楽しんでもらえます。
また、オフィスでのやり取りになるため、配布のしやすさ・置きやすさ・清潔感なども考慮しましょう。感謝の気持ちを伝えることが最優先ですが、形式ばらずともビジネスマナーを意識することが大切です。
ギフト選びのコツ
職場への出産内祝いを選ぶ際は、「誰もが気兼ねなく受け取れるもの」であることがポイントです。とくに以下のようなギフトが喜ばれやすいです。
-
個包装のお菓子(焼き菓子、フィナンシェ、チョコレートなど):分けやすく、衛生面でも安心。
-
日持ちのする食品:賞味期限が長いものを選ぶことで、人数の多い職場でも無理なく消費できます。
-
おしゃれなパッケージ:デスクや休憩スペースに置いても見栄えが良い、清潔感あるデザインが◎。
また、「のし」は外のしにして丁寧な印象を演出すると、上司や年配の方にも誠意が伝わりやすくなります。高価すぎるものよりも、「ちょっと嬉しい」ラインのものを選ぶと好印象です。
内祝いの例とテンプレート
職場向けの内祝いに添える一言メッセージも、形式を押さえつつ温かさが感じられる表現が理想です。
フォーマルなテンプレート例:
このたびは温かいお祝いをいただき、誠にありがとうございました。
感謝の気持ちを込めて、ささやかではございますが内祝いの品をお贈りいたします。
お時間のある際に、ぜひ皆さまでお召し上がりください。
カジュアルなテンプレート例:
素敵なお祝いをありがとうございました!
感謝の気持ちを込めて、お菓子を用意しましたので、休憩時間などにぜひ皆さまでどうぞ♪
いずれの場合も、封筒入りの一筆箋やカードに手書きで添えると、さらに印象が良くなります。
双子や三つ子の場合のお返し
特別な配慮が必要な理由
双子や三つ子など、多胎児の出産を祝っていただく機会は多くなりがちです。親族や友人だけでなく、ご近所や職場の同僚など、複数人から立て続けに出産祝いをいただくケースも珍しくありません。
そのため、一般的な1人出産のケースよりも、お返しする件数や合計金額が大きくなる傾向があります。もらった側も「たくさんいただいたから、きちんとお礼をしなければ」と感じる場面が多く、結果として相場よりやや高めのお返しを用意することも自然な流れです。
ただし、「人数が多い=返す総額も比例して高くなる」という感覚ではなく、いただいた金額や相手との関係性に応じて柔軟に対応することが大切です。大切なのは“金額”よりも“心遣い”を伝えることです。
容量と金額の考え方
多胎児の場合、「2人分」「3人分」と考えがちですが、出産内祝いの基本はあくまで“いただいた金額に対して”お返しをすることです。
例えば、双子だからといって1万円の出産祝いをいただいた場合に、2万円分のお返しをする必要はありません。内祝いの相場(1/3〜1/2程度)に従い、3,000〜5,000円程度が適切なラインとなります。
ただし、お祝いの品が高額だったり、名入れギフトや記念品のような特別なものをいただいた場合は、それに見合うように少し豪華なお返しを検討しても良いでしょう。感謝の気持ちを無理のない範囲で伝えることが、最も大切なポイントです。
お返しの種類の提案
双子・三つ子などの出産祝いへのお返しには、「特別感」と「実用性」のバランスが取れたギフトが人気です。以下のようなアイテムが多く選ばれています。
-
高品質なタオルセット:実用的でありながら上品な印象を与えるため、年代や性別を問わず喜ばれます。
-
スイーツの詰め合わせ:家族で楽しめる内容になっており、華やかなパッケージで贈り物感もUP。
-
名入れギフト(お菓子、ハンカチなど):赤ちゃんの名前が入ったギフトは、オリジナル感があり、記念としても好評です。
-
カタログギフト:好みがわからない場合や複数人宛てに贈るときに便利。選ぶ楽しみもプレゼントできます。
特に「複数の赤ちゃんが生まれたこと」を想起させる、華やかで優しいデザインのラッピングやカードを添えると、印象もより良くなります。贈る側の心遣いが伝わるように工夫するのが、成功のカギです。
結婚や新築と出産祝いのお返し
ハーモニックなギフト選びとは
出産と引っ越し、新築や結婚など、複数の慶事が重なった場合のお返し(内祝い)には、ひと工夫が必要です。一つの贈り物でまとめてお返しをするのではなく、それぞれの「お祝いの目的」に合わせたお返しを用意するのがスマートな対応です。
たとえば、「出産祝い」と「新築祝い」の両方をいただいた場合、それぞれの内容や贈ってくれた人の立場に応じて、個別にお返しすることが丁寧な印象を与えます。一緒に済ませる場合でも、「二つのお祝いへの感謝を込めて」など、メッセージで意図を明確にすることが重要です。
こうした対応により、受け取る側も「気遣ってくれた」「丁寧だな」と感じ、良好な関係性の維持につながります。ハーモニック(調和のとれた)なギフト選びとは、品物そのものだけでなく、気配りと文脈を大切にする贈り方を意味するのです。
慶事における贈り物のルール
慶事(お祝い事)が重なること自体に問題はありませんが、「お祝いを返す=一方通行の感謝の気持ち」であることを理解しておきましょう。
たとえば、自分が出産祝いをもらって、その相手が結婚や引っ越しをしたとしても、「お返し」として贈るのはマナー違反です。相手の慶事に便乗してお返しするのは、結果的に“お祝いを返した”形になり、マナー上望ましくありません。
また、慶事と弔事が近い時期に重なる場合には、祝い事を先に済ませ、後日に弔事に関する対応を分けて行うことが一般的です。それぞれの意味をしっかりと尊重し、節度ある対応が大切です。
共通するマナーと注意点
出産や新築、結婚など、どの慶事であっても共通して守りたい基本マナーがあります。
-
のし紙は「内祝」と表書きし、贈り主の名前を記載する(出産祝いでは赤ちゃんの名前のみ)
-
水引は紅白の「蝶結び」を選ぶ(繰り返しても良い慶事向け)
-
ラッピングは清潔感と品を重視。カジュアルすぎず、フォーマルすぎない中間が無難
また、複数人に贈る場合や相手の年齢層が幅広い場合は、誰でも喜ばれる実用的なアイテム(タオル、食品、カタログギフトなど)を選ぶのが安全策です。
さらに、包装やカード、送り状にさりげないメッセージを添えると、相手に与える印象が大きく変わります。気持ちが伝わるように、形式だけでなく“心を添えた贈り物”を意識しましょう。
出産祝いのお返しの時期
お返しを贈る適切なタイミング
出産祝いのお返し(内祝い)を贈る時期は、赤ちゃんの誕生から1ヶ月前後、いわゆる「お宮参り」の時期が一般的な目安とされています。お宮参りは、生後約30日前後に行う習わしで、内祝いもそのタイミングに合わせて準備する人が多いです。
実際には、出産直後は育児や生活の変化でバタバタしがちな時期。だからこそ、事前にリストを作って準備しておくと安心です。最適なタイミングは生後1ヶ月〜2ヶ月以内、遅くとも3ヶ月以内には贈るのが礼儀とされています。
早すぎると「形式的」と受け取られることもあり、逆に遅すぎると「忘れていたのかな?」と思わせてしまうことも。感謝の気持ちをタイミング良く伝えることが、より良い印象につながります。
地域毎の慣習の違い
出産祝いのお返しのタイミングや形式には、地域ごとに微妙な違いがあることも知っておきたいポイントです。
たとえば、関西地方では「お七夜(生後7日目)」の段階で内祝いを贈る風習がある地域もあります。一方で、東日本ではお宮参り後や命名の報告を兼ねて贈るのが一般的です。
また、地方によっては「いただいた金額以上の品をお返しする」ことを美徳とする考え方があったり、「家族単位でまとめてお返しをする」文化が根づいていたりもします。
そのため、相手が住んでいる地域の慣習に配慮したり、自分の地域のしきたりを踏まえたうえでの対応が求められます。迷ったときは、年配の家族や親戚に相談するのがベストです。
年内にお返しをする理由
もし年末が近いタイミングで出産祝いをいただいた場合、なるべく年内にお返しを済ませるのが望ましいとされています。これは、「新年を越さない=気持ちをすぐに伝える」姿勢が、礼儀正しく丁寧な印象を与えるためです。
また、年をまたぐと相手の記憶も薄れやすくなり、「お祝いを贈ったことへの反応がなかった」という誤解を生む可能性もあります。特に年賀状のやりとりなどで「あれ?お返しは…?」と意識される時期でもあるため、年内にお返しを贈っておくと双方にとって気持ちよく新年を迎えられます。
忙しい年末こそ、スケジュールに余裕をもって内祝いの準備を進めましょう。贈る側の気配りが、感謝の気持ちをより伝わりやすくする鍵となります。
贈り物の包装と見栄え
人気の包装方法
出産祝いのお返し(内祝い)は、贈る品物そのものはもちろん、包装の仕方も印象を大きく左右する重要な要素です。最近では、見た目にも美しく、実用性や環境への配慮も考慮された包装スタイルが人気を集めています。
-
ギフト用の化粧箱入り:高級感があり、のし紙との相性も抜群。正式なお返しや目上の方への贈答に適しています。
-
風呂敷包み:和のテイストが感じられるため、年配の方や目上の方に贈る場合に好印象。最近ではモダンなデザインの風呂敷も人気です。
-
木箱入り・缶入り:高級感と保存性を兼ね備えた包装スタイルで、特別感を演出できます。
包装と「のし」の見た目や色のバランスを整えることで、上品で丁寧な印象に仕上げることができます。
自宅でできる簡単なラッピング
カジュアルな関係の相手や、手作りの要素を加えたい場合には、市販のアイテムを活用した簡単ラッピングでも十分です。
-
リボン付きの紙袋:市販のギフトバッグに商品を入れ、サテンリボンやタグを添えるだけでも十分に華やか。
-
クラフト紙+シール:ナチュラル系の印象を与えるクラフト包装は、温かみがあり好印象。ポイントにメッセージシールやスタンプを使うと、ひと工夫感が出せます。
-
透明のラッピングバッグ:中身が見えることで安心感があり、焼き菓子や小物系のギフトに最適です。
手軽ながらも、メッセージカードやタグで感謝の気持ちを添えるだけで、グッと印象が良くなります。
手渡しと郵送時の注意点
出産祝いのお返しを「手渡しするか」「郵送にするか」は、相手との距離やタイミングに応じて選びましょう。
-
手渡しの場合:訪問の際は、相手の都合を事前に確認し、無理のない時間帯に。挨拶の言葉と一緒に、笑顔で渡すのが基本です。急に訪れるのはNG。
-
郵送の場合:宅配便を利用する際には、のし紙の上からプチプチなどで丁寧に包み、送り状やお礼のメッセージカードを必ず同封するようにしましょう。メッセージがあるだけで、「丁寧に対応してくれた」と感じてもらえます。
どちらの方法でも共通するのは、「相手に配慮したタイミングと気持ちの伝え方」。包装や演出を丁寧に行うことで、感謝の気持ちがよりしっかりと伝わります。
まとめ|正しいのし選びで感謝の気持ちを伝えましょう
出産祝いのお返しは、相手への感謝を形にする大切なマナーです。のしの選び方や書き方、水引の種類には、それぞれ意味やルールがあります。特に「蝶結び」の水引は出産祝いに適しており、のし紙には赤ちゃんの名前を書くのが基本です。
相場の目安や贈るタイミングにも配慮することで、より丁寧で好印象なお返しになります。迷ったときは、今回ご紹介したポイントを参考に、心を込めた内祝いを準備してみてください。