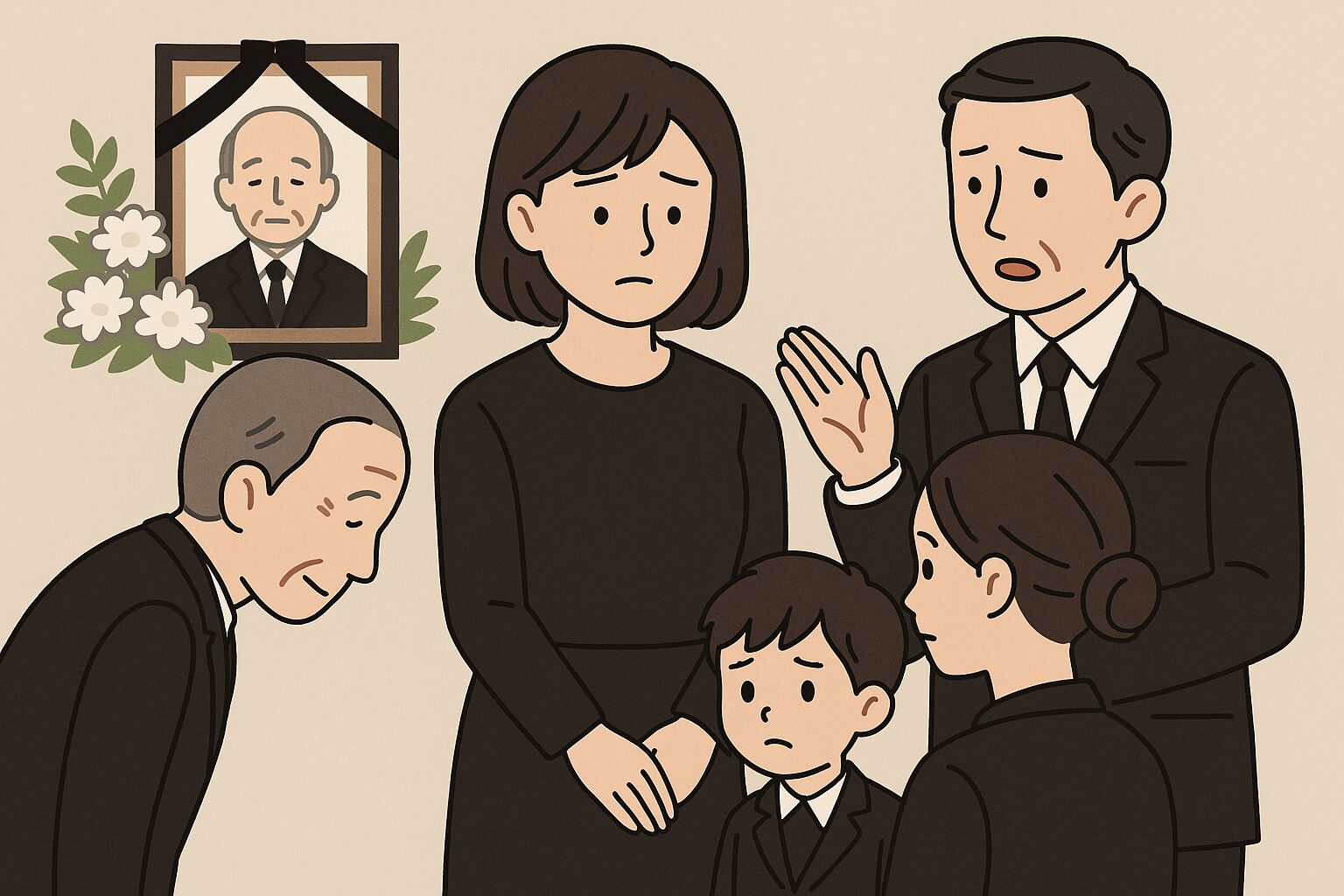「こんなとき、何を話せばいいの?」
祖母の葬儀に参列したとき、私が真っ先に思ったのはこの一言でした。喪主ではないけれど親族として参列し、お手伝いや来客対応をする立場になったとき、挨拶の言葉選びに戸惑う場面がたくさんあったんです。
とくに小さな子どもを連れての参列だったこともあり、気も使うし、失礼がないようにと焦ってしまって…。
この記事では、私自身の体験をもとに、葬儀で親族が使える挨拶の例文や、実際にどのタイミングで何を言えばよかったのかをまとめています。
形式ばりすぎず、けれどきちんと気持ちが伝わる言葉で、心を込めた挨拶ができるように——
そんなヒントになればうれしいです。
親族として「挨拶が必要な場面」は意外と多い

祖母の葬儀に参列したとき、喪主は私の伯父で、私は孫の立場でした。
いわゆる「親族のひとり」として列席することになったわけですが、ただ座っているだけというわけにはいきませんでした。
葬儀の準備や進行は意外と慌ただしく、親族の誰かが自然と動くことになります。
私も、会場の案内や受付の手伝いをしているうちに、思っていた以上に人前で挨拶する場面が多かったことに気づいたんです。
そのたびに、「こういうとき、何て言えばいいんだろう…」と迷うことがたくさんありました。
弔問客へのあいさつ
葬儀当日、私は親族代表として受付に立ちました。
いざ弔問客がいらっしゃると、香典を受け取るだけでなく、ちょっとした言葉も必要になります。
最初の頃は、
「ご会葬ありがとうございます」
とだけ、形式的にお伝えしていましたが、何人も何人もお越しになるうちに、なんだか気持ちがこもっていないような気がしてしまったんです。
そこで少し言葉を添えるように変えました。
たとえば、
「遠いところをお越しいただき、ありがとうございます」
「足元の悪い中、わざわざありがとうございました」
など、相手の状況に合わせた一言をつけ加えるだけで、表情もやわらぎ、気持ちのやりとりが生まれるように感じました。
なかには、祖母ととても親しかった方もいて、「最後に顔を見れてよかった」と声をかけてくださる方も。
そのときは、「本人も喜んでいると思います」とだけ返しましたが、本心からそう思えた一言を伝えられてよかったと思っています。
お通夜や告別式後のあいさつ
通夜や告別式が終わると、親族控室でホッと一息つける時間がやってきます。
そこでも、親族同士で自然に言葉を交わす場面がありました。
「今日は本当にありがとうございました」
「無事に終わってよかったね」
「お疲れさまでした」
そんな何気ない一言ですが、共に時間を過ごした親族への労いの気持ちが込められていると、あたたかいやりとりになります。
とくに、遠方から来てくれた親族や、高齢で参列してくれた祖父母世代には、しっかりと目を見て声をかけるようにしました。
「長旅で大変だったでしょう。来てくれてありがとう」
「〇〇伯母さんの顔が見られて、祖母もきっと喜んでいると思います」
場の空気を読んで静かにしているだけでは、気持ちは伝わりにくいこともある。だからこそ“言葉にする”ことが大事なんだなと、しみじみ感じました。
お手伝いの方への感謝
今回の葬儀では、伯母やいとこたちが率先して動いてくれたおかげで、本当にスムーズに進みました。
受付に立ってくれたり、式場の席順を整えてくれたり、進行のサポートまで…。
みんな自分の役割に集中していたので、式の最中はあまり言葉を交わせなかったのですが、落ち着いたタイミングで、
「今日は本当に助かったよ」
「〇〇ちゃんが受付してくれて安心だった」
と声をかけるようにしました。
こういう場では、“ありがとう”の一言が、何よりも大きな労いになるんだと感じました。
普段はなかなか感謝を伝える機会が少ない親族同士でも、葬儀という場を通して、関係が深まったような気がします。
そしてふと、「ああ、こうやって家族ってつながってるんだな」って思えたんです。
きっと、祖母がくれた最後の“時間”だったのかもしれませんね。
場面別|親族としての挨拶例文集

ここからは、私自身が祖母の葬儀で実際に使ったり、「これは言ってよかったな」と感じた挨拶の言葉を、場面ごとにご紹介します。
事前に何パターンか用意しておくと、当日バタバタしても落ち着いて言葉を選べます。
あまりかしこまりすぎず、でも礼儀を忘れずにが、私の中での大事な基準でした。
弔問客への受付時のあいさつ
葬儀の受付では、親族代表として香典を受け取るだけでなく、一言二言のあいさつも求められました。
たとえばこんな言葉を使いました。
-
「本日はご会葬ありがとうございます」
-
「お忙しい中、お越しいただきありがとうございます」
-
「足元の悪い中、ありがとうございます」
最初は緊張して、言葉がつっかえてしまうこともありましたが、徐々に落ち着いて対応できるように。
表情をやわらかくして、目を見てお礼を伝えることで、気持ちがしっかり伝わるように感じました。
特に高齢の方や、足元が不安そうな方には、
「お足元に気をつけてお進みください」などとひと言添えると、安心してもらえたように思います。
ご高齢の方や親しい関係の方へ
祖母のご近所さんや、昔から家族ぐるみで付き合いのあった方々には、少し踏み込んだ言葉も使いました。
-
「遠いところを本当にありがとうございます」
-
「〇〇さんにも最後にお顔を見ていただけて、祖母も喜んでいると思います」
-
「いつも祖母を気にかけてくださって、ありがとうございました」
故人とのつながりに少しだけ触れることで、相手の気持ちにもそっと寄り添える挨拶になると感じました。
実際、「そう言ってもらえると嬉しいわ」と涙ぐまれる方もいて、思い出を共有できたような気持ちになりました。
ときには、相手の方から「〇〇さんは優しいおばあちゃんだったね」と思い出話をしてくださることもあり、こちらの緊張も自然とほぐれていきました。
式後の親族同士のあいさつ
通夜や告別式が終わったあと、親族同士で控室に戻ると、みんな少しホッとした表情になります。
そのタイミングで、こんなあいさつを交わしていました。
-
「今日は一日お疲れさまでした」
-
「お手伝い、本当に助かりました」
-
「明日もよろしくお願いします」
手伝ってくれた親族にはしっかりお礼を伝え、遠方から来てくれた人には「今日は泊まり?」「ゆっくりできそう?」などの声かけも。
かしこまった言葉よりも、素直な感謝やねぎらいの気持ちを口にすることが、親族間ではとても大切だと感じました。
葬儀という非日常のなかで、身内の支えがあることは本当に心強く、その気持ちを言葉にすることでお互いの距離も縮まったように思います。
葬儀の「流れ」と挨拶のタイミングを知っておこう
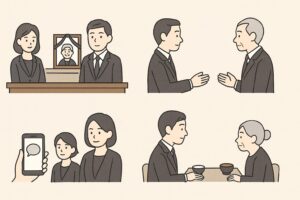
葬儀の当日はバタバタと慌ただしく、考える余裕もあまりありません。だからこそ、どんな流れで進むのか、どのタイミングで挨拶が求められるのかを事前にイメージしておくだけで、気持ちにかなり余裕が持てました。
とくに私は、祖母の葬儀で孫という立場でしたが、親族の一員としてしっかり動く必要があり、役割の多さに驚きました。
以下に、通夜から葬儀、そしてその後までの流れと、それぞれで必要な挨拶のタイミングをまとめてみます。
通夜の日(前日)
前日の通夜から、すでに人が集まり始め、親族としての対応が求められます。
弔問客の受付対応(挨拶)
夕方から始まることが多い通夜では、早めに到着した方への対応もあり、受付は比較的長い時間開いています。
香典を受け取るだけでなく、
-
「お足元の悪いなか、ありがとうございます」
-
「お忙しい中、わざわざ恐縮です」
といった言葉を添えるように心がけました。
受付は“はじめて会う人と一番多く接する場”でもあるので、言葉づかいや表情に気をつけるようにしました。
会場でのお出迎え・誘導
初めて来られる方は戸惑うこともあるので、「こちらでお焼香をお願いいたします」「お席はこちらになります」など、やさしく声をかけるようにしました。
案内が必要な場面では、迷っている方にそっと声をかけられると、全体の雰囲気もやわらぎます。
通夜振る舞いでの軽い会話
通夜後の食事の席では、緊張が少しほぐれるぶん、話しかけやすくなります。
「寒い中、ありがとうございました」「どうぞ温かいものを召し上がってください」などの軽い一言でも、場をあたためる役割を担えることがあるんだなと感じました。
告別式当日
本番とも言える告別式の日は、朝からスケジュールが詰まっており、参列者・親族どちらにとっても慌ただしい1日になります。
会場でのあいさつ
開式前の控室や待合スペースでの「本日はありがとうございます」「お世話になりました」の一言が、式に向かう静かな空気をつくってくれます。
とくに遠方から来てくださった方には、一言感謝を伝えるだけで“こちらの気持ちが伝わる”のだと実感しました。
火葬場での同行中の会話
火葬の間は待ち時間も長く、沈黙が多くなりがちです。
そんなときに、「祖母、ほんとにお花が好きだったよね」とか「よくあの公園でお散歩してたよね」なんて、思い出をぽつりと語ることで、自然と空気が和らぐ瞬間がありました。
沈黙を破ろうと無理に話す必要はないけれど、少しの言葉が場をほぐしてくれることもあります。
精進落としでのあいさつや会話
お食事を共にする精進落としでは、ある程度リラックスした雰囲気になります。
「今日は本当にありがとうございました」
「遠いところをお越しいただいて助かりました」など、改めて感謝を伝える場でもあります。
故人との思い出話を共有できる最後の場でもあり、親族・弔問客問わず、みんなで気持ちをまとめられる貴重な時間でした。
後日
葬儀が終わっても、親族としての役目は続きます。
香典返しの連絡や手配
四十九日やその前後に、香典返しを準備することもあります。親族同士で分担する場合には、
「香典返しの手配、私がまとめてやるね」
「この方には直接お届けした方がいいかもね」などのやりとりも。
連絡や確認のやりとりの中にも、自然と感謝や気づかいの言葉が必要になってくると感じました。
お手伝いしてくれた親戚へのお礼の連絡
式が終わったあとに、LINEや電話で一言お礼を伝えるだけでも、ぐっと関係が深まります。
「本当に助かったよ」「落ち着いたらまたゆっくりお話ししたいね」など、葬儀という時間だけで終わらない関係性が築けることもあります。
葬儀はあっという間に過ぎてしまいますが、その中にはたくさんの「挨拶の機会」が詰まっていました。
どれも形式ばった言葉ではなく、そのときどきの相手と向き合った“等身大のことば”が、なにより心に残ったように思います。
小さな子どもがいる場合の「気づかい」と挨拶のコツ
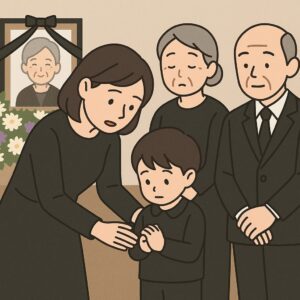
うちは当時、息子が2歳。
まだまだ落ち着きがない年頃で、言葉は少し通じるけれど、突然大きな声を出したり、うろうろ歩き回ったり…。正直、葬儀という厳かな場に連れて行っても大丈夫なのかすごく悩みました。
でも親族として参列する立場だったので、どうしても連れて行かざるを得ませんでした。
夫婦で何度も話し合って、当日はなるべく私が子どものそばにいられるように調整したり、途中で外に出られるよう準備して臨みました。
挨拶に子どもの存在を一言添える
葬儀当日、やはり少し落ち着かない場面がありました。親族控室で動き回ったり、お焼香の列で「抱っこ〜」と騒いだり…。
周囲に迷惑をかけてしまったかなと思ったときには、
-
「子どもが少し騒いでしまってすみません」
-
「今日はおとなしくしてくれていて助かりました」
-
「何かとご迷惑をおかけしました」
といったように、一言そえるようにしていました。
ただ、「謝るだけ」だと気まずくなりがちなので、感謝や気持ちもセットで伝えるようにしていました。
「見守ってくださってありがとうございます」など、少し気持ちを込めるだけで、周囲の反応もやわらかくなるんですよね。
なかには「子どもは元気がいちばんよ」「うちの孫もそうだったよ」と、笑ってくださる方もいて、救われた気持ちになりました。
子どもにも伝える「なぜ静かにするのか」
小さい子どもに、「今日は静かにしようね」と言っても、理由が分からなければなかなか通じませんよね。
なので、うちでは事前に少しだけ“説明”をしました。
「今日は、ひいばあちゃんとお別れする日だよ」
「いっぱいありがとうを言う日なんだよ」
「静かにしてると、ひいばあちゃんも喜ぶと思うよ」
まだ2歳だったので、どこまで分かっていたかは分かりません。
でも、なんとなく雰囲気を感じて、ぐずることなく参列できました。
「子どもだから分からない」ではなく、“その子なりに理解できる言葉で伝える”ことが大切だと、今回改めて思いました。
式の最中、息子が手を合わせていた姿を見て、親族の方が「ちゃんとしててえらいね」と声をかけてくださったのも印象的でした。
家族全体の姿勢が、自然と周囲への礼儀になる
夫も私も、「子どもが迷惑をかけたらどうしよう」とすごく気をつかっていました。
でも、夫婦で役割を分担しながら対応したり、なるべく静かな時間を過ごせるよう工夫していた姿を見て、周囲の方々も「頑張ってるね」と理解してくれたように思います。
もちろん、完璧にはいかなくて当然です。
でも、“丁寧に向き合っている姿勢”があるだけで、それは自然とまわりの方への礼儀になるのだと感じました。
葬儀は大人だけの場ではありません。
子どもがいる家庭なりの形で、故人とのお別れに向き合うことも、立派な弔いのかたちだと思います。
「言葉に迷ったとき」の考え方
葬儀の場では、ふいに言葉を求められる瞬間があります。
とくに親族の立場になると、親しさの度合いも人それぞれで、「この人には何を言えば…?」と迷うことも多くなります。
そんなとき、私が自分に言い聞かせていたのが、「完璧な言葉じゃなくていい。心を伝えよう」ということでした。
以下は、実際に私が意識していた3つのポイントです。言葉に詰まったときの“よりどころ”になるかもしれません。
1. 感謝を先に伝える
たとえば、弔問に来てくださった方に対しては、「お越しくださってありがとうございます」や「遠くからありがとうございました」と、まず感謝の言葉を口にするようにしました。
どんな立場の方にも、どんな関係性でも、「ありがとう」はまっすぐ届く言葉。
それだけで場の空気が少しやわらぎ、相手の緊張も解けるような気がしました。
特に祖母と親しかった方には、「来ていただけて祖母も喜んでいると思います」と続けると、相手も自然と「いいお顔だったね」などと思い出話をしてくださることが多かったです。
感謝の言葉は、心を通わせる最初の鍵なのだと思います。
2. 自分の言葉でOK
葬儀の場では、「正しい言い方をしなきゃ」とつい身構えてしまいますよね。
私も最初は、型通りの言い回しを探してしまっていました。
でも、いざその場になると、どうしても感情が先に込み上げてくるんです。
「私もまだ信じられなくて…」
「昨日まで普通に話してたのに、変な感じだよね」
そんなふうに、ぽろっと出てしまった言葉のほうが、相手も素直に受け取ってくれた気がします。
もちろんマナーは大事ですが、“飾らない自分の言葉”が、かえって相手の心に響くこともあると気づかされました。
あのとき、「無理にかしこまらなくていいんだ」と思えたことで、気持ちもラクになりました。
3. 無理に話そうとしない
一番印象に残っているのは、火葬場での待ち時間。
ふと隣に座った伯母と、何分間も無言で過ごしていました。
最初は「何か話したほうがいいのかな」と思っていたのですが、目が合ったとき、ふたりで小さくうなずきあっただけで、それだけで十分通じ合えた気がしたんです。
言葉って、ときには“なくても伝わる”ものなんですね。
沈黙もまた、弔意のかたち。
大切なのは、“何を言うか”よりも、“どんな気持ちでそこにいるか”なのかもしれません。
私自身、何度も言葉に迷いながらも、気持ちを伝えようと試行錯誤したことで、「ああ、自分なりにちゃんと故人を見送れたな」と思えるようになりました。
完璧じゃなくても、失敗しても、
それでも「心を込めたひとこと」は、ちゃんと届くと信じています。
まとめ|大切なのは「気持ちを伝えること」
葬儀での親族としての挨拶は、形式や言葉遣いももちろん大事だけれど、いちばん大切なのは「故人への想い」や「来てくれた人への感謝」がきちんと伝わること。
うまく話せなくても、涙で声が詰まってしまっても、その瞬間の「真剣さ」や「心」が伝われば、それで十分なんだと思います。
この記事で紹介した例文やタイミングが、少しでもあなたの安心につながればうれしいです。
そして、もしものときにあわてないように、家族の中でも少し話し合っておけたらいいですね。