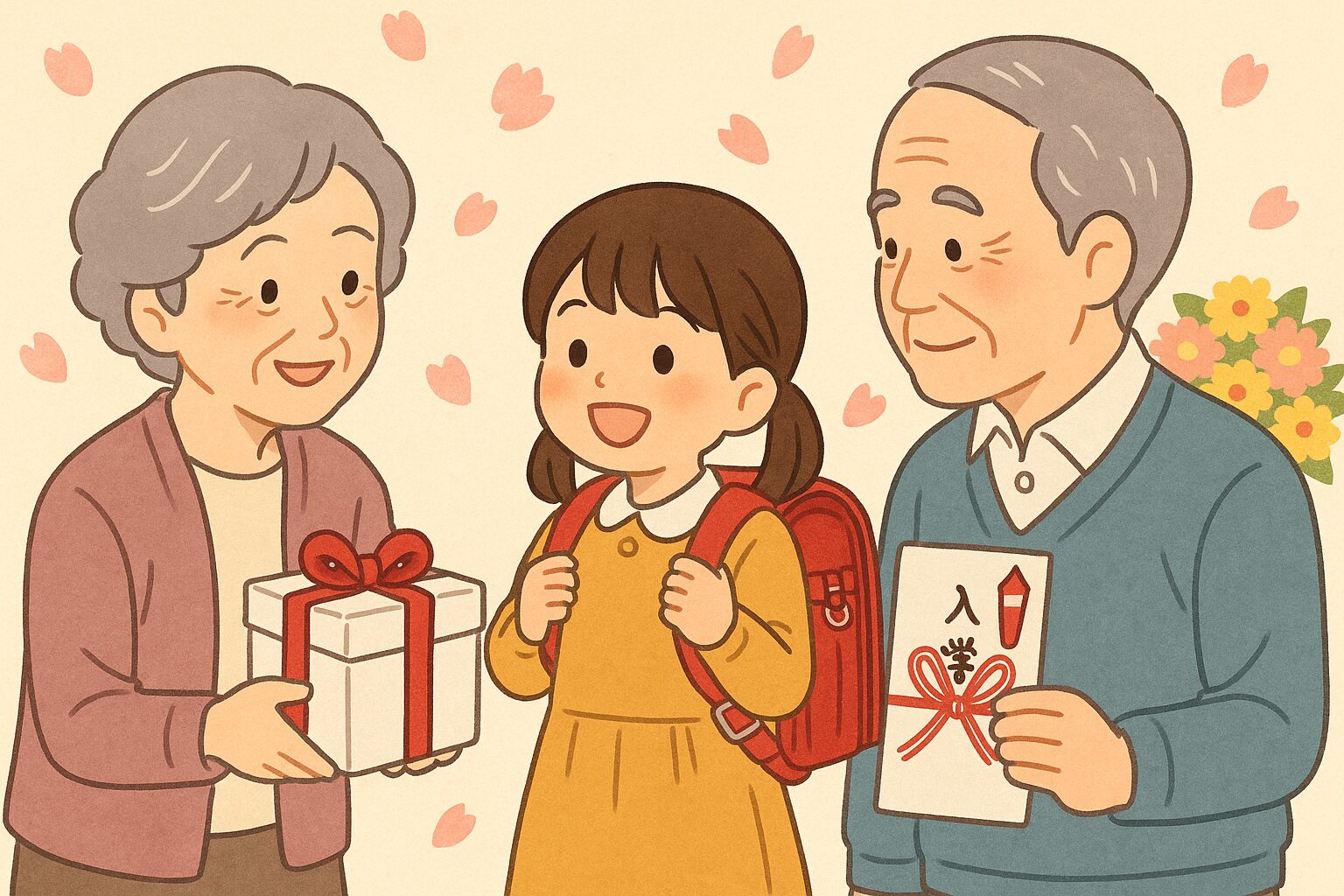「小学校の入学祝い、いくら包めばいいの?」「おもちゃより実用品の方がいいのかな?」
初めての入学祝いを贈るとき、そんな迷いを感じる祖父母は多いのではないでしょうか。私も娘の入学を控えたとき、両親や義両親が「何をあげたら喜ぶかな?」と相談してくれました。金額の相場や贈り方のマナーを知っておくと、贈る側も受け取る側も気持ちよく迎えられます。
この記事では、祖父母から贈る入学祝いの金額相場・おすすめの贈り物・マナー・渡し方までを、体験談を交えながらわかりやすく解説します。
入学祝いの基本マナーと贈るタイミング
入学祝いは「お祝い+応援」の気持ち
小学校入学は、子どもにとって初めての「社会生活」への第一歩。保育園や幼稚園とは違い、「自分で行動すること」「集団の中で過ごすこと」がぐんと増える節目です。
だからこそ、祖父母からの入学祝いには「おめでとう」という祝福だけでなく、「これからも応援しているよ」という想いを込めることが大切です。
私の娘が入学したときも、両家の祖父母が口をそろえて「もうランドセル背負うのね、立派になったわね」と目を細めていました。孫の成長を心から喜び、これからの未来を見守る気持ちを形にするのが入学祝いなんですよね。
お金や品物はあくまで「気持ちを添えるもの」。高額である必要はなく、子どもの成長を一緒に喜ぶ「お祝いの心」が一番のプレゼントです。形式にとらわれすぎず、“おめでとう”という言葉に愛情を乗せて伝えることを意識しましょう。
また、親世代からすると、祖父母からの応援の言葉やプレゼントはとても心強いものです。子どもだけでなく、親への「がんばってね」というメッセージにもなり、家族みんなの励みになります。
贈る時期の目安
入学祝いを贈るベストなタイミングは、入学式の2〜3週間前(3月中旬ごろまで)が理想とされています。早めに贈ることで、ランドセルや文房具などの準備資金として活用でき、親御さんの負担も軽くなります。
私の両親は、ちょうど3月上旬にお祝いを持ってきてくれました。娘と一緒に「どんな筆箱がいいかな」「上履きはこれがかわいいね」と買い物を楽しみながら選ぶ時間は、まさに春の思い出になりました。お祝いを“準備の時間”に変えることで、贈る側も受け取る側も笑顔になれます。
もし遅くなってしまった場合でも、入学式の直前や当日に手渡しても問題はありません。ただし、4月以降になると「入学祝い」ではなく「お小遣い」として受け取られることもあるため、タイミングには少し気をつけたいですね。
どうしても都合が合わない場合は、「新生活が始まって落ち着いた頃に」と伝え、入学後1週間以内を目安にすると丁寧です。
渡し方とメッセージの添え方
入学祝いを贈るときは、できるだけ直接手渡しするのが理想です。
お金を包む場合は、「紅白蝶結び」ののし袋を使います。蝶結びは「何度繰り返してもよい祝い事」に使われるため、入学・進学などの節目にぴったり。
表書きは「祝御入学」または「入学御祝」、下段には祖父母の名前をフルネームで記入します。
もし孫に直接渡すなら、「おめでとう!これから楽しい学校生活が待ってるね」と笑顔で一言添えると、緊張していた子どもの心もやわらぎます。
さらに、メッセージカードや手紙を添えると、より心が伝わります。たとえば、こんな一文はいかがでしょうか。
「小学生おめでとう。勉強も遊びも元気いっぱい楽しんでね。じいじとばあばは、いつでも応援しているよ。」
こうした言葉は、後から読み返しても温かい気持ちになれる宝物。娘も祖母からの手紙を大事にしていて、「がんばる力の源になる」と感じました。
また、遠方に住んでいて直接会えない場合は、現金書留で送ってもOKです。その際も、手紙やメッセージを添えることで、「ただお金を送るだけ」ではない温かさが伝わります。
顔を合わせて「おめでとう」と言葉を交わす瞬間こそが、子どもにとっての最高の入学祝いです。
入学祝いの金額相場|祖父母からはいくらが妥当?
祖父母からの相場は「10,000〜30,000円」
祖父母からの入学祝いは、おおむね1万〜3万円が無理のない目安。地域差や家計の状況、孫との距離感(同居・近居・遠方)で幅はあります。迷ったら“中央の2万円前後”を基準に、上げ下げして調整すると決めやすいです。
結婚祝いほど金額の縁起(偶数・奇数)を厳密に気にする必要はありません。気になる場合は3万円や1万5千円など奇数でまとめてもOK。新札を用意し、のし袋は紅白蝶結び、表書きは「祝御入学/入学御祝」に。封入方向は人物の顔が上にくる向きでそろえると見た目も丁寧です。
私の感覚では、初孫やとても身近に関わる予定がある場合は30,000円寄り、二人目・三人目で生活実感があるなら10,000〜20,000円寄り、と“関わりの濃さ”で微調整するのが自然でした。
ケース別の目安
「現金だけ」「品物+現金」「両家で分担」の3パターンで考えると、モヤモヤが減ります。
-
現金のみで贈る:10,000〜30,000円
例)遠方で指定品が分からない、親に自由に選んでほしいとき。使い道の自由度を重視。 -
ランドセル・机など高額品を贈る:品物+5,000〜10,000円
例)「ランドセルは祖父母が、細かい備品は親が」など分担。のし袋は“気持ちの上乗せ”として少額で十分。 -
両家がそれぞれ贈る:事前に連絡して重複回避
例)私の家では、私の両親=ランドセル、義両親=学習机。合計負担が過度に大きくならない上限を3万〜5万円程度に置くと、双方が気持ちよく決められました。 -
兄弟同時入学(双子など):1人あたりの基準を守る
例)「各2万円×2人」で計算し、合計4万円。まとめて包む場合も内訳は口頭で伝えると誤解がありません。 -
二人目以降:上の子と同額が基本
例)上の子2万円なら下の子も2万円。もし差をつけるなら、後でフォロー(誕生日や進級時)で埋める前提を家族で共有。
兄弟姉妹・孫が複数いるときの“公平感”の作り方
金額そのものよりも、「同じ基準で扱っている」という納得感が大切です。
私は簡単なメモ帳に「誰に、いつ、いくら、品物/現金」を記録しておきました。二人目以降のときに見返せるので迷いが減ります。もし上の子にランドセル(高額品)を贈っていたなら、下の子には「学習机+現金少額」など“総額感”でそろえるのも一案。
また、親の立場としては“過度な高額”はお返しや今後の基準に響きます。事前に「上の子のときと同じくらいで大丈夫?」とひと言確認してもらえると、本当に助かります。
金額を決める“5ステップ”
-
基準額を決める(1万・2万・3万のどれか)
家計負担と関わりの濃さで即決。ここがブレないと迷いにくい。 -
親に“必要な物リスト”を聞く
指定用品(色・サイズ・名入れ可否)は学校によって異なります。重複回避にも。 -
両家と軽く連絡を取り、役割分担
「私のほうでランドセルを」「ではこちらは机を+気持ちの現金で」。 -
現金か品物か、配分を決める
例)基準2万円 → 文具1万円分を一緒に買い、残り1万円をのし袋で。 -
のし袋・新札・メッセージを用意
最後に渡すタイミング(3月中旬目安)を合わせて完了。
会話で決まると早い|わが家のミニシミュレーション
-
じいじ「予算は2万円くらいでどう?」
-
ばあば「じゃあ、筆箱や上履きは一緒に買って残りは包もうか」
-
私「助かります。義母側で机を予定してくれてるので、重ならずに済みます」
この流れで、“総額の輪郭→必要な物→配分→渡す時期”が10分で決まりました。スムーズでした。
これだけで迷いが減り、祖父母も親も気持ちよく入学の日を迎えられます。
入学祝いのおすすめプレゼント|実用性と記念性で選ぶ
実用的なアイテムを選ぶと喜ばれる
小学校生活が始まると準備物が一気に増えます。実用品は親の負担を軽くし、子どももすぐに活用できます。まずは学校指定(色・サイズ・名入れ可否・キャラクター可否)を必ず確認。そのうえで、“毎日使う×消耗が早い”に投資すると失敗が少ないと感じています。
-
ランドセル
A4フラットファイル対応、重量は1,100〜1,300gが目安。背当ての通気性や肩ベルトのフィット感、6年間保証の有無をチェック。色は子どもの希望を尊重しつつ、通学服や防犯面で目立ちすぎないかも確認。 -
学習机・椅子
昇降機能で姿勢が崩れにくいものが長く使えます。照明は手元が陰にならない位置に。リビング学習なら“幅90〜100cmの省スペース+キャスター引き出し”が使いやすい印象でした。 -
文房具セット
鉛筆は2B〜HBを1ダース、消しゴムは消字性重視。筆箱はマグネット式で開閉が静かなもの。ネームスタンプや名前シールも一緒に贈ると準備が一気に進みます。 -
通学用の靴・傘・レインコート
靴は面ファスナーで着脱しやすいものを“2足ローテ”に。傘は50cm前後で透明窓つき、安全カバーがあると安心。レインコートはランドセル上から着られる作りと反射材の有無をチェック。 -
名前入りの鉛筆・下敷きなど
名入れは紛失防止だけでなく“自分のもの”という愛着につながります。替えを見越して無地デザイン+名入れにすると長く使えます。 -
あると重宝するセット提案
「上履き2足+体育館シューズ袋+名入れスタンプ」「給食ナフキン3枚+カトラリー+洗い替え巾着」など、“洗い替えまで含めたセット”は実践的でした。
買いすぎ注意ポイント
最初から高額な多機能文具や大型の辞書・百科事典は出番が限られることも。学校の配布物や担任の案内後に追加するほうが結果的に無駄がありません。キャラクター物は学年・学校方針でNGのケースがあるため事前確認が安心です。
記念に残る贈り物も人気
節目を彩る“形に残る品”は、あとで家族の会話を生む力があります。実用品とバランスを取りながら1点だけ“記念枠”を入れるのが私のおすすめ。“思い出が会話になる仕掛けを入れる”ことを意識すると、何年たっても価値が続きます。
-
フォトフレーム付き時計
名入れ・日付・メッセージを刻印。入学式の写真を入れて玄関やリビングに置くと“春が来た日”をいつでも思い出せます。 -
記念撮影用フォトブック
入学式だけでなく、通学路や初めての宿題、はじめての連絡帳など“1年生の最初の30日”をテーマに撮って編集。祖父母と一緒にページをめくる時間もごちそうです。 -
名前入りアクセサリー(キーホルダー・印鑑など)
ランドセル用のタグは防犯面からフルネームの露出を避け、表はイニシャル、裏にフルネームや連絡先など“見せ方”を工夫。印鑑は実印用途ではなく、連絡帳用の“連絡済み”スタンプなど日常で楽しく使えるものが安心です。 -
成長記録アルバム/タイムカプセル
身長・足サイズ・好きなものリストを家族で書いておき、卒業時に開く約束に。祖父母の直筆メッセージや当日の写真、学校までの切符や記念の桜の押し花を一緒に保存すると物語性が増します。 -
体験を添えるハイブリッド
記念品+体験のセットも素敵です。フォトフレームと一緒に写真館チケット、フォトブックと一緒に「花見ピクニック」の計画メモなど、“贈った日そのもの”が思い出に。
保管の工夫として、写真や手紙はクリアポケットのアルバムに入れて日付ラベルを貼っておくと、後から探しやすいです。わが家も義母からもらった名入れフレームを飾っていますが、写真を差し替えるたびに「このとき小さかったね」と自然に会話が生まれ、節目の温度をずっと感じられています。
お金を贈るときの工夫|現金だけで味気ないときは?
ギフトカードや商品券との組み合わせ
「現金だけだと少し寂しいかな…」「お祝いの気持ちをもう少し形にしたい」と感じる祖父母も多いものです。そんなときにおすすめなのが、ギフトカードや図書カードとの組み合わせ。
たとえば、
-
現金1万円+図書カード3,000円分
-
現金2万円+文具店・百貨店のギフト券2,000円分
といった“使い道の自由+楽しみ”の両立パターンは、親御さんにも子どもにも喜ばれやすいです。
私も娘の入学祝いに、両親が現金と一緒に図書カードを添えてくれました。渡すときに「好きな本を自分で選んでみようね」と声をかけてくれたことで、娘は自分で本を選ぶワクワク感を体験。「じぶんで決められる!」という自信にもつながりました。
“選ぶ楽しさ”が加わることで、現金だけよりも記憶に残る贈り物になると感じます。
さらに、文具券・百貨店ギフト券・電子マネーギフトなど、親が学校用品をそろえるのに役立つ券種を選べば、実用面でもサポートできます。特に遠方の祖父母が送る場合は、「何を買えばいいか分からない」「好みが分からない」といった不安を解消できるので、気軽に気持ちを届けやすいのもメリットです。
ラッピングや手紙で心を添える
金額の多寡にかかわらず、心を伝える“ひと工夫”があると特別感が生まれます。
シンプルな封筒でも、かわいい和柄や季節のモチーフがあしらわれたお祝い袋を選ぶだけで、ぐっと華やかな印象に。特に入学シーズンの3月〜4月は桜デザインののし袋が人気です。
また、短い言葉でも手書きのメッセージを添えると気持ちがより温かく伝わります。
たとえば、
「入学おめでとう!たくさんお友だちを作ってね」
「学校での毎日が楽しく、充実した時間になりますように」
「新しいことにどんどん挑戦してね。じいじとばあばは応援してるよ」
このような一言があるだけで、子どもは「応援されている」という安心感を持てますし、親御さんも「ちゃんと心を込めて贈ってくれたんだな」と感じられます。
また、孫に直接渡すときには、封筒のデザインを孫の好きな色や動物モチーフにするのもおすすめ。
「かわいいね!これ、ぼくの?」と笑顔で受け取る姿は、贈る側にとっても嬉しい瞬間です。
プレゼントと併せて渡すときの注意点
現金に加えてプレゼントを贈る場合は、“トータルバランス”を意識することが大切です。
あまりに高額になりすぎると、親御さんが「お返しをどうしよう…」と気を遣ってしまうことも。
たとえば、
-
現金2万円+実用品(文房具セットや通学グッズ)
-
現金1万円+記念品(フォトフレームや名入れアイテム)
のように、「お祝い+思い出」のバランスをとると、受け取る側も負担に感じにくくなります。
私の義母も「机を買うから、少しだけ現金も渡すね」と、5,000円を添えてくれました。
「必要なものの足しにしてね」と一言添えてもらえたおかげで、気を遣うこともなく、ありがたく受け取れました。こうした“ひと言の配慮”が、金額以上に心に残ります。
もしプレゼントの価格が高めになる場合は、「○○を贈ったから現金は少しにしておこう」「今回は気持ちだけで十分」と調整して問題ありません。どんな贈り方でも、“気持ちをまっすぐに伝えること”こそが一番のマナーです。
お金+ひと工夫で「心が伝わる贈り物」に
入学祝いは、単なる金銭のやり取りではなく、「おめでとう」と「応援しているよ」を形にする行為です。
現金にひと工夫を添えるだけで、贈り物はぐっと温かみのあるものになります。
孫と一緒に選ぶ「体験型」ギフトという選択
思い出を共有できるギフトもおすすめ
最近では「モノを贈る」だけでなく、“一緒に過ごす時間そのものを贈る”という「体験型ギフト」を選ぶ祖父母が増えています。
子どもにとっても、祖父母と一緒に選ぶ・体験するというプロセスが特別な記憶として残りますし、祖父母にとっても「孫の成長を間近で感じられる喜び」が得られる素敵な時間になります。
たとえば、こんな体験を一緒にするのはいかがでしょうか。
-
ランドセル購入を一緒にする
お店に出向き、背負い比べながら「どれがいいかな?」と会話する時間は、ワクワクと感動が詰まった瞬間。
孫に「これ、じいじとばあばと選んだんだよ」と語り継がれる、思い出深いギフトになります。
実際に私の父も「せっかくだから一緒に買いに行こう」と声をかけてくれました。カタログで眺めるだけでは分からない“背負い心地”や“好み”を話し合いながら選んだ1日は、今でも家族の宝物です。 -
写真館での記念撮影
「入学記念」として、祖父母も一緒に写真館で撮影するのも人気。
普段なかなか全員が揃う機会がないからこそ、節目にみんなで撮る1枚は一生の記念になります。
スタジオによっては「祖父母参加OK」の家族プランもありますし、スーツや和装を揃える楽しみも。撮影後にはフォトブックやパネルにして贈るのも喜ばれます。 -
入学式当日の服を一緒に選ぶ
新しい門出にふさわしいスーツやワンピースを、祖父母と一緒に見立てるのも心温まる体験です。
「これ似合うね」「この色素敵」と会話しながら選ぶ時間は、ただの買い物以上の意味を持ちます。
孫が服を着るたびに、「これはじいじとばあばと選んだんだよ」と誇らしげに話してくれる姿に、祖父母の目尻も下がるはずです。
ランドセルを選ぶ時間、写真を撮る時間、服を探す時間——それぞれの瞬間に会話が生まれ、笑顔が生まれ、“贈る”という行為が“思い出づくり”に変わるのです。
体験を贈るときの工夫
体験型ギフトは、終わったあとに「形」として残す工夫をすることで、さらに価値が高まります。
-
写真を撮ってアルバムやフォトブックにまとめる
体験の思い出は、写真に残すとより一層記憶に刻まれます。
たとえば、ランドセル売り場で試着している姿、店員さんと話している様子、祖父母と笑い合う瞬間などをスマホで撮影し、後日フォトブックにまとめてプレゼントするのもおすすめ。
「このとき、じいじが赤が似合うって言ってくれたね」など、写真を見返すたびにその日の会話や空気が蘇ります。 -
メッセージを添える
体験の後に「今日は一緒に選べてうれしかったね」「楽しい時間をありがとう」というメッセージカードを添えると、より温かい印象に。
子どもが文字を覚え始めている時期なら、「ありがとう」の一言を孫から祖父母へ渡すのも素敵な演出です。双方向の“贈り合い”が生まれます。 -
当日のエピソードを記録する
写真だけでなく、簡単なメモを残しておくのもおすすめです。
「この日、初めて自分でランドセルを選びました」「“小学生になるんだ”と話していた表情が頼もしかったです」など、一言でも書いておくと、数年後に見返したときに感動が蘇ります。
さらに、近年は「体験ギフトチケット」を利用する祖父母も増えています。
フォトスタジオ撮影やテーマパークチケット、カタログ型の“体験ギフト”をプレゼントすれば、スケジュールを合わせて一緒に出かける楽しみが生まれます。
「今度このチケットで一緒に行こうね」と約束する時間そのものが、すでにプレゼントの一部です。
体験を通して交わした会話や笑顔は、子どもの心の奥に長く刻まれます。
祖父母と孫が一緒に歩いたその時間こそが、何よりの「入学祝い」になるのです。
入学祝いを渡すときのマナーと注意点
直接手渡しが基本
入学祝いは、できるだけ対面で手渡しを。両手でのし袋を差し出し、「入学おめでとう。楽しい学校生活を過ごしてね」と一言添えるだけで温度が伝わります。渡す場所は自宅、祖父母宅、外食の席など落ち着いて話せる場所が安心。タイミングは入学式の2〜3週間前が目安ですが、会える日を最優先にして大丈夫です。
のし袋は紅白蝶結びを選ぶのが基本。お札は新札を人物の顔が上にくる向きで封入すると丁寧です。孫に直接渡す場合は、受け取りやすい高さでゆっくり手渡し、「ありがとう」と言えたらたくさん褒めてあげてください。写真を一枚撮っておくと、あとでお礼状に添えられます。
郵送・振込のマナー
遠方で会えないときは現金書留を使います。中にのし袋と短い手紙を同封し、到着日が入学の少し前になるよう投函を調整。商品券やギフトカードのみなら簡易書留を使うと安心です。振込でお願いされた場合は、メッセージカードを別送し、到着日と金額が分かるメモを添えると親御さんの管理がスムーズ。
電話やビデオ通話で受け取り確認を兼ねたお祝いの言葉を伝えると、郵送でも“心の距離”をぐっと縮められます。
お返しは不要だが「お礼」は忘れずに
入学祝いは原則として内祝い不要。ただし受け取った側は、当日〜数日以内に電話やメッセージでお礼を伝えるのがマナーです。わが家は当日、娘と一緒に「じいじ、ありがとう」と電話で伝え、その週末に入学式の写真を同封したカードを送りました。
高額になった場合や、特別に時間を作ってもらった場合は、焼き菓子やお茶など“気持ちのプチギフト”を添えたお礼状も喜ばれます。形式的な品より、写真や手書きの一言のほうが心に残ります。
両家で差が出ないように配慮
双方の祖父母がいる場合は、事前のひと言連絡がいちばんの予防策です。「わたしの両親はだいたい2万円で考えているよ」「義母は机を用意してくれるみたい」など、予算感と担当を共有。
もし差がついてしまったら、金額で埋めようとせず、写真共有や一緒に買い物へ行く“時間の贈り物”でバランスをとると角が立ちません。親の立場からは、どちらの贈り物にも同じ熱量でお礼と写真を返すことが公平感につながります。
のし袋・表書き・連名の書き方
表書きは「入学御祝」または「祝御入学」。下段は贈り主の氏名をフルネームで。祖父母連名なら中央に世帯主、その左に配偶者名をやや小さく、苗字を省いて名だけでも可。孫宛の現金に兄弟がいる場合は、のし袋の外には書かず、内袋メモに「〇〇へ」と対象名を書いておくと誤解を防げます。
封入額が多いときは中袋に金額を旧字体で記すと改まった印象に。迷ったら“読みやすさ優先”で楷書を丁寧にが安心です。
NGになりやすい例とトラブル回避
学校指定前の大型購入は避ける、過度に高額で親に負担を感じさせない、フルネームの外付け名札など防犯上の配慮を忘れない。キャラクター物は学校方針や学年で不可の場合があるため、事前確認が安全です。
迷ったときは、予算感と希望を親に軽くヒアリングし、「必要なものの足しにしてね」と伝えるのが一番。相手に“選ぶ自由”を残す配慮が、気持ちの良いお祝いにつながります。
祖父母としての気持ちを伝える一言メッセージ例
入学祝いに「おめでとう」の言葉を添えると、贈り物が“心のこもったメッセージ”に変わります。
短い一文でも、祖父母の温かさや優しさはしっかり伝わるものです。ここでは、実際に使えるフレーズとともに、メッセージに込めたい想いのポイントを紹介します。
シーン別・気持ちが伝わる一言フレーズ集
1. 新しい環境を応援する言葉
「入学おめでとう!新しいお友だちと楽しく過ごしてね」
「ピカピカの1年生、がんばってね!毎日が楽しい発見になりますように」
このメッセージには、「楽しく過ごしてほしい」「安心して学校生活を送ってほしい」という思いが込められています。新しい環境に少し緊張している子どもに、やさしい励ましを伝えられます。
特にシャイな性格の子には、「焦らなくてもいいよ」「少しずつ仲良くなれたら大丈夫」という補足の一言を添えると安心感が広がります。
2. 学びを応援する言葉
「勉強も遊びも元気いっぱいにがんばってね」
「たくさんのことを学んで、ステキな毎日を過ごしてね」
勉強に限らず、学校生活全体を応援する言葉です。
「がんばってね」には“無理をしてでも”という意味を込めないように注意しましょう。
祖父母として伝えたいのは、“努力を応援する気持ち”と“あなたを信じているよ”という信頼。
「いっぱい楽しんでね」「ゆっくりで大丈夫」など、子どものペースを尊重する言葉を加えると、プレッシャーを与えずに温かく背中を押せます。
3. 成長を願う言葉
「小学生になっても笑顔を忘れず、楽しい毎日を過ごしてね」
「これからの成長を楽しみにしているよ」
「優しい気持ちを大切に、たくさんの出会いを楽しんでね」
“成長を楽しみにしている”という言葉は、孫への愛情そのもの。
子どもに「自分のことを見てくれている」「応援してくれている」と感じてもらえるメッセージです。
入学は“できることが増える時期”でもあり、“挑戦が始まる時期”でもあります。
祖父母からの言葉が「どんな自分でも大丈夫」「見守ってくれている」という安心感を届けてくれます。
4. 家族の絆を伝える言葉
「じいじとばあばは、ずっと応援しているよ」
「うちに遊びに来たとき、学校のお話を聞かせてね」
「あなたの笑顔が、みんなの元気のもとだよ」
家族全体で子どもの成長を喜んでいる気持ちを伝えると、孫にとって“帰る場所”の安心感を与えます。
特に共働き家庭や離れて暮らす家庭では、「いつでも応援している」というメッセージが心の支えになります。
メッセージをより印象的にするひと工夫
-
手書きで伝える
たとえ短くても、直筆のメッセージには温かみがあり、思いがよりストレートに届きます。
字に自信がなくても構いません。「あなたのために書いた」という気持ちが何より嬉しい贈り物です。 -
孫の名前を入れる
「○○ちゃん、入学おめでとう!」のように、名前を呼ぶことで一気に親しみが増します。
特に子どもは“自分の名前”に反応しやすく、読んだ瞬間に顔がほころびます。 -
思い出に残る保管方法
メッセージカードや手紙は、後から見返せるようにアルバムやフォトフレームに残すのもおすすめ。
我が家では、祖父母から届いた手紙を写真と一緒に保管しています。
読み返すたびに、そのときの空気や温かさがよみがえるんです。子どもが成長して中学生、高校生になったときに読み返すと、「このときこんな言葉をもらったんだ」と感慨深い気持ちになるものです。
入学という新しいスタートラインに立つ孫へ、あたたかな言葉を贈ることで、家族の絆がさらに深まるはずです。
まとめ|「おめでとう」の気持ちをまっすぐに伝えよう
祖父母からの入学祝いは、金額や品物以上に「お祝いの気持ち」を伝えることが大切です。
相場を目安にしながらも、孫や家族の状況に合わせた贈り方を意識しましょう。
「おめでとう」「応援してるよ」の言葉を添えれば、それが何よりのプレゼントになります。
今日紹介したアイデアを参考に、“心のこもった入学祝い”で新しい一歩を応援してあげてください。