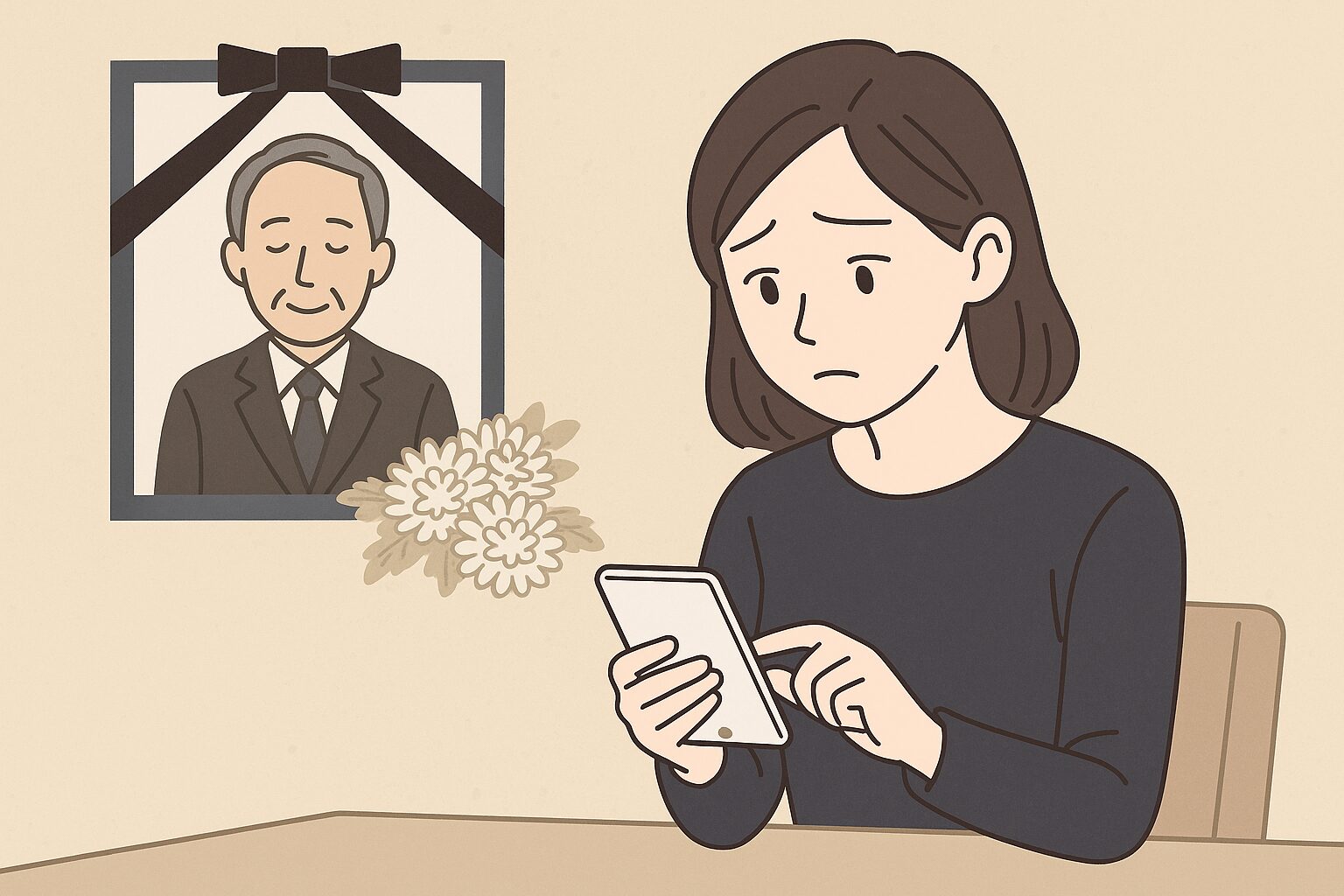突然の訃報に接したとき、「何か一言伝えたいけれど、どんな言葉を選べばいいの?」と戸惑ったことはありませんか?
私も、子どもを寝かしつけた夜に訃報の連絡を受け、「今すぐお悔やみを伝えたいけれど、失礼があってはいけない」と迷った経験があります。
この記事では、お悔やみメールの基本マナーや、ビジネス・親族それぞれの例文を紹介します。気持ちを込めつつ、相手に負担をかけない表現を知ることで、急なときでも落ち着いて対応できます。
大切なのは「完璧な言葉」ではなく、「相手を思う気持ち」。その気持ちがきちんと伝わるメールの書き方を、一緒に見ていきましょう。
お悔やみメールを送るときの基本マナー
お悔やみの言葉を「メール」で伝える機会は、ここ数年で確実に増えています。
LINEやSNSが日常的な連絡手段になった今でも、改まった気持ちを伝えたいときはメールが最も安心で丁寧な方法です。特にビジネスシーンや目上の方、親族への連絡では、形式を整えたメールが印象を左右します。
ここでは、「いつ・どのように送るか」「どんな件名・文体がよいか」を、私自身の体験を交えながら詳しく解説します。
送るタイミング
訃報を受けたら、まずは「できるだけ早く」気持ちを伝えるのが基本です。
相手が深い悲しみの中にいるからこそ、すぐに寄り添う姿勢を示すことが何よりの心遣いになります。
私も以前、職場の先輩のご家族が亡くなった際、「どのタイミングで連絡すべきだろう…」と迷いました。悩んだ末、その日の夜に短いお悔やみメールを作成し、翌朝7時に送信予約をしました。深夜の連絡は避けたいけれど、「翌日まで待つのも失礼かもしれない」と感じたためです。
-
夜間(21時以降)は避ける
-
朝8時~9時台に送るのが理想
-
可能であれば24時間以内に送る
「お悔やみはスピードが誠意」とも言われます。
忙しいからといって後回しにせず、まずは短くても構いません。「訃報を受け取り、心よりお悔やみ申し上げます」と伝えるだけでも、十分に気持ちは伝わります。
メールの件名
お悔やみメールは、本文に入る前の「件名」から丁寧さが問われます。
件名がカジュアルだったり曖昧だったりすると、開封前に違和感を与えてしまうこともあります。形式に沿った落ち着いた表現を使うことで、「真摯な気持ちで書かれている」ことが伝わります。
代表的な件名の例は以下の通りです。
-
ご逝去のお知らせを受けて
-
お悔やみ申し上げます
-
このたびのご訃報に際し
どれを選んでも問題ありませんが、迷ったときは「お悔やみ申し上げます」が最も汎用的です。
また、ビジネス関係の場合は、相手の立場に配慮して会社名を併記するのも良い方法です。
例:「株式会社〇〇〇〇様 お悔やみ申し上げます」
件名は短く、丁寧に。本文を読む前から誠実さが伝わるよう心がけましょう。
文体と語尾
お悔やみメールは、「敬語+落ち着いた文体」で統一するのが基本です。
たとえ普段フランクなやり取りをしている相手でも、この場面では“フォーマルな敬意”を優先するのがマナーです。
たとえば、普段なら「大丈夫だった?」「元気出してね」といった言葉を使うかもしれませんが、
お悔やみでは「ご心痛いかばかりかと存じます」「どうかお体を大切にお過ごしください」といった丁寧な表現に置き換えましょう。
また、語尾はすべて「です・ます調」で統一します。
文章全体にやわらかさが生まれ、相手に寄り添う印象を与えます。
代表的な表現と注意点
-
「ご冥福をお祈り申し上げます」:仏教以外でも広く使える
-
「安らかにお眠りください」:やさしく聞こえるが、宗教によっては避ける
-
「ご愁傷様です」:目上の人に使うのは避ける(同等・目下に限定)
もし宗派がわからない場合は、「心よりお悔やみ申し上げます」が最も無難です。どんな宗教にも対応でき、相手への思いやりが伝わります。
文章構成の基本
実際に本文を書くときは、以下の3ステップを意識すると迷いません。
-
【冒頭】訃報を知った驚きとお悔やみの言葉
例:「このたびはご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。」 -
【中盤】相手の気持ちへの配慮・思い出の一言
例:「ご家族の皆様のご心痛いかばかりかと拝察いたします。」 -
【結び】体調を気遣う言葉
例:「どうぞご無理なさらず、お体を大切にお過ごしください。」
この構成を守れば、形式・心遣い・文面の整合性が取れ、どんな関係性の相手にも対応できます。
ちょっとした気配りのコツ
-
改行を多めに入れて、読みやすくする
-
絵文字・顔文字は使わない
-
署名をつけて、誰からの連絡か明確にする
私も昔、一度だけ急いで送ったメールで改行を忘れてしまい、後から見直して「読みにくかったかも」と反省したことがあります。形式だけでなく、“読みやすさ”もマナーの一部。丁寧な印象を大切にしましょう。
まとめのポイント
-
訃報を知ったらできるだけ早く(24時間以内)送る
-
夜遅い時間帯(21時以降)は避け、翌朝に
-
件名は「お悔やみ申し上げます」など落ち着いた表現に
-
敬語+「です・ます調」で統一
-
宗派がわからない場合は「心よりお悔やみ申し上げます」が安全
形式ばかりを気にせず、「どうか穏やかに過ごしてほしい」という思いを込めて書くことが、何よりのマナーです。
お悔やみメールで避けたいNG表現
お悔やみメールは、言葉ひとつで印象が大きく変わります。
「気持ちは伝えたつもりなのに、相手を傷つけてしまった」ということにならないよう、慎重な言葉選びが大切です。
特に、訃報に接して感情が揺れ動いているときほど、冷静さを失いやすいもの。
ここでは、つい使ってしまいがちなNG表現と、安心して使える代替表現をセットで紹介します。
縁起の悪い言葉に注意
お悔やみの場面では、日常的には問題のない言葉が「不幸の連鎖を連想させる」ために避けられます。
これは日本の言葉文化に根付いた「忌み言葉」の考え方で、葬儀や弔事全般にも共通するマナーです。
避けたい言葉の例
- 「重ね重ね」「たびたび」「再び」
- 「また」「繰り返し」「次々と」
- 「追って」「続いて」「引き続き」
これらの表現は、「不幸が重なる」印象を与えてしまいます。たとえば、「重ね重ね申し訳ございません」は一見丁寧に見えても、場面によっては不適切です。
代わりの言い方
- 「心よりお悔やみ申し上げます」
- 「謹んでお悔やみ申し上げます」
- 「ご冥福をお祈り申し上げます」
このように、繰り返しを示す表現を避け、1回で完結する言葉に置き換えることが基本です。
メール文中での挨拶も1度きりにとどめ、同じ文言を繰り返すことは避けましょう。
ポイント: 「たびたびご連絡差し上げて失礼いたします」など、通常ビジネスでは丁寧な表現でも、お悔やみの場ではNGになることを覚えておきましょう。
カジュアルすぎる表現を避ける
突然の訃報を受けると、つい自分の驚きや悲しみを率直に伝えたくなります。
しかし、お悔やみメールの目的は「自分の感情を伝えること」ではなく、相手を気遣い、寄り添うことです。
NG例
- 「びっくりしました」
- 「信じられません」
- 「そんなことあるんですね」
- 「うそでしょ?」
これらは感情的な表現に聞こえ、相手の心情に踏み込みすぎてしまうことがあります。
訃報に接した驚きや動揺を抑え、相手の気持ちを優先するトーンに整えることが大切です。
代わりの言い方
- 「突然のことでお力落としのことと存じます」
- 「さぞご心痛のことと拝察いたします」
- 「深い悲しみの中にいらっしゃることとお察しいたします」
これらの表現なら、相手の悲しみを理解し、静かに寄り添う印象を与えます。
特にビジネスメールでは、感情的な言葉を避け、落ち着いた敬語表現を意識しましょう。
「頑張って」は励ましでもNG
普段なら「頑張って」は前向きな言葉ですが、悲しみの最中の相手には重く響くことがあります。
喪失の悲しみは時間をかけて癒すもの。そこに「頑張って」「元気出して」といった言葉をかけると、
「頑張らなきゃいけないの?」と感じさせてしまうことも。
私自身、友人を亡くした直後に「頑張ってね」と言われ、
「今は何をどう頑張ればいいのか分からない…」と感じたことがありました。
どんなに善意でも、相手の心に負担をかけてしまうことがあるのです。
NG例
- 「元気出して」
- 「頑張ってください」
- 「しっかりしてください」
代わりの言い方
- 「無理をなさらず、ご自身のペースでお過ごしください」
- 「お体を大切にお過ごしください」
- 「ご自身もどうぞおいたわりください」
「頑張れ」より「休んで」「いたわって」という方向の言葉に変えるだけで、
相手に安心感を与えることができます。
ネガティブな言葉・強い感情表現も控える
お悔やみのメールは、静かなトーンでまとめるのが基本です。
「悲しすぎて」「ショックで」「涙が止まりません」といった強い表現は、
自分の感情を前面に出してしまい、受け取る相手が気を使ってしまうことがあります。
ポイント: 感情を表す言葉よりも、「相手の悲しみに寄り添う」言葉を選ぶのが正解。
代替表現
- 「突然のことでお言葉もございません」
- 「ご心痛のほど、心よりお察しいたします」
これらの言い回しは、感情を抑えつつも誠実な印象を与えます。
重ね言葉・忌み言葉のチェックリスト
お悔やみメールを書く前に、下記のような言葉が入っていないか確認しましょう。
| 種類 | NGワード | 代替表現 |
|---|---|---|
| 縁起の悪い言葉 | 重ね重ね、再び、続いて | 心よりお悔やみ申し上げます |
| 感情的な表現 | びっくりしました、信じられません | お力落としのことと存じます |
| 励ましすぎる言葉 | 頑張って、元気出して | 無理をなさらずお過ごしください |
| ネガティブ表現 | 悲しすぎて、ショックで | ご心痛のほどお察しいたします |
相手の悲しみに「寄り添う」言葉を選ぶ
お悔やみメールでは、丁寧さと静けさがもっとも大切です。
相手の気持ちを癒すのは、派手な言葉や強い表現ではなく、
「静かな思いやり」がこもった一文。
シンプルで優しい言葉を選びましょう。
ビジネスシーンでのお悔やみメール例文
仕事関係者に訃報が届いた場合、スピード感と丁寧さの両立が求められます。
お悔やみメールは「社交辞令」ではなく、ビジネス上の信頼関係を守るためのマナーでもあります。
相手が悲しみの中にあるときこそ、思いやりのある対応が信頼を深めます。
私も会社員時代、上司のご家族の訃報を受けたとき、
「どんな言葉なら負担にならず、気持ちを伝えられるだろう」と悩みました。
お悔やみの言葉は、長文でなくても構いません。心を込めた一文があれば、それで十分です。
ここでは、シーン別に「上司の家族」「取引先」「同僚」「部下」の4パターンを紹介します。
それぞれの立場や関係性によって、言葉選びを少しずつ変えることが大切です。
上司の家族が亡くなった場合
上司のご家族が亡くなられたときは、敬意と配慮を最優先に。
特に「上司本人が喪主」になることも多く、心身ともに負担が大きい時期です。
形式的な文面よりも、相手を思いやる柔らかいトーンでまとめましょう。
件名:お悔やみ申し上げます
本文:
○○部長
このたびはご尊父様のご逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。
突然のことで、さぞお力落としのこととお察しいたします。
ご家族の皆様も、深い悲しみの中にいらっしゃることと拝察いたします。
どうぞお体を大切にされ、ご無理のないようお過ごしくださいませ。
業務のことはどうかお気になさらず、今はご家族とのお時間を大切になさってください。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
(自分の名前)
ポイント:
-
「謹んでお悔やみ申し上げます」は、目上の方への最適な表現。
-
「どうぞお体を大切に」は、形式の中にも温かさを添える一文。
-
「業務は気にしないで」などの気遣いを入れると、実務面でも安心感を与えられます。
上司は責任感が強く、「迷惑をかけたくない」と思ってしまうこともあります。
だからこそ、「今はゆっくり休んでください」というメッセージが心に響くのです。
取引先へのお悔やみメール
取引先の関係者やそのご家族が亡くなった場合は、
「ビジネス上の敬意」と「人としての思いやり」の両方をバランス良く示すことが重要です。
過度に感情的にならず、落ち着いたトーンで誠意を伝えるのが基本です。
件名:お悔やみ申し上げます
本文:
株式会社〇〇
〇〇様
このたびは〇〇様のご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。
突然のことで、さぞご心痛のことと拝察いたします。
本来であれば直接お伺いし、お悔やみを申し上げるべきところ、
略儀ながらメールにて失礼いたします。
ご家族の皆様のお悲しみが少しでも癒やされますよう、心よりお祈り申し上げます。
どうぞお体をおいといくださいませ。
(自社名・部署名・名前)
ポイント:
-
ビジネス関係では「略儀ながらメールにて失礼いたします」を添えることで、
「本来は直接伺うべき」という礼儀を示せます。 -
「お体をおいといください」は、フォーマルかつ柔らかな言葉で相手を気遣う表現です。
取引先とは一定の距離があるため、馴れ馴れしい表現や感情的な言葉は避け、
「礼節を守りながら、相手の立場に寄り添う」姿勢が信頼感を生みます。
同僚へのお悔やみメール
同じ職場の同僚の場合は、相手の状況を知っていることも多く、
形式よりも心のこもった一言が喜ばれます。
「一緒に働いている仲間として気にかけている」という温かいメッセージを意識しましょう。
件名:お悔やみ申し上げます
本文:
○○さん
このたびはご尊父様のご逝去を知り、心よりお悔やみ申し上げます。
急なことで、さぞご心痛のことと存じます。
今はご家族の皆さんと過ごす時間を大切に、どうぞご無理なさらないでください。
落ち着かれた頃に、またサポートできることがあれば声をかけてくださいね。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
(自分の名前)
ポイント:
-
同僚には「です・ます調」を保ちながらも、少しやわらかい言葉を選ぶのが自然。
-
「サポートできることがあれば…」などの一文が、職場での信頼関係を深めます。
私も同僚が喪に服していたとき、「戻る場所がある」と伝えるような言葉を添えたことで、
「心が少し軽くなった」と後から言ってもらえた経験があります。
形式だけではなく、“人として寄り添う”気持ちを込めることが何より大切です。
部下へのお悔やみメール
部下へのメールでは、立場上「気遣い」と「支援の意思」を示すことが求められます。
上司として、業務面の配慮と心のケア、両方を意識しましょう。
件名:お悔やみ申し上げます
本文:
○○さん
ご尊父様のご逝去を知り、謹んでお悔やみ申し上げます。
突然のことで、お力落としのことと拝察いたします。
今はご無理をなさらず、ご家族とのお時間を大切になさってください。
仕事のことは心配せず、こちらでサポートいたしますので安心してください。
ご冥福をお祈り申し上げます。
(自分の名前)
ポイント:
-
「仕事のことは心配せず」など、部下を気遣う具体的な言葉を添えると安心感を与えます。
-
「謹んでお悔やみ申し上げます」は、ビジネスシーン全般で使える最も丁寧な表現です。
部下は「迷惑をかけたくない」と感じがち。
上司からの一言が、「心の支え」になることも多いです。
丁寧さの中に“温かさ”を添えることが信頼を生む
お悔やみメールは、定型文を並べるだけでは心に響きません。
大切なのは、「相手の立場に立ち、思いやりをもって言葉を選ぶ」こと。
-
「謹んでお悔やみ申し上げます」で始める
-
感情的にならず、落ち着いた敬語でまとめる
-
「どうぞご自愛ください」「ご無理のないように」と気遣いを添える
-
関係性に応じて、フォーマル度を調整する
“形式+思いやり”の両立こそが、ビジネスにおけるお悔やみのマナーです。
親族や友人へのお悔やみメール例文
親しい人へのお悔やみメールは、形式よりも「気持ち」や「思い出」が何より大切です。
ビジネスシーンのようにかしこまった表現よりも、心に寄り添うやわらかな言葉でまとめることで、相手に安心感を与えることができます。
私も、親戚のおばが亡くなったとき、夜中に涙をこらえながらメールを書いたことがあります。
「うまく書けているかわからない」と不安でしたが、後日、叔母の娘さんから
「あなたの言葉に救われた」と言ってもらえたとき、“丁寧な形式”よりも“心のこもった一言”こそが人を癒やすのだと実感しました。
ここでは、親族・友人それぞれに向けたメール例文を、感情とマナーのバランスを大切にしながら紹介します。
親族に送る場合|思い出を添えて、心からの言葉を
親族へのお悔やみでは、「家族としての思い出」や「故人の人柄」に触れる一文を添えることで、形式的ではない“生きた言葉”になります。
故人を知る者同士としての共感が、深い慰めになります。
件名:お悔やみ申し上げます
本文:
○○さん
このたびはお母様のご逝去に接し、心よりお悔やみ申し上げます。
あの日、笑顔で話してくださったお母様の優しい声を思い出すと、今も胸がいっぱいになります。
本当に、周りの人を明るくしてくれる温かい方でしたね。
突然のお別れで、悲しみや寂しさは計り知れないことと思います。
どうかご無理をなさらず、ご家族の皆さんと支え合いながら、少しずつお体を休めてください。
私も心よりご冥福をお祈りいたします。
お母様の優しさを胸に、これからも一緒に前を向いて歩んでいきましょう。
(自分の名前)
ポイント:
-
「あの日」「笑顔」「声」など、具体的な記憶を一文添えると、心の温度が伝わる。
-
「無理をしないで」「少しずつ休んで」など、時間をかけた癒やしを促す言葉が◎。
-
家族の悲しみを共有する気持ちを込めることで、「同じ気持ちで寄り添ってくれている」と感じてもらえます。
大切なのは、“何を言うか”より“どう寄り添うか”。
自分なりの言葉で「一緒に悲しみを分かち合う姿勢」を示しましょう。
親戚に送るときの注意点
-
感情的になりすぎない
「ショックです」「悲しすぎて言葉もありません」など、
自分の感情に偏る表現は控えめに。相手の心を癒やすことを第一に考えます。 -
宗教的な言葉は控えめに
親族でも宗派が異なる場合があります。「ご冥福をお祈りします」程度に留めましょう。 -
義理の親族には敬意を忘れずに
義理の両親・兄弟姉妹などには、少し丁寧な言葉遣いを心がけると安心です。
友人に送る場合|言葉より「気持ち」を優先して
友人へのお悔やみメールでは、マナーよりも心に寄り添う「声かけ」が大切です。
親しい関係だからこそ、堅苦しい文面よりも、あたたかくシンプルな言葉が心に響きます。
件名:お悔やみ申し上げます
本文:
○○ちゃん
お父様のご逝去を聞いて、本当に驚きました。
今は何を言えばいいのか言葉が見つからず、ただ心からお悔やみ申し上げます。
お父様の優しい笑顔を思い出すと、胸がいっぱいになります。
○○ちゃんにとって、どれほど大きな存在だったかと思うと、私も胸が締めつけられるようです。
どうか無理をしないでね。
眠れない夜もあるかもしれないけれど、少しずつ気持ちを休めてください。
落ち着いたら、また話そう。私はいつでも話を聞くよ。
心よりご冥福をお祈りします。
(自分の名前)
ポイント:
-
「無理しないで」「いつでも話を聞くよ」など、“そばにいる”ことを伝える一言が大切。
-
「言葉が見つからないけれど」という前置きは、率直でやさしい印象を与えます。
-
「また話そう」「私はここにいる」というメッセージが、相手の孤独を和らげます。
友人へのメールで気をつけたいこと
-
長文になりすぎない
感情が溢れて長く書きすぎると、読む側の心の負担になります。
短くても、思いやりのこもった一文で十分伝わります。 -
命令調・励ましすぎる言葉は避ける
「元気出して」「頑張って」よりも、「無理しないで」「ゆっくりね」といった柔らかい表現を。 -
スタンプや絵文字は使わない
普段のやりとりで使っていても、お悔やみの場面では避けましょう。
文字だけで静かに気持ちを届けるのがマナーです。
状況別のアレンジ例
子どものころから知っている友人の親が亡くなった場合
○○ちゃんのお父さんには、子どもの頃よく遊んでもらったよね。
あのときの笑顔を思い出すと、今でも心が温かくなります。
本当にありがとうございましたと、心からお伝えしたいです。
久しぶりに連絡を取る友人に送る場合
突然のご連絡で驚かせてしまったらごめんなさい。
訃報を聞いて、いてもたってもいられずメールを送りました。
今はどうか、ご自身を責めず、お体を大切にしてください。
形式より「心を込めた言葉」こそが最大の慰め
親族や友人へのお悔やみメールで大切なのは、正しさよりも温かさ。
完璧な言葉を探すよりも、
「相手の悲しみに寄り添う」「故人を一緒に偲ぶ」「体を気遣う」
この3つを意識すれば、自然と心に届くメールになります。
-
故人の思い出を一文添える
-
無理をしないよう気遣う言葉を入れる
-
「いつでも話を聞くよ」と支えの姿勢を示す
メール以外で伝える場合の工夫
お悔やみの気持ちは、メールだけでなく、相手との関係性や状況に合わせて柔軟に伝えることが大切です。
最近では、訃報をLINEなどのSNSで受け取ることも増えており、その場で返信を求められるケースもあります。
一方で、時間をおいてから手紙やハガキで丁寧に想いを伝えることも、昔ながらの温かい方法として根強い価値があります。
ここでは、「LINE」と「ハガキ・手紙」の2つのケースについて、それぞれのマナーと気配りのポイントを詳しく見ていきましょう。
LINEで伝えるとき|絵文字なし・シンプルに心を込めて
スマートフォンが普及した今、訃報をLINEで知ることは珍しくありません。
家族や友人、同僚など、親しい関係であれば、LINE上でやりとりを完結させることもあります。
ただし、通常のトーンとは切り替え、フォーマルな文面で丁寧に対応することが大切です。
LINEでのお悔やみの基本マナー
-
絵文字・スタンプ・顔文字は使用しない
-
改行を入れて、落ち着いた印象に整える
-
短くても「気持ちが伝わる文面」にする
-
深夜や早朝の送信は避け、相手の負担にならない時間帯に送る
返信の目的は「気持ちを伝えること」
お悔やみLINEでは、長文で書くよりも、「相手を思う気持ち」を簡潔に表すことが大切です。
文章が短くても、誠実さが伝わればそれで十分です。
例文①(フォーマル寄り)
このたびはご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。
突然のことで驚いております。どうかお体を大切にお過ごしください。
例文②(親しい関係の場合)
○○ちゃんのお父様のご逝去を聞いて、本当に驚きました。
今は言葉が見つからないけれど、心からお悔やみ申し上げます。
どうか無理をせず、少しずつ休んでね。
ポイント:
-
「びっくりした」「悲しい」など自分の感情よりも、相手の心情への配慮を優先する。
-
「また話そうね」「無理しないでね」など、そっと寄り添う一言を添えると温かみが出ます。
-
“返事を求めない”メッセージにすることも思いやりです。相手が返信に気を使わずに済むよう、「返事はいりません」や「落ち着いたらで大丈夫です」と添えるのも◎。
送信タイミング
訃報を受け取った直後に返信するのが基本です。
ただし、夜遅い時間帯(21時以降)は避け、翌朝に送るなど時間帯への気配りを忘れずに。
相手が悲しみの中で過ごしていることを踏まえ、焦らず、“静かなトーン”で寄り添う姿勢を心がけましょう。
ハガキ・手紙で伝える|後日の「心を込めた一筆」が支えに
メールやLINEよりも時間がかかりますが、手書きの手紙やハガキには“ぬくもり”が宿ります。
特に、四十九日や一周忌など、少し時間が経った節目に送ると、遺族にとって「忘れずにいてくれた」という安心感につながります。
手紙・ハガキを送るタイミング
-
四十九日、または一周忌の頃
-
訃報を後から知った場合(「喪中見舞い」として送る)
-
遠方で葬儀に参列できなかった場合
ポイント: 「今さらかな…」と思っても、“思い出してくれたこと自体”が相手の慰めになります。
書き方の基本構成
-
【冒頭】 訃報を知った驚きとお悔やみの言葉
-
【中盤】 故人への思い出・感謝の気持ち
-
【結び】 ご遺族への気遣い・体調への配慮
例文①(親族・年配者向け)
拝啓
このたびはご母堂様のご逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。
あの穏やかな笑顔と、いつも優しく声をかけてくださったお姿を思い出すと、今も胸が熱くなります。
季節の変わり目でもございますので、どうかお体を大切にお過ごしください。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
敬具
(自分の名前)
例文②(友人・知人向け)
○○ちゃん
お母様のご逝去を知り、心からお悔やみ申し上げます。
子どものころ、一緒にお家に遊びに行ったとき、お母様が出してくださった手作りお菓子の味、今でも覚えています。
あの温かい笑顔が忘れられません。
どうか無理をせず、ご家族でゆっくりお過ごしくださいね。
心よりお母様のご冥福をお祈りします。
(自分の名前)
封筒・便箋のマナー
-
便箋・封筒は白無地またはグレー系が基本。華やかな柄やカラーは避ける。
-
ボールペンよりも黒の万年筆または筆ペンが望ましい。
-
差出人名は封筒の裏に明記し、封は糊付けのみ(テープやシールは使わない)。
メール以外で伝えるときの心構え
-
「形式」より「思いやり」を重視する
短くても誠実な言葉を選び、相手の気持ちに寄り添うことを意識しましょう。 -
相手の立場を考える
忙しい時期や深い悲しみの中にいることを踏まえ、返信を求めない一方通行のメッセージでも十分です。 -
自分の気持ちを押しつけない
励ましよりも、「お体を大切に」「ご無理のないように」といったやさしい気遣いを添えましょう。
“今、寄り添いたい”気持ちを最も伝えやすい方法で
お悔やみの気持ちは、「どう伝えるか」より「どんな想いで伝えるか」が大切です。
LINEなら短くても真心を込めて。手紙なら一筆一筆を丁寧に。
どんな手段でも、あなたの温かい気持ちは必ず相手に届きます。
静かな思いやりを込めて伝えましょう。
体験談|私がお悔やみメールを送ったときの話
私が初めて「お悔やみメール」というものを書いたのは、娘が1歳の頃でした。
夜、寝かしつけの途中で鳴ったスマホ。静かな部屋の中、ふと表示された名前を見た瞬間、胸の奥がざわつきました。
学生時代の友人からのメッセージには、「母が亡くなりました」の一文。
一瞬で涙があふれて、目の前がにじんでしまいました。
友人のお母さんは、学生のころから私にとって特別な存在でした。
遊びに行くたびにお菓子を出してくれたり、夜遅くまで話を聞いてくれたり…。
私にとっても“第二の母”のような存在でした。
だからこそ、「何か言葉をかけたい」と思う一方で、いざ書こうとすると指が止まってしまったのです。
「こんな時、どんな言葉が正しいんだろう?」
「悲しみに寄り添いたいけど、間違った表現をして傷つけてしまわないだろうか…」
普段ならすぐに返信できる私も、このときばかりはスマホを握りしめたまま動けませんでした。
「“ご冥福をお祈りします”でいいのかな?」「“お世話になりました”って書いても失礼じゃないかな?」
いろんな言葉が頭に浮かんでは消えていき、どうしても一文にまとまりません。
そんなとき、隣で娘を寝かしつけていた夫に思い切って相談しました。
「どう書いたらいいと思う?」と聞くと、夫は少し考えて、穏やかにこう言いました。
「難しく考えすぎないで。自分の素直な気持ちをそのまま伝えたら、それが一番伝わると思うよ。」
その言葉に、ふっと肩の力が抜けました。
形式や正解を探すのではなく、“心からのありがとう”を伝えることが大事なんだと気づかされた瞬間でした。
私は深呼吸をして、短く、けれど真っすぐな気持ちを込めてこう書きました。
「お母さんには学生のころ本当にお世話になりました。心よりお悔やみ申し上げます。」
わずか2行のメッセージ。
それでも、書き終えたあと、胸の中に少しだけ温かいものが広がりました。
「この言葉なら、あのお母さんにも、友人にも届くかもしれない」
そう思いながら、送信ボタンを押しました。
翌日、友人から返ってきたメッセージにはこう書かれていました。
「ありがとう。あなたの言葉に励まされました。」
それを読んだ瞬間、胸がいっぱいになりました。
完璧な言葉じゃなくても、心を込めた言葉は必ず届く。
そう確信した出来事でした。
この経験を通して、私は「お悔やみメール」に対する考え方が変わりました。
最初は「間違えてはいけない」「マナーを守らないと」と、形ばかりを気にしていました。
けれど、実際に大切なのは“文面の整い”ではなく、“相手を思う気持ち”と“誠実さ”なんですよね。
今、もし誰かから「お悔やみのメール、どう書けばいい?」と相談を受けたら、私はこう答えると思います。
「あなたが心から感じたことを、短くてもいいからまっすぐに伝えたら、それがいちばんの言葉になるよ。」
お悔やみの場面では、誰もが緊張し、何を言えばいいのか迷います。
けれど、「あなたの存在を思い出してくれて嬉しかった」と思える人はたくさんいるのです。
そして、その一通のメールが、悲しみの中の心をほんの少しでもあたためてくれることがあります。
“思いやりのある一文”は、どんな長文よりも力を持つ。
お悔やみメールは、相手の悲しみを癒やすためだけでなく、送る自分自身の「ありがとう」を形にする大切な時間でもあるのだと、あのときの経験が教えてくれました。
まとめ|形式より「思いやりの気持ち」を大切に
お悔やみメールは、難しい言葉よりも「寄り添う気持ち」が伝わることが何より大切です。
迷ったときは、「相手の立場になって考える」「自分ならどう言われたいか」を思い出してみてください。
-
早めに連絡する
-
敬語で落ち着いた文面にする
-
不幸を連想させる言葉を避ける
-
相手の心に寄り添う一言を添える
大切な人を思う気持ちがあれば、きっとそのメールは相手の心に届きます。
慌てず、心を込めて言葉を選びましょう。