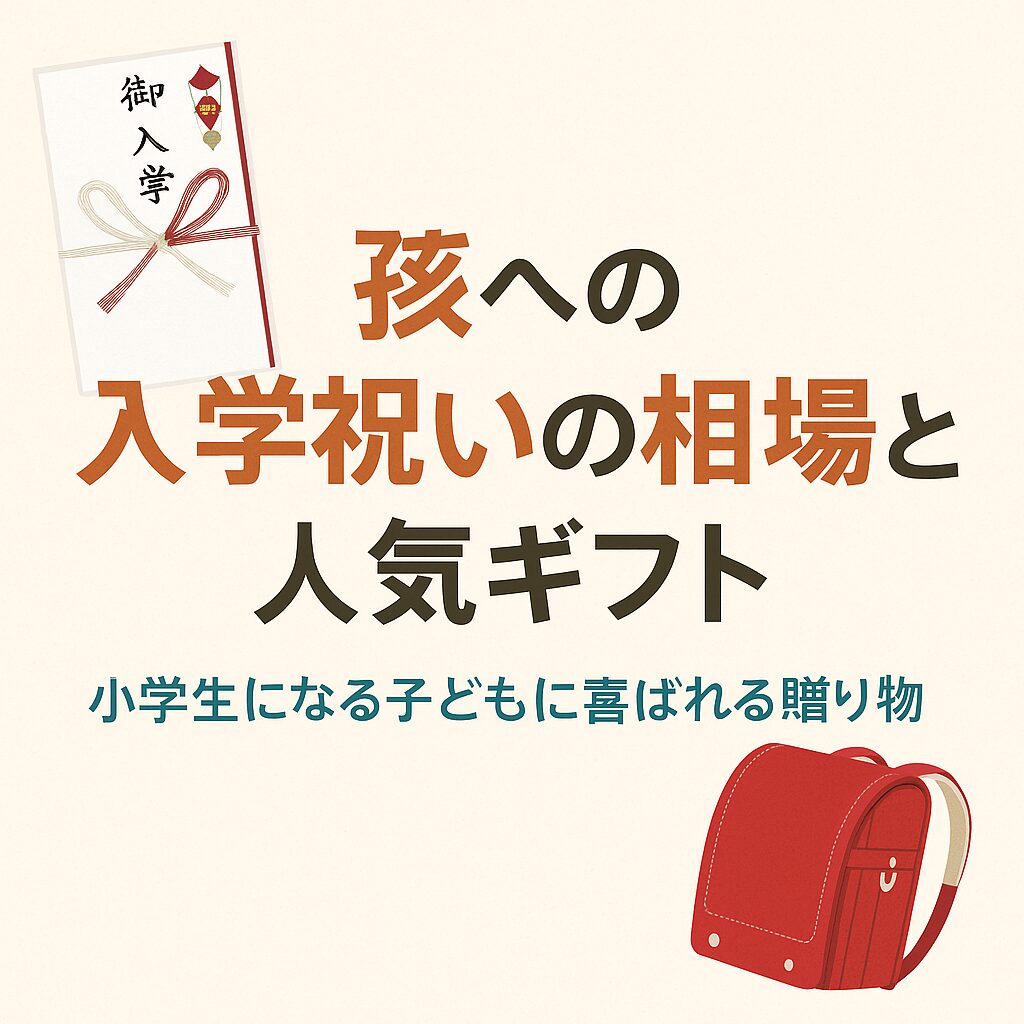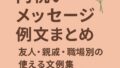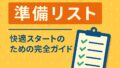孫への入学祝い、相場はいくらが適切なのか悩んでいませんか?
「せっかくのお祝いだから失礼のない金額にしたい」「喜んでもらえる贈り物を選びたい」と考えるのは自然なことです。
本記事では、孫に贈る入学祝いの相場に関する基本情報や、人気のギフトアイデア、贈るときのマナーまでわかりやすく解説します。
大切なお孫さんの新たな門出を、心温まる贈り物で応援するために、ぜひ最後までご覧ください!
孫への入学祝いの相場とは
入学祝いの金額はどれくらい?
孫への入学祝いの金額相場は、一般的に1万円〜3万円程度とされています。
祖父母から贈る場合は、両親や親戚からの祝い金よりもやや高めに設定されることが多く、特別な存在ならではの「応援の気持ち」を込めるのが一般的です。
とはいえ、無理をして高額なお祝いを贈る必要はありません。
家庭の経済状況や地域の慣習、親との関係性を踏まえ、無理のない金額設定をすることが何より大切です。
また、孫が複数いる場合には、将来にわたって公平性を保てる金額設定を意識しておくと、後々のトラブル防止にもつながります。
小学校入学祝いの相場と人気のギフト
小学校への入学は、子どもにとって大きな節目です。
このため、ランドセルや学習机といった高額な記念品を贈るケースも多く、相場がやや高めになる傾向があります。
具体的には、
-
ランドセル代:5万円〜7万円
-
学習机代:3万円〜10万円
が一般的な目安です。
ただし、物品ではなく現金で渡す場合は、1万円〜2万円程度でもまったく失礼にはあたりません。
最近では、子ども自身や親が好みの商品を自由に選びたいというニーズも高まっており、現金やギフトカードを贈るスタイルも増えています。
一方で、形に残る記念品を贈ることは、孫にとっても心に残る思い出となるため、品物の贈り物も根強い人気を誇っています。
祝金と商品の選び方について
入学祝いを現金で渡すか、品物で贈るかは、それぞれにメリットがあります。
現金のメリット
-
親が必要なものを自由に購入できる
-
実用品や教育資金など、用途の幅が広い
-
持ち運びが便利でスマート
品物のメリット
-
特別な思い出として孫の心に残る
-
ランドセルや学習机など、長く使える
-
贈った側の気持ちが伝わりやすい
特に、ランドセルや文房具セット、図書カードなどは、贈った思い出を子どもが成長しても覚えていることが多く、祖父母ならではのギフトとして人気です。
どちらを選ぶか迷う場合は、事前に親御さんと相談し、必要なものや希望を確認してから決めると、より喜ばれる入学祝いになります。
祖父母が贈る入学祝いのマナー
適切な金額の設定について
孫1人あたりの入学祝いの金額は、一般的に1万円〜3万円程度が目安とされています。
ただし、この金額はあくまで相場であり、重要なのは家庭の収入バランスを意識することです。
無理をして高額なお祝いを用意する必要はありません。
たとえば、兄弟姉妹や従兄弟が複数いる場合、将来的に金額差が目立つと不公平感が生まれる可能性もあるため、兄弟間で金額に差が出ないよう細心の配慮をしましょう。
また、初孫の場合はつい気持ちが高ぶり、高額なお祝いをしたくなりがちですが、他の孫にも同様の対応ができるかを考えておくと、長期的なバランスが取れます。
「気持ちを込めることが何より大切」という視点を忘れずに、適切な金額を決めることが大切です。
のし紙の書き方とタイミング
入学祝いを贈る際は、正式なマナーとして紅白の蝶結びののし紙を使用します。
蝶結びは「何度あっても良い慶事」に用いられるため、入学祝いに最適です。
【のし紙の書き方】
-
表書き:「祝御入学」または「御入学御祝」
-
下段:贈り主のフルネーム(名字だけより、名前も添える方が丁寧)
また、現金の場合は祝儀袋(のし袋)を使用し、品物の場合でもラッピングの上からのし紙をかけると、より正式な印象になります。
【贈るタイミング】
理想的な時期は、入学式の2〜3週間前。
遅くとも入学式当日までには届くように手配しましょう。
直接手渡しできない場合は、配送日指定を活用すると安心です。
贈り物に対する内祝いの考え方
基本的に、祖父母からの入学祝いには、内祝い(お返し)は不要とされています。
祖父母にとっては「孫の成長を祝う喜び」が最大のご褒美であり、形式的なお返しは求めないのが一般的です。
しかし、感謝の気持ちはしっかり伝えることが大切です。
おすすめの方法としては、
-
孫本人から「ありがとう」の手紙を送る
-
入学式の写真を添えたメッセージカードを贈る
-
成長した姿を伝えるビデオレターを送る
など、心のこもった形でお礼を伝えると、さらに絆が深まります。
小さな気遣いが、祖父母にとっては何よりうれしい贈り物になりますので、ぜひ一手間かけてみましょう。
入学祝いで喜ばれる人気ギフト
ランドセルや学習机の選び方
孫への入学祝いとして定番のランドセルや学習机は、選び方にもポイントがあります。
【ランドセルの選び方】
最近では、従来の重厚な革製ランドセルだけでなく、軽量タイプやデザイン重視のモデルが人気です。特に、A4フラットファイル対応サイズや、背負いやすさに配慮したモデルは実用性が高く、親御さんにも喜ばれます。
ブランドについても、土屋鞄、池田屋、セイバンなどの有名メーカーが人気。
購入前には、必ず親御さんと相談し、希望のブランドやカラー、素材(人工皮革か本革か)を確認しておくと安心です。
また、最近は「ランドセルを本人が選びたい」という家庭も増えているため、購入支援金という形で現金を渡すスタイルも増えています。
【学習机の選び方】
学習机も、近年は「リビング学習」が主流になってきていることから、コンパクトタイプや高さ調整可能なデスクが人気です。
成長に合わせて天板の高さや椅子のサイズを変えられるロングユースタイプを選ぶと、小学校から中学・高校まで長く使うことができます。
また、収納スペースが工夫されているデスクを選ぶと、整理整頓の習慣づけにも役立ちます。
文房具や図書カードのおすすめ
入学祝いとして気軽に贈れるアイテムに、高品質な文房具セットや図書カードがあります。
【文房具セットのおすすめ】
高学年まで長く使える筆箱、鉛筆、定規、色鉛筆、ノートなどを組み合わせたセットは実用性抜群。
特に、人気キャラクターものやおしゃれなデザインの文房具は、子どものモチベーションを高める効果もあります。
また、質の良い文具を贈ることで、学ぶ楽しさや道具を大切にする心を育むきっかけにもなります。
【図書カードのおすすめ】
図書カード(3000円〜5000円程度)は、子ども自身が好きな本を選べる自由度が魅力。
読みたい本を自分で選び、買う喜びを味わうことができるため、読書習慣を促進する効果も期待できます。
図書カードNEXT(全国の書店で使えるカード)なら、遠方に住んでいる孫にも気軽に贈ることができるので便利です。
カタログギフトを活用する方法
「何を贈ればいいか迷う」という場合には、子ども向け専用のカタログギフトを活用するのもおすすめです。
【子ども向けカタログギフトの特徴】
最近では、文具、知育玩具、科学実験キット、図鑑、絵本など、子どもの好奇心を刺激するアイテムが揃ったカタログギフトが登場しています。
たとえば、ハーモニックの「えらべるギフト こども向けシリーズ」などは、年齢別に最適な商品ラインナップが用意されており、選ぶ楽しさを体験できます。
【カタログギフトのメリット】
-
子ども自身が好きなものを選べるワクワク感
-
親が「必要なもの」を選べる実用性
-
贈り主側も「外れ」のリスクを減らせる安心感
また、カタログギフト+メッセージカードをセットで贈ると、気持ちもしっかり伝わり、さらに喜ばれるでしょう。
入学祝いの贈り物の種類
現金の活用法と注意点
孫への入学祝いに現金を贈る場合は、いくつか押さえておきたいマナーとポイントがあります。
【現金を贈る際のマナー】
まず、新札を用意するのが基本です。折り目や汚れのない新しいお札には、「これからの門出を祝う」という意味が込められているため、事前に銀行などで両替しておきましょう。
現金は、紅白の蝶結びの水引がついたのし袋(祝儀袋)に包みます。表書きには「祝御入学」「御入学御祝」などと書き、下段には贈り主のフルネームを記載します。
【注意すべきポイント】
現金を贈る際は、金額が高額になりすぎないよう注意が必要です。
一般的な目安は1万円〜3万円ですが、あまりにも高額だと親御さんに気を遣わせてしまうこともあります。
相場感を意識しつつ、家庭の事情や親との相談を踏まえて、無理のない範囲で設定しましょう。
品物との組み合わせの提案
現金だけを渡すのが味気ないと感じる場合は、現金+ちょっとしたプレゼントを組み合わせるスタイルもおすすめです。
【組み合わせ例】
-
現金+高品質な文房具セット(ペンケース・多機能ペンなど)
-
現金+キッズ向け腕時計(時間管理の練習にも◎)
-
現金+知育パズルや学習ゲーム
このように、金銭面でのサポートと形に残るギフトの両方をカバーできるため、より思い出深い贈り物になります。
また、品物は孫本人に、現金は親御さんに手渡す形にすると、管理面でもスムーズです。
ハーモニックやセットアイテムの魅力
「何を贈ればいいか迷う」「好みがわからない」という場合には、ハーモニックのカタログギフトなどの活用がおすすめです。
【ハーモニックのカタログギフトの特徴】
-
子ども向けラインナップが充実(文房具、図鑑、知育玩具など)
-
価格帯が3000円台〜1万円以上まで豊富
-
年齢に応じたカタログを選べるため失敗しにくい
【カタログギフトのメリット】
カタログギフトなら、子ども本人や親御さんが本当に欲しいものを選べるため、ミスマッチを防ぐことができます。
また、「選ぶ楽しみ」もプレゼントできるので、子どもの自主性を育むきっかけにもなります。
【セットアイテムの活用】
最近では、文房具セットや学習サポートグッズなどがセットになったギフトボックスも人気。
たとえば、
-
「小学校入学祝い専用ギフトセット」
-
「知育おもちゃ+図書カードのコンビセット」
など、テーマに合わせた贈り方を選ぶと、よりセンスの光るプレゼントになります。
入学祝いのタイミングと時期
入学式前後のベストタイミング
孫への入学祝いを贈るタイミングは非常に重要です。
理想的なのは、3月中旬〜4月初旬の間。
この時期はちょうど卒園式と入学準備の間にあたるため、子どもや家族にとっても心に余裕があり、しっかりとお祝いの気持ちを受け取ってもらいやすい時期です。
早すぎると卒園祝いとの区別がつきにくくなり、遅すぎると入学式や新生活が始まった後で気持ちのタイミングがずれてしまう可能性があります。
そのため、春休み期間中に手渡しするイメージでスケジュールを組むとよいでしょう。
また、遠方に住んでいる場合は、3月中旬を目安に配送手配を済ませるのがおすすめです。
事前に用意すべきアイテムとは
入学祝いでランドセルや学習机、制服関連などを贈る場合には、早めの準備が必要です。
特にランドセルや学習机は、人気ブランドやデザインのものは秋頃には完売することも珍しくありません。
そのため、これらを贈りたいと考えているなら、前年秋頃からリサーチを始めるのがベスト。
例えば、ランドセル選びでは「ラン活(ランドセル活動)」と呼ばれる動きがあり、夏頃から予約受付がスタートするブランドもあります。
制服についても、サイズ直しや小物類の準備が必要なため、余裕を持って手配できるよう親御さんと事前に相談しておきましょう。
間際になってバタバタしないためにも、贈り物の種類によって準備スケジュールを意識することがポイントです。
季節や状況を考慮した贈り方
新型コロナ禍やインフルエンザの流行時期など、健康リスクが高い時期には、直接の手渡しを控える配慮も必要です。
この場合、
-
ギフトを郵送する
-
オンラインギフト(電子ギフト券など)を活用する
-
メッセージカードを同封して気持ちを伝える
など、安全と心遣いを両立する方法を選びましょう。
また、配送を利用する場合も、単なる荷物の到着にならないように、「お祝いの気持ちが伝わる演出」を忘れずに。
たとえば、のし紙やリボン付きのギフトラッピング、孫への手書きメッセージカードを添えることで、温かみのある贈り方ができます。
季節や社会状況に応じた柔軟な対応を心がけることで、より心に残る入学祝いとなるでしょう。
入学祝いのメッセージの書き方
孫への入学祝いには、心のこもったメッセージカードを添えると、贈り物がより一層温かみのあるものになります。
直接会えない場合でも、言葉を通して祝福の気持ちや応援の想いを伝えることができるので、ぜひ取り入れましょう。
メッセージカードのアイデア
メッセージは、明るく前向きな言葉を中心に、子どもが読んでわかりやすい内容にするのがポイントです。
たとえば、
「ご入学おめでとう!新しい友達とたくさん楽しい思い出を作ってね」
といったシンプルで温かい言葉を手書きで添えるだけでも、子どもの心に響きます。
【さらに一工夫するなら】
-
子どもの好きなキャラクターのシールを貼る
-
カラフルなペンを使ってカラフルに書く
-
メッセージカードに写真やイラストを添える
このように、親しみやすさと遊び心を加えると、メッセージがより印象深いものになります。
お祝いの言葉や書き方のポイント
お祝いの言葉は、堅苦しくなりすぎないことが大切です。
小学校に入学する子どもは、まだ漢字をすべて理解していないことも多いため、ひらがなや簡単な言葉を中心にすると、子ども自身が読める喜びも味わえます。
【書き方のポイント】
-
短くても気持ちが伝わる内容にする
-
明るく、ポジティブな表現を心がける
-
プレッシャーを感じさせる表現(例:「たくさん勉強しなさい」など)は避ける
【例文】
「たくさんのことを楽しんでね。応援しているよ!」
「学校生活がキラキラ輝きますように!」
子どもの心に寄り添った言葉選びをすることで、より心に残るメッセージになります。
子どもへの思いを伝える方法
お祝いの言葉に加えて、子どもをそっと支える気持ちを伝える一文を添えると、より深いメッセージになります。
たとえば、
「困ったことがあったら、いつでもおじいちゃん・おばあちゃんに相談してね」
といった一言は、子どもに安心感を与えるだけでなく、心の支えになります。
【その他に伝えたい想い例】
-
「頑張る姿をいつも見守っているよ」
-
「新しい世界をいっぱい楽しんでね」
-
「いつでも味方だよ。応援しているからね!」
こうした言葉は、子どもにとって大きな励みになりますし、家族の絆をさらに強めるきっかけにもなります。
入学祝いで気をつけるポイント
入学祝いは、孫の成長を祝う素晴らしい機会ですが、贈る際にはいくつか注意すべきポイントがあります。
気持ちだけが先行してしまうと、かえって相手に負担を感じさせてしまうこともあるため、心遣いとバランスを意識することが大切です。
高額なお祝いの考え方とその背景
「孫がかわいいから」と、つい奮発したくなる気持ちは自然なものですが、あまりにも高額すぎる入学祝いは注意が必要です。
一般的な相場(1万円〜3万円程度)を大きく超えるような高額な贈り物は、親に心理的な負担を与える場合があります。
例えば、
-
「お返しをどうすればいいのか」と悩ませてしまう
-
「次の兄弟にも同じだけ用意しなければならない」と感じさせてしまう
など、喜びよりも気遣いが勝ってしまうことも。
贈る側は「純粋に祝いたい」という思いでも、受け取る側は「負担」と受け止めることもあるため、家庭全体のバランスを見ながら、無理のない金額設定を心がけましょう。
「孫を思う気持ちが伝わる範囲内で贈る」ことが何より大切です。
失礼にならない贈り物の選び方
贈り物を選ぶ際は、実用性と華やかさをバランスよく兼ね備えたアイテムを選ぶのがポイントです。
【選び方のコツ】
-
実用的で長く使えるもの(例:ランドセル、図書カード、文房具セット)
-
見た目にも華やかでお祝いらしいもの(例:ラッピングがきれい、デザイン性の高いギフト)
-
子どもと親、両方に喜ばれるもの(例:子どもには楽しみ、親には実用性)
逆に、贈る側の自己満足になってしまうと、かえって相手を困らせることになります。
たとえば、好みが大きく分かれるファッションアイテムや、保管や管理に困る高額品などは慎重に考えましょう。
「受け取る側の立場に立って選ぶ」ことを常に意識するのが、失礼にならない贈り方の基本です。
兄弟や他の親戚との調整
孫が複数いる場合や、親戚間で子どもが多い場合には、贈り物の金額や内容に不公平感が出ないように注意が必要です。
【注意すべきシチュエーション】
-
兄弟のうち、一人だけ高額な贈り物をもらった
-
従兄弟間で入学祝いの有無や金額に大きな差があった
などが起きると、親同士や子ども同士で微妙な空気になりかねません。
【対策方法】
-
事前に親と相談して、金額の目安をすり合わせる
-
孫ごとに内容を揃える(現金+文房具セットなど統一感を持たせる)
-
年齢差がある場合でも、祝う気持ちを形にして平等感を意識する
特に、最初の孫への対応が今後の「基準」となるケースが多いため、最初から無理のない範囲で統一感のあるルールを作っておくと安心です。
入学祝いの金額の変動要因
入学祝いの金額相場は一律ではなく、家庭環境や地域性、文化的背景によって大きく変わる場合があります。
「何が正解か」ではなく、それぞれの状況に合わせて柔軟に考えることが大切です。
ここでは、金額が変動する主な要因について詳しく解説します。
家族の状況や経済状況を考える
まず第一に、家族の状況や家計のバランスを考慮することが大切です。
子どもや孫が複数いる場合、最初は気持ちが高ぶり、つい奮発してしまいがちですが、将来的にも同じように祝い続けることを考える必要があります。
【具体例】
-
孫が3人いる場合、最初の孫だけ5万円、他は1万円だと不公平感が生じる
-
将来的な誕生日祝いや進学祝いとのバランスを取る必要がある
また、贈る側自身の家計事情も重要です。
無理をして高額な祝い金やプレゼントを用意するよりも、無理なく続けられる範囲内で心を込めることが、長期的な良好な関係を築くポイントです。
地域差や文化の影響について
入学祝いの金額には、地域ごとの習慣や文化が色濃く影響することもあります。
【地域差の例】
-
都市部では現金ベースでシンプルに贈る傾向が強い
-
地方では、品物(ランドセルや学習机)を贈る習慣が根強く残っている
-
地域によっては親戚一同でまとまった祝い金を贈るケースもある
たとえば、東日本と西日本でも、祝い事に対する感覚や形式が若干異なることがあります。
地元の慣習を尊重しつつ、親御さんと相談しながら柔軟に対応することで、不要なトラブルや誤解を防ぐことができます。
入学式の重要性と相場の変化
特に小学校の入学式は、子どもにとっても家族にとっても人生の大きな節目とされるイベントです。
そのため、入学祝いにも特別な意味合いが込められ、自然と金額が高めになる傾向があります。
【相場が高まる背景】
-
ランドセル購入支援を兼ねた祝い金
-
学習机や学用品など高額品の贈呈
-
「一生に一度の晴れ舞台を盛大に祝いたい」という思い
ただし、最近では経済状況やライフスタイルの多様化に伴い、現金+実用的な小物ギフトなど、負担を抑えたスマートなお祝いスタイルも増えてきています。
大切なのは、金額そのものではなく、祝う気持ちが伝わることです。
家族で無理なく、気持ちよく贈れる範囲でお祝いをすることが、何よりも大切な考え方といえるでしょう。
入学祝いを贈る際の注意点
入学祝いは、単に品物や現金を贈るだけではなく、渡し方やタイミング、贈る側の気遣いも非常に大切です。
ここでは、贈る際に気をつけたいポイントについて詳しくご紹介します。
適切な時間帯や場面について
入学祝いを直接手渡しする場合は、家族の生活リズムや予定を配慮することが基本マナーです。
【手渡しの際のポイント】
-
事前に訪問の希望日時を連絡して確認する
-
入学準備や行事などで忙しい時期のため、訪問時間はコンパクトにまとめる
-
一般的には、昼食後から夕方頃(13時〜16時頃)の訪問が無難
特に、小さな子どもがいる家庭では、食事や昼寝のタイミングに配慮する必要があります。
「少しだけお祝いを渡しに伺います」という気軽なニュアンスでアポイントを取ると、相手も安心して迎えることができるでしょう。
もし直接訪問が難しい場合には、配送で贈りつつ、電話やビデオ通話でお祝いの言葉を伝える方法もおすすめです。
相手の年齢や関係性の考慮
贈り物を選ぶ際には、相手(孫)の年齢や性格、親との関係性を意識することが大切です。
【考慮すべきポイント】
-
小学校低学年:かわいいデザインやキャラクター系も喜ばれる
-
小学校高学年:シンプルで「大人っぽい」デザインを好む子も
-
活発な子にはスポーツ用品やリュック、読書好きな子には図書カードや本も◎
また、親との関係性も考慮しましょう。
-
近い関係:多少カジュアルなギフト選びでもOK
-
少し距離がある場合:よりフォーマルなギフトや、親にも配慮したアイテム選びが無難
「子ども本人だけでなく、親も喜ぶ贈り物を選ぶ」意識を持つと、さらに好印象になります。
贈り物選びの参考になる情報源
どんなギフトが喜ばれるか迷ったら、最新のギフトトレンドをリサーチするのがおすすめです。
【情報源例】
-
百貨店のギフトカタログや店頭コーナー
→定番ギフトから最新アイテムまで網羅。年齢別の提案も充実しています。 -
子ども向けギフト専用カタログ
→ハーモニック、リンベルなどのブランドカタログが人気。選べる楽しみも贈れます。 -
オンラインショップの特集ページ
→楽天市場、Amazon、LOFT、東急百貨店オンラインなどの「入学祝い特集」は要チェック。レビューも参考になります。
これらを活用して選択肢を広げておくと、相手の好みに合った素敵なギフトが見つかりやすくなります。
また、人気ランキングや口コミを参考にすることで、失敗しにくいギフト選びが可能になります。
まとめ|お孫さんにぴったりの入学祝いを選びましょう!
孫への入学祝いは、金額の相場を押さえつつ、子どもの成長を応援する気持ちを込めることが大切です。現金だけでなく、ランドセルや文房具、図書カードなど、実用的かつ心に残る贈り物を選びましょう。
また、地域や家庭の慣習にも配慮しながら、無理のない範囲で祝うことが何よりの思いやりです。
本記事を参考に、ぜひお孫さんにとって一生の思い出に残る素敵な入学祝いを贈ってくださいね!