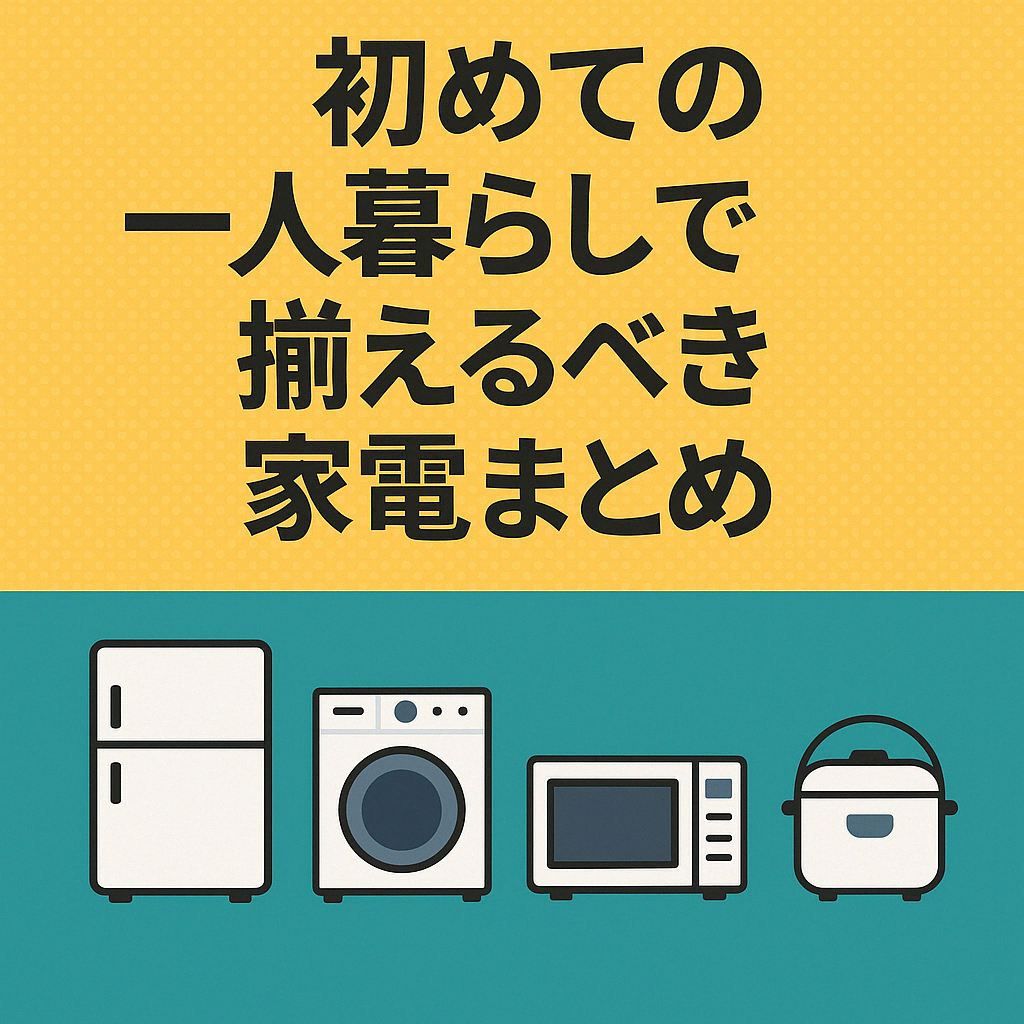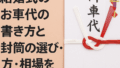初めての一人暮らし、楽しみな反面「どんな家電を揃えればいいの?」と悩んでいませんか?限られた予算とスペースの中で、必要最低限の家電を選ぶのは意外と難しいものです。
この記事では、一人暮らしを快適に始めるために必要な最低限の家電をリストアップし、選び方のポイントやおすすめアイテムを分かりやすくご紹介します。無駄なく賢く揃えて、理想の新生活をスタートさせましょう!
一人暮らしで揃えるべき家電のリスト
家電選びの基準とは
一人暮らしで家電を選ぶ際は、限られた予算とスペースを有効に使うために、3つの基準を意識すると失敗しにくくなります。
-
本当に必要か(必須性)
→ 最初から「あると便利」なものまで揃えるのではなく、「生活に直結するかどうか」を基準に優先順位をつけましょう。 -
コンパクトか(省スペース性)
→ ワンルームや1Kでは設置場所に限りがあるため、サイズや形状も選定基準の一つになります。多機能で小型の製品を選ぶと効率的です。 -
電気代に優しいか(省エネ性)
→ 一人暮らしでも電気代は意外とかさみます。省エネラベルや年間消費電力量をチェックして、長期的にコスパが良い家電を選びましょう。
また、はじめは必要最低限の家電だけを揃え、生活を始めてから本当に必要だと感じたものを追加するスタイルもおすすめです。無駄な出費やスペースの浪費を防げます。
生活に必要な最低限の家電
初めての一人暮らしで最低限必要な家電は、以下の6つです。
-
冷蔵庫:食材や飲料を保存するための基本アイテム。自炊しない人でも必要。
-
洗濯機:コインランドリーの利用も可能ですが、時間や手間、費用を考えると自宅にあると便利。
-
電子レンジ:弁当の温め、冷凍食品の解凍など、食生活に欠かせない存在です。
-
炊飯器:白米はもちろん、時短調理や節約にも役立ちます。
-
照明器具:備え付けがない場合は必須。LEDで明るさや色調が調整できるものが人気。
-
掃除機:部屋を清潔に保つために重要。小型で扱いやすいスティック型が一人暮らしには最適です。
これらの家電が揃っていれば、生活の基本的なインフラが整うため、安心して新生活をスタートできます。
人気の家電セットをチェック
初期費用を抑えつつ必要な家電を一気に揃えたい方には、「一人暮らし家電セット」の活用がおすすめです。
多くの家電量販店や通販サイトでは、以下のようなセット販売が行われています。
-
2点セット(冷蔵庫+洗濯機)
-
3点セット(冷蔵庫+洗濯機+電子レンジ)
-
4点セット(上記+炊飯器)など
セットで購入するメリット:
-
単品購入より安い(1〜2万円ほどお得な場合も)
-
配送・設置が一括で済むため手間が少ない
-
デザインや色味に統一感がある
また、引っ越し業者と連携して家電セットを提供しているサービスもあるため、引っ越しと同時に家電を揃えたい方にもぴったりです。
冷蔵庫の選び方と必要性
冷蔵庫のサイズと配置のポイント
冷蔵庫を選ぶ際は、「どれくらい自炊をするか」「部屋の広さ」「設置スペース」を基準に考えるのがポイントです。自炊の頻度に応じて、以下のようなサイズが目安になります。
-
自炊をほとんどしない場合(外食・コンビニ中心)
→ 100L〜150L前後のコンパクトサイズ
→ 飲み物や軽い食材の保存には十分 -
自炊をよくする場合(毎日・週に数回)
→ 200L〜300L前後の中型モデルがおすすめ
→ 食材のストックや作り置きにも対応可能
加えて、設置場所との相性も非常に重要です。
-
扉の開く方向(右開き・左開き):壁やシンクとの干渉がないか確認を。
-
コンセントの位置:延長コードを使わなくても済むかをチェック。
-
高さと搬入経路:天井やドア枠との干渉、エレベーターのサイズなども事前に確認しましょう。
狭いキッチンやワンルームでは、冷蔵庫の上に電子レンジを置ける耐熱天板つきモデルを選ぶと省スペースになります。
冷蔵庫の機能と価格帯
最近の一人暮らし用冷蔵庫は、価格を抑えながらも便利な機能を搭載している機種が多数登場しています。主な注目ポイントはこちら。
-
冷凍室の広さ:まとめ買いや作り置きが多い人には必須
-
静音設計:寝室と同じ空間で使用する場合、動作音が30dB前後の静音モデルが快適
-
耐熱トップテーブル:電子レンジやトースターを置ける耐久設計は一人暮らしで重宝
-
省エネ性能:年間消費電力量をチェック。ランニングコストにも影響します。
価格帯は2万円〜5万円台がボリュームゾーンです。
目安として:
-
100〜150Lクラス → 約20,000〜35,000円
-
200〜300Lクラス → 約35,000〜55,000円
引越しシーズンや型落ち品はセール対象になることもあるので、タイミングを見て購入するのもおすすめです。
おすすめの冷蔵庫ブランド
初めての一人暮らしにおすすめの冷蔵庫ブランドを3つご紹介します。それぞれの特徴を理解して、自分の生活スタイルに合ったものを選びましょう。
-
シャープ(SHARP)
→ 国内メーカーの安心感。省エネ性能・収納性ともに優秀。コスパの良い2ドアモデルが人気。 -
ハイアール(Haier)
→ とにかく安く抑えたい方におすすめ。基本機能に特化しており、2万円前後で購入可能。シンプルな設計も◎。 -
無印良品
→ インテリアとの調和を重視したい人向け。デザイン性が高く、コンパクトながら静音性もあり。多少価格は上がりますが、長く使える品質です。
この他にもアイリスオーヤマやアクアなど、国内外で信頼のあるブランドが豊富なので、口コミやレビューを参考に比較して選ぶと安心です。
洗濯機を用意する理由
洗濯機の種類と選び方
一人暮らしにおいて洗濯機は「買うかどうか迷う家電」の一つですが、長期的に見ると自宅にある方が断然ラクで経済的です。洗濯の手間やコインランドリー代を考えると、早い段階での導入がおすすめです。
現在主流の洗濯機タイプは以下の2種類です。
-
縦型洗濯機(おすすめ)
→ 比較的安価でコンパクト。水流でしっかり汚れを落とせるため、汚れが気になる衣類に強い。一人暮らし用のスタンダードタイプ。 -
ドラム式洗濯機(上級者向け)
→ 節水性が高く、乾燥機能付きモデルが多いですが、サイズが大きく価格も高め。設置スペースや予算に余裕がある場合に向いています。
一人暮らしには「全自動の縦型洗濯機(5kg前後)」がコスパ・使い勝手ともに最適です。
サイズや容量の選定ポイント
一人暮らしの洗濯機選びで特に注意したいのは容量と設置可能サイズです。
-
容量の目安:
5kg前後が標準。一人分の1週間分の衣類やタオルをまとめて洗うのにちょうど良い容量です。
※2〜3日に1回洗う場合は4.5kgでも十分対応可。 -
洗濯パンのサイズ:
集合住宅では洗濯機を設置する防水パン(洗濯パン)のサイズが決まっているため、事前に内寸を測ることが必須です。 -
蛇口の位置と高さ:
機種によっては水道蛇口の高さが合わず、別売りの取り付け部品(延長ホースなど)が必要になる場合もあります。購入前に現地をチェックしておきましょう。
また、防音・防振マットを併用すると下階への騒音対策にもなり、アパート住まいでも安心です。
洗濯機の設置とコスト
洗濯機の設置は自分でできる場合もありますが、水漏れやホースの誤接続などのリスクがあるため、初めての場合は業者に任せるのが安心です。
-
本体価格の目安(5kg前後):
25,000円〜40,000円ほど。国内メーカーでシンプルなモデルならこの価格帯で購入可能です。 -
設置・取付費用の目安:
5,000円〜10,000円前後。量販店で購入すると、配送+設置サービスがセットになっていることが多く、追加費用なしで対応してもらえるケースもあります。 -
合計費用の目安:
約3万円〜5万円前後を見ておけば、安心して購入と設置が可能です。
ちなみに、引っ越し時には「階段作業料」や「ドア幅制限による吊り上げ作業」などの追加料金が発生する場合もあるため、事前確認をおすすめします。
電子レンジが必要な理由
電子レンジの機能を比較
一人暮らしにおける電子レンジは、調理の効率を上げるだけでなく、食生活の満足度にも大きく関わる家電です。特に料理をしない方にとっても、電子レンジは「必須家電」といっても過言ではありません。
主な機能タイプは以下の2つ。
-
単機能レンジ(温め専用)
→ 弁当・おかず・飲み物の温めに特化したシンプルなモデル。
→ 初期費用を抑えたい方、調理はしないという方におすすめ。
→ 一人暮らし用なら十分な機能。価格帯は6,000〜12,000円程度。 -
オーブン・グリル機能付きレンジ
→ パンの焼き直しやグラタン、冷凍ピザ、焼き料理なども対応可能。
→ 自炊に挑戦したい人や、オーブン調理を楽しみたい人向け。
→ 価格帯は15,000〜30,000円台。温度・ワット数調整も可能なモデルが多い。
生活スタイルに応じて、必要な機能を見極めて選びましょう。
便利な調理器具としての電子レンジ
最近では、「電子レンジ+レンジ専用調理器具」という組み合わせが一人暮らしに人気です。電子レンジさえあれば、火を使わずに1人分の食事が手軽に作れるのが魅力。
便利なレンジ調理器具の例:
-
パスタ調理器:水とパスタを入れてチンするだけでOK
-
蒸し野菜容器:ブロッコリーやじゃがいもを短時間で加熱
-
煮物対応タッパー:肉じゃがやおでん風のレシピも可能
-
卵調理器:ゆで卵・温泉卵が電子レンジで完成
これらは100均やニトリ、Amazonなどでも手に入ります。料理初心者でも失敗しにくく、洗い物も少ないため、時短と節約の両面で優秀な調理スタイルです。
おすすめの電子レンジモデル
一人暮らしで使いやすく、口コミ評価も高いコスパ重視のモデルをご紹介します。
■ アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
-
価格帯:6,000円〜15,000円台
-
シンプルな単機能タイプから、オーブン・グリル機能付きの多機能タイプまでラインナップ豊富。
-
操作が簡単で見た目もスッキリしており、初めての電子レンジとして最適。
-
「解凍モード」「出力切替」などの機能も十分。
■ パナソニック(Panasonic)
-
価格帯:15,000円〜30,000円台
-
加熱ムラが少なく、解凍性能やセンサー精度が高いのが特徴。
-
オーブン付きタイプでもコンパクト設計。自炊メインの方にはおすすめ。
-
スチームオーブンレンジも人気があり、調理の幅が広がる。
そのほかにも、シャープの「ヘルシオ」シリーズや東芝の「石窯ドーム」など、上位モデルを検討する余地もありますが、スペースや予算との相談が必要です。
自炊を助ける炊飯器の重要性
炊飯器の選び方と特徴
一人暮らしにおいて炊飯器は、自炊派はもちろん、時短・節約を意識する人にとって非常に重宝する家電です。外食やコンビニに頼らず、自宅でお米を炊けるだけで食費を大きく抑えられるという利点があります。
特におすすめなのは、3合炊きサイズの炊飯器。
理由は以下のとおり。
-
一度にまとめて炊いて冷凍保存できる
-
コンパクトでキッチンのスペースを圧迫しない
-
小容量でもふっくらと炊き上がる機種が多い
さらにタイマー機能が付いていると、夜寝る前にセットして朝に炊きたてご飯を食べる、といったライフスタイルが可能になります。忙しい朝にも食生活の質をキープできるのが魅力です。
炊飯器の利便性について
「炊飯器=白米専用」と思いがちですが、近年の炊飯器は多彩なモードを搭載しており、白米以外にも対応しています。
代表的な調理モード例
-
玄米モード:通常より時間はかかるが、ふっくら炊き上がる
-
おかゆモード:風邪気味のときや胃にやさしいメニューとして活用
-
炊き込みご飯モード:具材を入れるだけで手軽に一品料理に
-
雑穀米モード:健康志向の方に人気
これにより、毎日のお米メニューに変化が出せるため、飽きずに続けられるのもポイントです。特に自炊初心者にとっては、失敗が少なく作りやすいメニューが多いのも安心材料です。
多機能炊飯器のメリットとは
最近は「炊飯器=炊飯だけ」ではありません。煮込み料理やスイーツ調理にも対応した“多機能炊飯器”が、一人暮らし用にも数多く登場しています。
主なメリットはこちら
-
煮物・スープ・カレーも作れる:材料を入れてスイッチを押すだけ。放置で完成するので忙しい人にも◎
-
ケーキモード搭載機種:ホットケーキミックスを使った簡単ケーキなども可能
-
保温機能や再加熱機能も充実:食べたいときに温かく食べられるのが嬉しい
特に一口コンロしかないキッチンの場合、コンロが空かない・火加減が面倒…といったストレスを炊飯器が軽減してくれます。“小さな電気鍋”のような感覚で活用できるのが多機能炊飯器の魅力です。
部屋に必要な家具家電の配置
部屋の広さに合わせた配置
一人暮らしの部屋は、ワンルームや1Kで6〜8畳ほどが一般的。限られたスペースの中で快適に暮らすには、空間を有効に使う工夫が不可欠です。
特に意識したいのが以下の2点
-
縦の空間を活用すること
→ 壁面収納・突っ張りラック・ハンガーラックなど、床を使わず収納力を増やすアイテムを活用しましょう。
→ 上部スペースに家電を置けるラックやシェルフも人気です。 -
動線を意識した家具配置
→ 部屋の中をスムーズに歩けるように、ベッド・デスク・収納家具は壁側や角を基本に配置するのがポイント。
→ 家電の設置場所も、コンセントや導線との兼ね合いを考慮することが重要です。
家具と家電を「別々に選ぶ」のではなく、配置とサイズ感をトータルで考えることがスッキリした空間づくりの第一歩です。
インテリアと家電の統一感
見た目にこだわりたい方は、家具や家電の色味や素材感を揃えるだけで部屋全体の印象が大きく変わります。
特に人気の配色パターンは以下の通り
-
ホワイト系(明るく開放的)
→ ナチュラルで清潔感のある空間に。女性やミニマル志向の方に人気。 -
ブラック・ダークグレー系(落ち着いた印象)
→ 高級感・統一感が出やすく、男性にもおすすめ。 -
木目×白の組み合わせ(温もり+スッキリ感)
→ カフェ風や北欧インテリアにぴったり。どんな家電とも馴染みやすい。
家電は白物が多くなりがちですが、黒や木目調のモデルも増えているため、好みのインテリアに合ったものを選ぶと統一感が出ておしゃれな空間に仕上がります。
無駄のない収納家具の選び方
一人暮らしでは、「収納スペースが足りない問題」に悩まされる人が多数。そんな時に活躍するのが多機能家具や収納付きアイテムです。
おすすめの収納家具アイデア
-
収納付きベッド:引き出し式・リフトアップ式など、布団や衣類、季節家電を収納できて一石二鳥。
-
多機能ラック:上段に電子レンジ、下段に炊飯器やゴミ箱を置ける家電ラックが人気。キッチンまわりの整理に最適です。
-
キャスター付き収納ワゴン:小型家電やキッチン用品を乗せて移動できるため、掃除や模様替えもラク。
さらに、家電と家具を兼用できるアイテム(例:収納棚にトースターを置くなど)を活用すれば、スペースも機能も最大限に活かせます。
収納アイテムを選ぶ際は、「縦に収納する」「隙間に置く」「ベッド下を活用する」など、“余白の使い方”を意識すると無駄のない部屋づくりが実現します。
快適な生活を支える掃除機
掃除機の種類と特徴
一人暮らしの部屋でも、清潔感を保つために掃除機はあると便利な家電です。特に、髪の毛やホコリが目立ちやすいフローリングの部屋では、掃除機の存在が快適さに直結します。
以下に、主な掃除機の種類と特徴を紹介します。
■ スティック型掃除機
-
特徴:軽量・スリムで立て掛け収納が可能
-
メリット:サッと出してサッと使えるため、日々の掃除が面倒に感じにくい
-
おすすめの人:狭い部屋や収納スペースが少ない人に最適。ワンルーム住まいの定番。
■ ロボット掃除機
-
特徴:自動で部屋を掃除してくれるスマート家電
-
メリット:外出中や在宅ワーク中でも勝手に掃除してくれるため時短・手間削減に◎
-
注意点:床に物が多いと使用しづらい。段差やコードがある部屋にはやや不向き。
-
おすすめの人:片付けが得意な人、掃除が苦手な人、忙しい社会人など。
■ ハンディ型掃除機
-
特徴:コンパクトで持ち運びやすく、狭い場所の掃除に便利
-
メリット:机や棚、車の中、布団などピンポイントの掃除に活躍
-
おすすめの人:掃除頻度が少なめな人や、クイックルワイパーとの併用派。
それぞれの掃除スタイルや生活環境に合わせて、一台を選ぶのもよし、2台を使い分けるのもアリです。
掃除機はどのくらい必要か
掃除機が本当に必要かどうかは、部屋の広さ・床材・生活スタイルによって異なります。
-
フローリング中心の6畳部屋程度なら、クイックルワイパー+ハンディ掃除機でも対応可能。
-
ただし、髪の毛やホコリ、食べかすなどが気になる方や、アレルギー体質の方はしっかり吸引できる掃除機を備えておいた方が安心です。
特に以下のような人には掃除機の導入をおすすめします。
-
長い髪で抜け毛が気になる人
-
ペットを飼っている人
-
じゅうたんやラグを敷いている人
-
洗濯物のホコリが床にたまりやすい生活動線の人
「掃除が面倒」と感じる原因は、掃除機の出し入れの手間や収納のしづらさが大きいです。スティック型やコードレス型を選ぶことで、日々の掃除ストレスは大幅に軽減されます。
おすすめの掃除機ブランド
コスパと信頼性のバランスが取れた掃除機ブランドを3つ厳選してご紹介します。
■ ダイソン(Dyson)
-
吸引力に定評あり。コードレススティック型が主力。
-
吸引力が弱くならない構造で、髪の毛やペットの毛にも強い。
-
デザイン性も高く、インテリアに馴染む。
■ マキタ(Makita)
-
元は業務用電動工具メーカーで、小型・軽量で実用性重視の掃除機が人気。
-
バッテリー持ちが良く、ワンルームならこれ一台で十分な性能。
-
飲食店や事務所での利用実績も豊富で信頼性◎。
■ 日立・パナソニック(国内メーカー)
-
国内ブランドならではの細やかな設計。静音性や節電機能に優れている。
-
アパート・マンションなどの集合住宅に住む人にもおすすめ。
-
紙パック式やサイクロン式など、タイプが豊富。
照明器具の選び方と重要性
部屋の雰囲気を変える照明
照明は単なる「明かり」ではなく、部屋の雰囲気を左右する大切なインテリア要素でもあります。特に一人暮らしのワンルームでは、照明を工夫するだけで“ホテルライクな空間”や“温かみのある癒し空間”に変えることが可能です。
おすすめの照明活用アイデア
-
間接照明:壁や天井を柔らかく照らすことでリラックス効果アップ
-
デスクライト・ベッドライト:集中したい時や夜間の読書に最適。直接照らすことで目に優しい環境が作れます
-
スマートライト:スマホ連携で明るさや色を調整可能。自分好みの空間演出が簡単に
「ちょっと暗くて寂しい」「夜の部屋が味気ない」と感じたら、間接照明を一つ追加するだけで居心地が格段にアップします。
照明器具の種類と機能
一人暮らしに適した照明器具は大きく分けて以下のような種類があります。
■ シーリングライト(天井直付けタイプ)
-
部屋全体を明るく照らす主照明。
-
調光・調色機能付きのモデルも多く、昼は明るく、夜は暖かい光に変更できるタイプが人気。
-
リモコン付きならベッドからの操作も可能。
■ フロアライト(スタンド式)
-
インテリア性が高く、おしゃれな雰囲気やムードの演出に最適。
-
間接照明としても使え、テレビ視聴時や来客時に重宝します。
■ デスクライト・クリップライト
-
勉強・仕事・趣味に集中したい場所に設置。
-
コンパクトで場所を取らず、明るさ調整機能や目に優しい光を選べるモデルが人気。
■ その他:
-
足元灯・センサーライト:夜間のトイレ移動時に便利
-
LEDテープライト:ベッド下や棚裏に貼るだけで雰囲気が激変
一人暮らしでは「1つの照明で完結させる」のではなく、複数の照明を用途別に組み合わせるのが理想です。
コストパフォーマンスの良い照明
おしゃれで機能的な照明が欲しいけれど、あまりお金はかけたくない——そんな方にも安心なのが、低価格で高性能なアイテムが揃うブランドの活用です。
おすすめブランド・販売店例
-
ニトリ
→ シンプルで使いやすく、一人暮らし向けの照明が豊富。3,000円前後でLED・リモコン付モデルも入手可能。 -
アイリスオーヤマ
→ コスパと機能性のバランス◎。調光・調色可能なLEDシーリングライトが5,000円〜6,000円台で買える。 -
IKEA(イケア)
→ デザイン性重視ならおすすめ。北欧風のフロアライトやテーブルランプが多数。 -
Amazon・楽天市場
→ スマートライトやLEDテープライトなど、トレンド系の照明も手軽に揃えられる。
照明は「長く使う」アイテムだからこそ、初期費用を抑えつつも、自分の生活スタイルや好みに合ったものを選ぶことが大切です。
収納家具の重要性
部屋の収納スペースの計画
一人暮らしの部屋は、6〜8畳程度のワンルームや1Kが主流。収納スペースが限られていることが多く、「どう収納するか」より「どこに収納するか」が重要な課題になります。
そこで活用したいのが、次の2つの考え方です。
-
縦収納(高さを活かす)
→ 棚やラックを活用し、空いた壁面やクローゼットの上部まで有効活用
→ 家具の上やベッド下など、デッドスペースを見逃さない -
隠す収納(見せない収納)
→ 見た目をスッキリさせるには、収納ボックス・カーテン・扉付きの家具などを使って生活感を抑える工夫が有効
この2つの視点をベースに、収納計画を立てると、狭い部屋でも整った暮らしが実現できます。収納家具を選ぶ前に、持ち物の量や使用頻度を見直す断捨離も効果的です。
人気の収納アイテムを紹介
「見た目よし・使い勝手よし・コスパよし」の一人暮らしに最適な収納アイテムをご紹介します。
■ 無印良品のユニットシェルフ
-
サイズ展開が豊富で、キッチン・リビング・ベッドサイドなど場所を選ばず設置可能
-
パーツを追加してカスタマイズも自由自在。シンプルデザインで部屋になじむ
■ ニトリの組み合わせ収納ボックス
-
スタッキング可能でスペース効率◎。カラーや素材も豊富でインテリアと調和しやすい
-
クローゼットの中やベッド下に入れることで、見た目もスッキリ
■ IKEAの折りたたみ収納ケース
-
不使用時は折りたためるため、季節物やストック収納にぴったり
-
シンプルでおしゃれなデザインが多く、ラベルを付けて分類しやすい
これらのアイテムは、コスパと使い勝手を両立した収納家具の定番です。通販でも簡単に入手できるので、引越し後の買い足しにも便利。
DIYで作る収納方法
「収納家具にあまりお金をかけたくない」「自分の部屋にぴったり合うサイズがない」という場合には、100均グッズやホームセンター素材を使った“プチDIY収納”がおすすめです。
人気のDIY収納アイデア:
-
突っ張り棒+布で作る目隠しカーテン収納
-
ワイヤーネット×結束バンドで作る簡易ラックや小物掛け
-
木箱+キャスターで作るオリジナルワゴン
-
すのこDIYでスリムなシューズラックや本棚も作成可能
DIYは単なる節約術ではなく、自分の生活動線や部屋のテイストに合わせた収納スペースが作れるのが魅力です。また、SNSやYouTubeには初心者向けの動画も多く、初めてでも挑戦しやすいです。
まとめ|最低限の家電を揃えて快適な一人暮らしを始めよう
一人暮らしを始める際に、家電をすべて揃えようとすると予算もスペースも足りなくなりがちです。まずは「本当に必要なもの」からスタートし、自分の生活スタイルに合った家電を少しずつ揃えていくのが失敗しないコツです。
冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・炊飯器など、最低限の家電を揃えるだけでも快適な生活は十分可能です。この記事で紹介した内容を参考に、自分にとって必要な家電を見極め、無理のない一人暮らしを始めましょう。