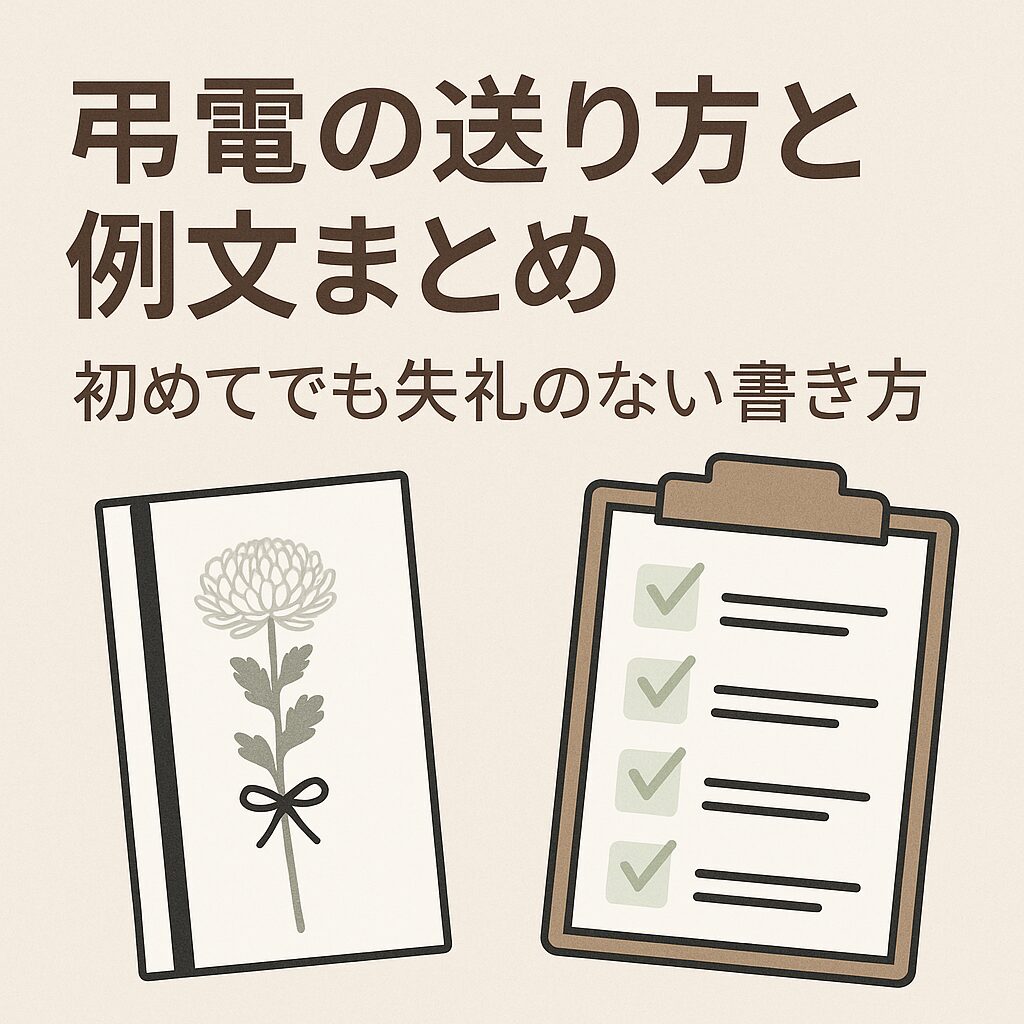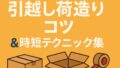訃報を受けたものの、葬儀に参列できない──そんなときに大切なのが「弔電」です。しかし、「何を書けばいい?」「送り方は?」「失礼がないか不安…」と戸惑う方も多いのではないでしょうか。
本記事では、初めての方でも安心して送れるように、弔電の送り方や文例をわかりやすく解説。形式だけでなく、心を込めた一文の作り方まで丁寧に紹介します。これさえ読めば、もう迷いません。大切な気持ちを、適切な形で届けましょう。
弔電の基本知識
弔電とは何か
弔電(ちょうでん)とは、身内や知人の訃報を受けた際に、直接葬儀に参列できない事情がある場合でも、哀悼の気持ちを遺族や故人に対して電報という形で伝える方法です。特に葬儀が急に行われるケースや、距離・仕事の都合などで駆けつけられない場合に活用されます。
また、弔電は単なる形式的な挨拶ではなく、「心を届ける手段」として、多くの人々が利用しており、公私を問わず重要なコミュニケーションの一つとされています。ビジネス上の関係者に対しても、会社や団体名義で送ることで、誠意を伝えることができるため、社会的な礼節としての役割も大きいです。
弔電の重要性
弔電の最大の意義は、直接顔を合わせてお悔やみを伝えられない状況でも、「想いをかたちにすること」ができる点です。遺族は葬儀の際、非常に多忙かつ精神的にも疲弊しているため、弔電によって丁寧な配慮を受け取ることで、少しでも心の支えになることがあります。
また、弔電を受け取った側にとっては、送った側の気遣いや心遣いが感じられるものです。特に会社の上司や取引先など、一定の関係性がある場合には、送らないことが逆に失礼と受け取られてしまう可能性もあるため、マナーとしても押さえておくべきポイントとなります。
弔電における敬称の使い方
弔電では、故人や遺族への敬意を欠かさないよう、適切な敬称を使うことが非常に重要です。たとえば、以下のような敬称の使い分けが一般的です。
-
故人が男性の父親であれば:「ご尊父様」
-
故人が母親であれば:「ご母堂様」
-
ご本人に直接宛てる場合は:「○○様 ご逝去」
-
遺族宛ての表現としては:「ご遺族の皆様へ」「喪主 ○○様へ」
また、「故○○様のご冥福をお祈りいたします」といったフレーズにおいても、「故」の使用や「様」の有無は文脈に合わせて丁寧に選びましょう。誤った敬称を使ってしまうと、かえって失礼な印象を与えることもあるため、正確な言葉遣いと敬意ある表現が求められます。
弔電の送り方
弔電の申込み方法
弔電は、NTTが提供する「D-MAIL」や「115番(電報申込み専用ダイヤル)」、郵便局のサービス、さらにはインターネット電報サービス(VERY CARD・e-denpo・ほっと電報など)から24時間いつでも申し込み可能です。
スマートフォンやパソコンから申し込めば、自宅や外出先からでもすぐに手配でき、急な訃報にも迅速に対応できます。また、インターネットサービスでは、デザイン台紙の選択やオリジナル文章の入力ができるなど、柔軟な対応が魅力です。
法人名義での送付にも対応しており、会社としての正式なメッセージとして活用される場面も少なくありません。申込時は、喪主名・故人名・葬儀会場の正確な情報を確認の上、入力ミスのないよう注意しましょう。
送り方のマナー
弔電を送る際には、配慮と正確さが何より大切です。以下のマナーを押さえておきましょう。
-
宛先は「葬儀会場名+喪主名(○○家 喪主 ○○様)」を明記
-
届けるタイミングは、通夜または葬儀の当日午前中までに到着するよう手配
-
誤字脱字や敬称の誤用は失礼にあたるため、何度も見直しを
また、遺族が読み上げたり保管したりすることもあるため、簡潔で丁寧な文章を心がけましょう。最近はデザイン台紙も豊富にあり、蓮や菊、落ち着いた和紙風など、宗教や雰囲気に配慮して選ぶのもマナーの一環です。
弔電のタイミング
訃報を受け取ったら、できる限りその日のうちに手配するのが理想です。遅くとも葬儀の前日までに申し込みを済ませ、式に間に合うように配達日を設定しましょう。
もしどうしても葬儀当日に間に合わない場合は、後日「お悔やみの手紙」や「香典」などで気持ちを伝える方法も選択肢となります。
なお、夜間や休日でもインターネットを使えば即時対応可能なため、時間帯を気にせず手配できるのは現代ならではの利便性です。スピードとマナーの両立が、遺族への誠意を表すことにつながります。
弔電の文例集
弔電の文面は、形式を重んじると同時に、送る相手との関係性や状況に応じた気遣いある表現が求められます。ここでは、汎用的に使える定型文から、オリジナル要素を加えたメッセージ、親しい友人向けの文例まで幅広くご紹介します。
一般的な弔電の文例
誰にでも失礼なく使える、フォーマルかつ簡潔な表現です。ビジネス関係者や会社名義で送る際にも最適です。
ご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。
ご冥福をお祈りするとともに、心よりご遺族の皆様にお見舞い申し上げます。
補足ポイント:
-
決まり文句として用いられるため、失敗が少なく安心です。
-
故人の名前や具体的な関係性はあえて書かず、汎用性を保つ構成です。
オリジナルメッセージの作成例
故人との思い出や感謝の気持ちを織り交ぜたい場合にふさわしい文例です。やや長めでも問題ありませんが、簡潔さと丁寧さのバランスを大切にしましょう。
○○様には公私にわたり大変お世話になり、心から感謝しております。
ご冥福をお祈りするとともに、ご遺族の皆様のご健康をお祈り申し上げます。
補足ポイント:
-
故人に対する個人的な感謝の気持ちを表現できます。
-
遺族への配慮を文末に添えることで、全体の印象が柔らかくなります。
-
「公私にわたり」「感謝しております」などの語句が、格式を保ちながらも温かみを演出します。
友人への弔電の文例
親しい友人や同級生など、比較的カジュアルな関係性で送る際の例です。直接的な感情表現も許容される範囲ですが、節度を忘れずに。
○○さんの訃報に接し、驚きと悲しみでいっぱいです。
学生時代からの思い出は今も大切な宝物です。心よりご冥福をお祈りいたします。
補足ポイント:
-
「驚きと悲しみでいっぱい」など、感情を率直に伝えることが可能です。
-
故人との具体的な関係(例:学生時代の思い出)に言及することで、心のこもった内容に仕上がります。
-
ただし長文になりすぎず、読みやすい文量に留めることが大切です。
弔電の内容について
弔電は短い文章の中に「敬意・哀悼・配慮」を込める必要があるため、言葉選びが非常に重要です。ここでは、代表的なお悔やみ表現から、心を込めた文章にするためのポイント、さらに避けるべき忌み言葉や重ね言葉について詳しく解説します。
お悔やみの表現方法
弔電では、遺族の心情に配慮し、控えめかつ丁寧な表現が求められます。たとえば以下のような表現が広く用いられています。
- 「ご冥福をお祈りいたします」
- 「心よりお悔やみ申し上げます」
- 「安らかにお眠りください」
- 「突然のことで言葉もございません」
これらはいずれも直接的な死を連想させない言い回しであり、弔辞や弔電で長年使われてきた定型的な文言です。
一方で、「亡くなられて悲しいです」「死んでしまって残念です」など、あまりに直接的・感情的すぎる表現は避けるのがマナー。哀しみの感情を伝える場合も、あくまで格式と節度を意識した言葉を選びましょう。
故人への心を込めたメッセージ
心のこもった弔電には、故人との思い出や感謝の気持ちを一文添えるのが効果的です。たとえば、
○○様には常に優しいお言葉をかけていただき、今でもその温かさが忘れられません。
これまでのご厚情に深く感謝し、ご冥福を心よりお祈りいたします。
こうした個人的なエピソードを盛り込むことで、定型文だけでは伝わりにくい「あなたらしさ」や「真心」が伝わります。
ただし注意点として、
- 長くなりすぎない(3〜5行以内が目安)
- 遺族が読んでも負担にならないよう配慮する
- 他の参列者と差がつきすぎるような表現は避ける
といった点に気をつけましょう。
重ね言葉と忌み言葉の注意点
日本では古くから、縁起の悪い言葉や繰り返しを連想させる表現を「忌み言葉」「重ね言葉」として避ける習慣があります。弔電でもこれらの使用は控えましょう。
代表的なNG表現とその理由:
| 表現 | 理由 | 推奨される言い換え例 |
|---|---|---|
| 死ぬ・死亡 | 直接的で生々しい | ご逝去/お亡くなりになる |
| 繰り返し・たびたび・ますます | 不幸が重なることを連想 | 使用を避ける |
| 生きていたころは | 生死を強調しすぎる | ご生前は/ご厚情に感謝申し上げます |
| 最後に会ったのは~ | 終わりを強調しやすい | ご在世中にお会いできたことが~ |
言葉の選び方ひとつで、受け取る側の印象が大きく変わります。特にビジネス関係など距離のある関係性では、言葉のプロトコル(儀礼性)を重視した文章構成が大切です。
弔電の種類
弔電は一律に見えて、実際には送る相手や状況によって適した文面や形式が異なります。ここでは、よく使われる定型文の特徴、個性を出せるカスタマイズ例、そして送るシーンごとのポイントを詳しく解説します。
弔電の定型文
NTT(D-MAIL)やe-denpo、VERY CARDなどのサービスでは、目的別にあらかじめ用意された定型文を選ぶことができます。主な特徴は以下の通りです。
-
短く整った敬語表現で失礼がない
-
内容の選択肢が多く、宗教・関係性別に分かれている
-
会社名や団体名での送付にも適している
たとえば、以下のような一文が用意されています。
ご逝去の報に接し、深い哀悼の意を表します。ご遺族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
このような文例は、多忙な中でも迅速に手配でき、無難で安心感があるため、ビジネス関係者や上司宛てなど、あまり親しくない相手にもふさわしい形式です。
カスタマイズ可能な文例
最近では、自由に文章を入力できるカスタマイズ型の弔電サービスも増えています。これは、故人との思い出や感謝の気持ちを込めたオリジナルメッセージを送りたい方におすすめです。
カスタマイズの際に注意すべきポイントは以下の通りです。
-
文字数制限がある(一般的に250~400文字程度)
-
句読点の使用や改行が制限される場合がある
-
内容は必ず確認・校正すること(誤字や忌み言葉に注意)
また、台紙の種類によっては、文章の雰囲気に合った装飾やデザイン(和紙調・蓮の花・菊・モノトーンなど)を選ぶことで、メッセージの印象をより丁寧に伝えることができます。
シーン別の弔電
弔電を送る際は、相手との関係性に応じて文面を使い分けることがマナーです。以下に、代表的なシーンごとの文面傾向と注意点を紹介します。
● 上司のご家族が亡くなった場合
ご母堂様のご逝去を悼み、心より哀悼の意を表します。ご遺族の皆様のご心痛をお察し申し上げます。
-
敬語を丁寧に使い、私的な感情は控えめに
-
「様」や「ご尊父様」「ご母堂様」など適切な敬称を使用
● 友人宛の弔電
○○さんの突然の訃報に接し、悲しみを禁じ得ません。安らかにお眠りください。
-
思い出や感情を込めた表現が可能
-
くだけすぎず、一定の節度は保つ
● 恩師・教育関係者宛て
○○先生のご逝去の報に接し、深い悲しみを覚えております。ご教示いただいた日々に感謝し、ご冥福をお祈り申し上げます。
-
敬意と感謝を込めた表現が望ましい
-
「先生」という敬称を使用するのが一般的
POINT:選び方に迷ったら?
・公的な相手には定型文+堅めの表現
・個人的なつながりにはカスタマイズ+思い出を一文添える
・迷った場合は、失礼のない定型文を選ぶのが無難
このように、弔電の種類は多様化しており、形式に縛られすぎず、気持ちを丁寧に伝えることが大切です。
弔電の配達と料金
弔電は「気持ちを届ける手段」であると同時に、「正確なタイミングで届くこと」がとても重要です。特に葬儀・通夜の場で読み上げられる可能性があるため、配達方法や申し込み時間には十分な注意が必要です。ここでは、配達手段や代表的なサービス、費用相場について詳しく解説します。
配達方法の選択肢
弔電にはいくつかの配達手段がありますが、即日配達が基本とされています。主な配達オプションは以下の通りです。
- NTTの電報(D-MAIL/115):最短当日中の配達が可能。午前中に申し込めば当日午前〜午後に届くケースが多い。
- 民間の電報サービス(VERY CARD、e-denpoなど):ネット専用で、最短即日または翌日配達が可能。
- 郵便局の「郵便電報」:翌日配達が基本。土日・祝日は配達不可の場合もあり。
【重要なポイント】
- 弔電は通夜または葬儀が行われる当日の午前中までに届けるのが理想です。
- 遅れてしまうと式中に読み上げてもらえなかったり、遺族に直接渡されない可能性があります。
- 早めの手配(訃報を受けた当日中)が基本マナーとされます。
NTTの弔電サービス
NTTが提供する「D-MAIL(でぃーめーる)」は、最も利用者が多い弔電サービスのひとつです。注文は以下の方法で対応しています。
- インターネットから(D-MAIL公式サイト)
- 電話から(115)※固定電話・携帯どちらも可
NTTのサービスの特徴:
- 全国どこへでも即日配達が可能(※地域・時間帯による)
- 約200種類以上の台紙から選べる(弔電専用デザインも豊富)
- 定型文と自由文の両方に対応
- 法人名義や複数同時申し込みも可能
※Web申込みの場合、24時間365日受付対応なので、深夜や早朝でも手配できるのがメリットです。
料金の相場について
弔電の料金は、主に以下の3つの要素で決まります。
| 項目 | 概要 | 価格帯の目安 |
|---|---|---|
| 基本料金 | 電報の送信料 | 約660円〜(文字数・地域により変動) |
| 台紙料金 | デザイン・素材により変動 | 約300円〜5,000円以上(高級台紙) |
| 文字数追加料金 | 規定文字数(例:25文字)を超えた場合 | 1文字あたり5〜10円程度追加の場合あり |
例:スタンダード弔電(NTT)
- 基本料金:約660円
- 台紙(弔電用和紙):550円
- 100文字メッセージ:+150円程度
→ 合計:約1,300〜1,500円ほどが一般的な価格帯です。
高級弔電の例(木製装丁・花柄デザイン台紙など)
→ 合計3,000円〜5,000円超のケースもあります。
お得に利用するには?
- Web注文限定の割引あり(NTT・VERY CARDなど)
- 定型文使用+簡素な台紙にすると費用を抑えられる
- 楽天やAmazonなどでポイント連携可能なサービスも存在
弔電は、「タイミング」「文面」「形式」の三要素を整えて初めて、真心が伝わるものになります。料金の安さだけにとらわれず、相手との関係性や式の規模感に合わせた台紙・内容を選ぶことが大切です。
葬儀と弔電の関係
弔電は単なる形式ではなく、葬儀の中で重要な役割を果たします。特に参列できない人にとっては、弔意を伝えるための唯一の方法になることも。ここでは、弔電が葬儀の中でどのように扱われるか、送るべき状況、送付先の注意点について詳しく解説します。
葬儀での弔電の役割
弔電は、通夜や葬儀・告別式の際に、司会者が代表的なものを読み上げる場合があります。一般的には、喪主や遺族があらかじめ選んだ数通が会場で紹介され、それ以外の弔電は以下のように扱われます。
- 会場内に設置された弔電台紙掲示スペースに展示される(参列者も閲覧可能)
- 式終了後、まとめて遺族に手渡される(会葬礼状とともに)
- 遺族が後日読み返し、心の支えとして保管されるケースも多い
特に読み上げられる可能性がある場合は、句読点を控えた読みやすい文構成や、宗教的配慮(例:「ご冥福」ではなく「安らかに」など)が重要になります。
参列できない場合の弔電
遠方在住・急な仕事・体調不良など、物理的・時間的な事情で葬儀への参列が難しい場合、弔電は最低限のマナーとして非常に有効です。
送る側としては、「出席できなかったことに対するお詫び」+「哀悼の意」を伝えることで、礼を尽くした印象を持ってもらえます。
また、さらに丁寧な対応としては、
- 弔電に手書きの一筆箋や「お悔やみの手紙」を添える
- 数日後に改めて、お供え物や香典を郵送する
といった配慮が遺族の心に届くでしょう。特に親しい間柄であった場合は、形式的な電報だけでなく、手紙の温かみを添えるのが理想的です。
葬儀場への弔電送付
弔電を送る際の宛先は、以下の点に注意しましょう。
【送り先の基本構成】
〒〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇葬儀会館 気付
〇〇家 喪主 〇〇 様
(または ご遺族一同 様)
- 「〇〇家 喪主 〇〇様」と明記することで、遺族側にスムーズに届けられます
- 「〇〇葬儀会館 気付」を入れることで、式場スタッフが対応してくれるようになります
- 喪主の名前がわからない場合は、「〇〇家 ご遺族様」と記載しても失礼にはなりません
【送付前の確認ポイント】
- 葬儀会場が「自宅」なのか「葬儀場」なのかを確認すること
- 葬儀の日程・時間帯を把握し、必ず当日午前中までに到着するよう手配
- 式場に弔電受付の有無を電話で確認しておくと安心
弔電は、ただ「送ること」だけでなく、「正確に、心を込めて、遺族のもとに届ける」ことが最も大切です。葬儀という限られた時間の中で、想いをきちんと届けるためにも、宛先・時間・文面の3点を丁寧に準備しましょう。
弔電のアレンジ
弔電はシンプルな形式でも十分に弔意を伝えることができますが、工夫を加えることでより心のこもった印象を遺族に届けることができます。ここでは、供花との組み合わせや台紙の選び方、文章のアレンジ方法など、弔電をより丁寧に演出するための工夫をご紹介します。
供花との兼ね合い
弔電に加えて供花(きょうか)を一緒に送ることで、より厚意の伝わる弔意の表現になります。特に親族や親しい関係であった場合は、弔電だけでなく供花を添えるのが礼儀とされることもあります。
供花と弔電を併せて送る際の注意点:
-
葬儀場が供花の受け入れに対応しているか事前確認が必須
-
宗派によっては供花の種類や色に制限がある
-
例えば仏教では白を基調とした花が一般的ですが、キリスト教式ではユリやカーネーションなど、色味のある花も選ばれます。
また、供花と弔電を同時に手配できるサービス(NTTや民間電報会社)もあり、セットで申し込むとスムーズです。
台紙やデザインの選び方
弔電の印象を大きく左右するのが、台紙のデザインです。特に故人の人柄や年齢、遺族との関係性を考慮した台紙選びは、心遣いとして高く評価されることがあります。
よく選ばれる弔電用台紙の例:
-
和紙風の落ち着いたデザイン(蓮の花・菊・白木蓮など)
-
黒やグレーを基調としたシンプルなもの(フォーマル・ビジネス向け)
-
木製台紙や布貼りの高級仕様(格式ある式や親族向け)
故人が明るく上品な方だった場合は、白や藤色を基調とした優しいデザインを選ぶなど、台紙で「想い」を表現することも可能です。
【TIPS】
「価格の高い台紙=良い」ではありません。故人やご遺族の好みに配慮し、過剰にならず、控えめで品のあるものを選ぶことが大切です。
表現を豊かにするアレンジ
定型的な弔意表現に加えて、格式と情感を高める工夫として、下記のようなアレンジを盛り込むのもおすすめです。
● 漢詩・和歌・俳句の引用
「千の風になって 君を包む」
「花は散る されど思いは 風のごとし」
など、故人を讃えたり、静かな哀しみを表す表現が選ばれます。
※ただし、文語調・比喩的な表現は受け手が誤解しないよう注意が必要です。
● 宗教的な聖句や祈りの言葉(キリスト教・仏教など)
-
キリスト教:
主のもとに召された〇〇様の永遠の平安をお祈り申し上げます。
-
仏教:
安らかなる御仏の御許にて、おやすみください。
● 故人への称賛や感謝を一文添える
○○様のお人柄と笑顔は、今も私たちの心に生き続けています。
多くの教えと励ましをいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。
このように、個人的な想いをさりげなく盛り込むことで、画一的な弔電から一歩抜け出た、印象深いメッセージに仕上がります。
弔電はあくまで「形式を守りつつ、心を届ける」もの。アレンジしすぎて奇抜になるのは逆効果ですが、節度ある中で表現を豊かにする工夫は、遺族の心に温かく残る贈り物となるでしょう。
弔電に関するよくある質問
弔電を送るべきかどうか、どんな内容が失礼にあたるのか…。葬儀の場面では、誰もが少なからず迷いや不安を感じるものです。ここでは、弔電を送る際によくある疑問とその対処法を、Q&A形式でわかりやすくまとめました。
Q. 弔電を送るべきか迷った時の対応は?
A. 故人やご遺族との関係の深さを軸に判断しましょう。
-
故人と個人的なつながりがあり、なおかつ葬儀に参列できない場合は、弔電を送るのが基本的なマナーとされます。
-
ビジネス上の付き合いがあった場合や、以前お世話になった恩人など、直接の親族でなくても弔電を送るのは失礼にはあたりません。
-
一方で、あまり深いつながりがなかった場合や、遺族が家族葬・密葬を希望している旨が伝えられている場合は配慮が必要です。
その場合は、無理に弔電を送らず、後日落ち着いたタイミングでお悔やみの手紙や電話、供物など別の方法で思いを伝える選択もあります。
Q. トラブルを避けるための注意点は?
A. 以下の3つは最低限チェックしておくべきマナーです。
① 宛名・住所の誤記に注意
→ 喪主の名前を間違えたり、葬儀場の名称や所在地を誤ると、弔電が届かない・受け取ってもらえない可能性があります。申し込み前に必ず葬儀案内状や関係者に確認を。
② 忌み言葉・重ね言葉の使用を避ける
→ 「死ぬ」「ますます」「たびたび」「繰り返し」など、弔事にふさわしくない表現は避け、丁寧な言い換え(例:「ご逝去」「ご冥福」)を使いましょう。
③ 感情のままの表現は控える
→ 弔電は「共感を伝える」より「礼節を示す」ことが第一目的。
「信じられません!」「とてもショックです」など強すぎる感情表現は避け、穏やかで格式ある文章を心がけましょう。
Q. 親戚や知人への対応に違いはある?
A. 関係性の濃淡に応じて、柔軟に対応しましょう。
● 親戚であっても、直接喪主や故人と付き合いが薄い場合
→ 無理に弔電を送るよりも、「お悔やみの手紙」や「後日の香典」が適しているケースもあります。
● 知人で関係が深かった場合(例:学生時代の恩人、旧友など)
→ 弔電に一文だけ思い出や感謝の言葉を添えると好印象です。たとえば:
「○○様には在学中、大変お世話になりました。心より感謝申し上げ、ご冥福をお祈りいたします。」
このように、定型文に個人的な背景を少し加えることで、格式を保ちつつ温かみも伝えることができます。
弔電はマナーと気遣いのバランスが大切です。相手の立場や状況を思いやりながら、「失礼のない丁寧なかたちで、気持ちを届ける」ことを最優先に考えましょう。
まとめ|弔電で真心を届ける準備を始めましょう
弔電は、直接会えない状況でも哀悼の気持ちを丁寧に伝える大切な手段です。本記事では、弔電の送り方やマナー、例文まで幅広くご紹介しました。形式的なものと思われがちですが、故人や遺族への配慮が表れる心のこもったメッセージは、必ず相手の心に届きます。
いざという時に慌てないよう、正しい知識と文例を今のうちに確認し、弔電で思いをきちんと伝える準備を整えておきましょう。