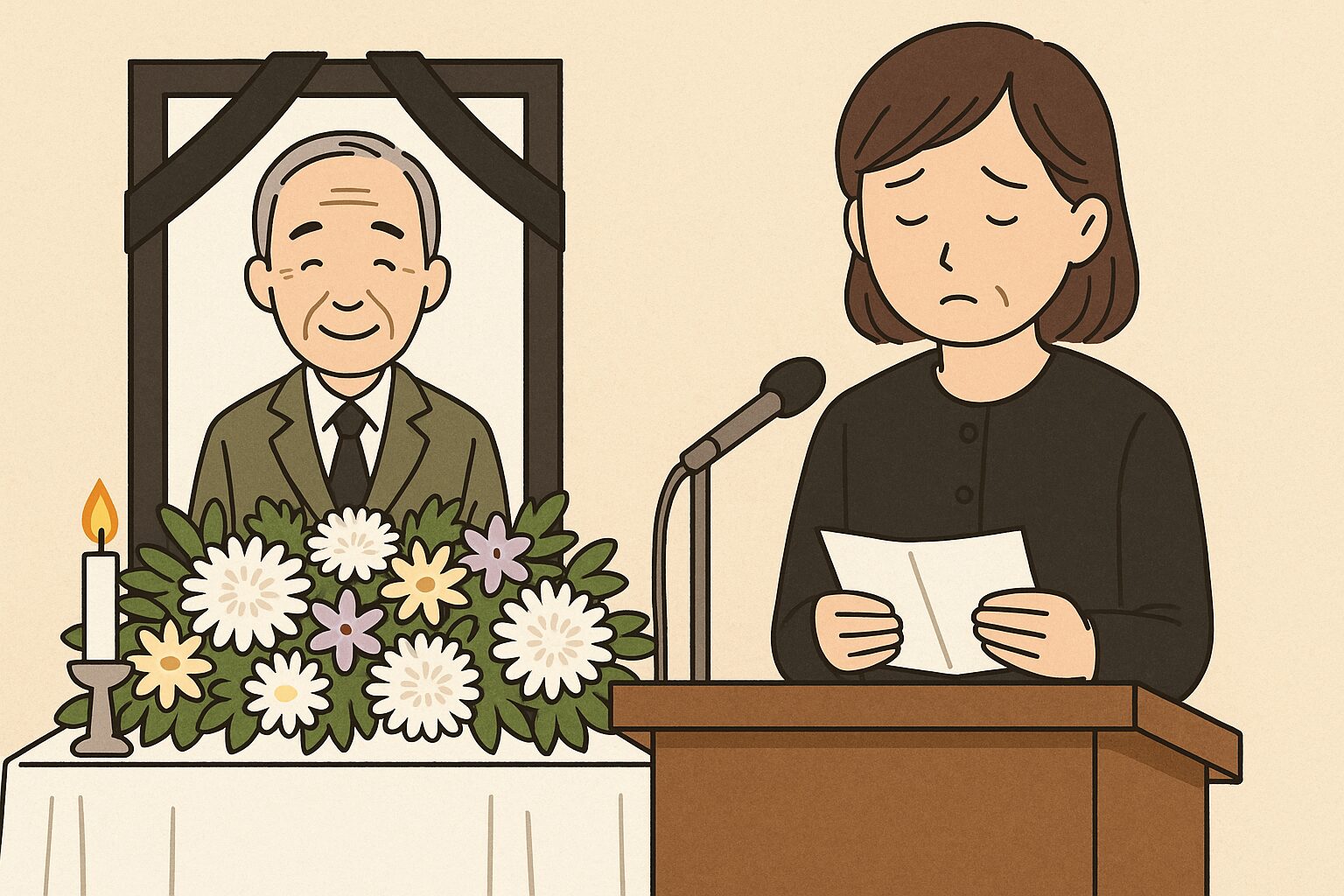身近な人を見送るとき、避けて通れないのが喪主としての挨拶。私も親族の通夜で喪主を務めることになったとき、「何を話せばいいのか」「失礼にならないか」と胸がいっぱいになりました。特に小さな子どもを育てながら準備を進めるのは心身ともに大変です。でも、通夜の挨拶に求められているのは長い言葉ではなく、短くても心のこもった一言。
この記事では、喪主の挨拶に迷う方へ、実際の文例や準備のコツをまとめました。家庭の雰囲気を交えながらご紹介します。
通夜で喪主が挨拶する意味

通夜での喪主挨拶は、ただ形式的に言葉を述べるだけではなく、「故人に代わって参列者に心からの感謝を伝える」という大切な役割を持っています。
参列者は、それぞれの都合を調整して故人を見送るために足を運んでくださっています。その思いに対して、喪主が一言でも感謝を伝えることで、会場全体が「共に故人を偲ぶ空気」にまとまるのだと感じました。
また、挨拶の場は喪主にとっても「悲しみを抱えつつ気持ちを整える時間」になります。深い悲しみの中で言葉を紡ぐのは簡単ではありませんが、その時間があることで、少しずつ現実を受け入れるきっかけにもなりました。形式にとらわれるのではなく、心を込めて「ありがとう」を届けることこそが、通夜での喪主挨拶の本当の意味だと私は思います。
家族を代表しての感謝
私が喪主を務めたとき、まだ子どもたちが小さく、通夜の場の雰囲気も十分に理解していない様子でした。けれども、参列者の方が子どもに優しく声をかけてくださったり、そっと見守ってくださったりする光景を見て、家族としての支えを強く感じました。
挨拶のときは、「子どもたちや家族をここまで温かく見守ってくださった方々への感謝」を、何よりも優先して伝えるようにしました。形式的な決まり文句よりも、目の前の参列者へ自分の気持ちを素直に言葉にすることが、一番心に響くのだと実感しました。
振り返ってみても、立派な言葉を並べる必要はなく、「遠方から来てくださってありがとうございます」「皆さまに支えられて母も安心して旅立てたと思います」といった短い一言で十分でした。むしろ、そのシンプルな感謝の言葉の方が、私自身の気持ちを落ち着かせてくれたのです。
通夜の挨拶の基本構成

通夜での喪主挨拶は、長いスピーチを求められているわけではありません。一般的には2〜3分程度に収めるのが理想的とされています。実際に私も、あらかじめ時間を意識して練習しておいたことで、緊張していても落ち着いて話すことができました。
流れとしてはとてもシンプルで、「冒頭の挨拶 → 参列へのお礼 → 故人について一言 → 締めの言葉」という4つのステップを意識すれば十分です。
-
冒頭の挨拶
まずは「本日はお忙しい中、父○○の通夜にお集まりいただきありがとうございます」と、場を始める一言を述べます。 -
参列へのお礼
遠方から駆けつけてくださった方や、日常の忙しさの中で時間を割いてくださった方に対し、感謝の気持ちを伝える場です。 -
故人について一言
故人の人柄や思い出を簡単に添えると、場に温かさが生まれます。「母はいつも笑顔で家族を支えてくれました」など、一言で大丈夫です。 -
締めの言葉
「簡単ではございますが、心より御礼申し上げます」とまとめ、深く一礼して締めくくります。
このように、型を知っておけば、自分の気持ちを乗せて話す余裕も生まれます。
短くても失礼にならない
初めて喪主を務めたとき、私は「短すぎると参列者に失礼ではないか」と心配していました。しかし実際には、むしろ簡潔であることが参列者への思いやりにつながります。通夜は多くの方にとって仕事や家事の合間を縫っての参列であり、心身ともに疲れやすい時間帯でもあります。
だからこそ、長い挨拶よりも「要点を押さえた短い言葉」の方が相手にとって心地よく受け取られるのです。私自身も参列者から「気持ちがよく伝わってきたよ」と声をかけてもらい、安心したのを覚えています。
つまり、通夜での挨拶において大切なのは長さではなく、感謝の気持ちを相手にまっすぐ届けること。それだけで、十分に心は伝わるのだと思います。
実際に使える挨拶文例

通夜での喪主挨拶は、どんなに準備していても当日は緊張して言葉が飛んでしまうことがあります。私自身も「頭が真っ白になったらどうしよう」と不安でした。そこで、あらかじめいくつかの文例を用意し、自分の言葉に置き換えながら練習しておくと安心です。ここでは、場面に応じて使いやすいシンプルな文例を紹介します。
一般的な文例
「本日はご多用の中、亡き父○○の通夜にお集まりいただき、誠にありがとうございます。故人も皆さまに見送られ、安らかに旅立てることと思います。簡単ではございますが、生前のご厚誼に深く感謝申し上げます。」
こちらは、最もオーソドックスで幅広く使える挨拶文例です。ポイントは「参列への感謝」と「故人が皆に見送られている安心感」を伝えること。具体的に人柄に触れていなくても、十分に気持ちは伝わります。
実際にこの文例を使った親族の挨拶では、参列者から「しっかりとした言葉で安心した」と言われました。無理にアレンジを加えず、基本の形を押さえるだけで十分です。
家族を意識した文例
「本日はお忙しい中、母○○のためにお集まりいただき、本当にありがとうございます。子どもたちも祖母を偲びながら、この場で皆さまに支えられていると感じています。どうぞ今後とも家族を見守っていただければ幸いです。」
この文例は、子どもや家族の存在を意識した形。特に小さな子どもがいる場合、参列者は「これから大丈夫かな」と心配してくださることもあります。そんな気持ちに寄り添うように「今後とも家族を見守っていただければ」という言葉を添えることで、会場に温かな雰囲気が生まれます。
私も母を亡くしたとき、この文例に近い形で話しました。涙がこみあげて声が震えましたが、正直な気持ちを短く言葉にするだけで、周りの方々に支えられている安心感が広がったのを覚えています。
短くまとめる文例
「本日はお集まりいただきありがとうございます。心より感謝申し上げます。」
どうしても言葉が出てこないとき、あるいは参列者が多くて時間をかけられないときに使えるシンプルな文例です。短いながらも「お集まりいただいたこと」への感謝を伝えており、失礼にはなりません。
実際に、体調がすぐれなかった親族がこの挨拶を使いましたが、それでも参列者から「お気持ちは伝わりましたよ」と声をかけてもらっていました。挨拶は長さではなく、心が込められているかどうかが大切だと実感できる一例です。
文例を使うときの工夫
これらの文例はそのまま使っても問題ありませんが、自分の気持ちや状況を一言添えると、より心に響きます。たとえば「遠方からお越しいただき、ありがとうございます」と加えるだけでも、参列者は「自分のことを思ってくれている」と感じやすくなります。
また、声の大きさや話す速度にも注意が必要です。焦って早口になるよりも、一文ごとに区切ってゆっくり話す方が、落ち着きや誠実さが伝わります。
挨拶のときに意識したいこと

通夜での喪主挨拶は、あらかじめ用意した文例を読むだけでも十分に役割を果たせます。ただし、そこにほんの少し自分の心を添えるだけで、参列者に与える印象はぐっと変わります。私自身も、最初は「暗記した言葉をそのまま読めばいい」と思っていましたが、実際にやってみると、自分の気持ちを一言足すだけで、場の空気がやわらぎ、参列者の表情も変わったのを覚えています。
感謝の気持ちを込める
どんな状況でも外せないのは「足を運んでくださった方への感謝」です。通夜は平日の夜に行われることも多く、仕事帰りに駆けつけてくださる方、遠方から時間をかけて来てくださる方もいます。その労をねぎらう一言があるだけで、参列者は「来てよかった」と思ってくださいます。
例えば、
-
「お忙しい中をお越しいただき、心から感謝申し上げます」
-
「お寒い中、足を運んでいただき本当にありがとうございます」
といった具体的な表現にすると、より自然に気持ちが伝わります。たとえ声が震えても、「ありがとう」の一言さえあれば十分に誠意は伝わるのです。
故人を思い出す一言を添える
もう一つ、できれば入れておきたいのが故人の人柄を感じさせる一言です。長いエピソードを語る必要はなく、ほんの一文でも十分です。
例えば、
-
「母はいつも笑顔で、家族を明るくしてくれる存在でした」
-
「父は寡黙でしたが、影で私たちを支えてくれる人でした」
こうした短い一言があるだけで、参列者は自然と故人の姿を思い出し、会場に温かい空気が流れます。特に故人と親しくなかった参列者にとっても、「ああ、そんな人だったのだな」と心に残るきっかけになります。
自分の言葉で添える勇気
大切なのは、完璧に話そうとしないことです。途中で涙が出て言葉が詰まってしまっても、それはむしろ自然なこと。参列者も気持ちを理解してくれるので安心して大丈夫です。私も挨拶の途中で声が震えてしまいましたが、後から「気持ちが伝わったよ」と声をかけてもらい、救われました。
つまり、通夜の喪主挨拶では、「感謝」と「故人を偲ぶ一言」を心を込めて伝えることができれば、それ以上の飾りは必要ないのです。
家族で準備しておくと安心

喪主の挨拶は「自分一人で完璧にしなければならない」と思い込むと、必要以上にプレッシャーを感じてしまいます。ですが実際には、家族で協力しながら準備しておくことで心の負担がぐっと軽くなるのです。挨拶は形式ではなく気持ちが大切だからこそ、家族の支えを受けながら一緒に考えることが大切だと実感しました。
子どもとの関わり
我が家の場合、子どもたちはまだ小さかったため、通夜の意味や挨拶の重みまでは理解できませんでした。それでも「パパがみんなにお話するんだね」と、少し誇らしげに見守ってくれていた姿が印象的でした。子どもにとっても、大人が真剣に誰かを見送る姿を間近で感じることは大切な経験になります。
また、子どもがいると式の最中にぐずったり落ち着かなかったりすることもあります。そんなときのために、他の家族と「誰が子どもを見るか」をあらかじめ話し合っておくと安心です。喪主が挨拶に集中できる環境を作るのも、家族の大切な役割だと感じました。
メモを用意する
通夜の挨拶では、感情があふれて言葉が詰まることも珍しくありません。私も実際に、途中で声が震えて読めなくなりそうになりました。そのときに助けになったのが、手元に用意していたメモです。
メモは長い原稿である必要はなく、
-
参列へのお礼
-
故人についての一言
-
締めの言葉
といった要点を短く書いておくだけで十分です。小さなカードにまとめてポケットに入れておくだけでも安心感が違います。「万が一、言葉を忘れても大丈夫」という心の支えになるのです。
家族での事前確認
さらに安心できるのは、家族の前で一度声に出して練習しておくことです。妻や兄弟に聞いてもらい「もう少し短くしてもいいかも」「その言葉は分かりやすいね」とアドバイスをもらうだけで、本番への自信につながります。
私は家族と共有していたことで、当日の緊張も少し和らぎましたし、「みんなで作った言葉だから大丈夫」と思えたことが大きな支えになりました。
まとめ|短い挨拶でも心は伝わる
通夜の喪主挨拶は、長さや形式にとらわれる必要はありません。大切なのは「参列してくださった方への感謝」と「故人を偲ぶ気持ち」。私は、子育てに追われる日常の中で準備するのも大変でしたが、短くても心を込めた言葉なら十分だと実感しました。もし挨拶に迷ったら、まずは感謝の一言から始めてみてください。あなたの気持ちはきっと伝わります。