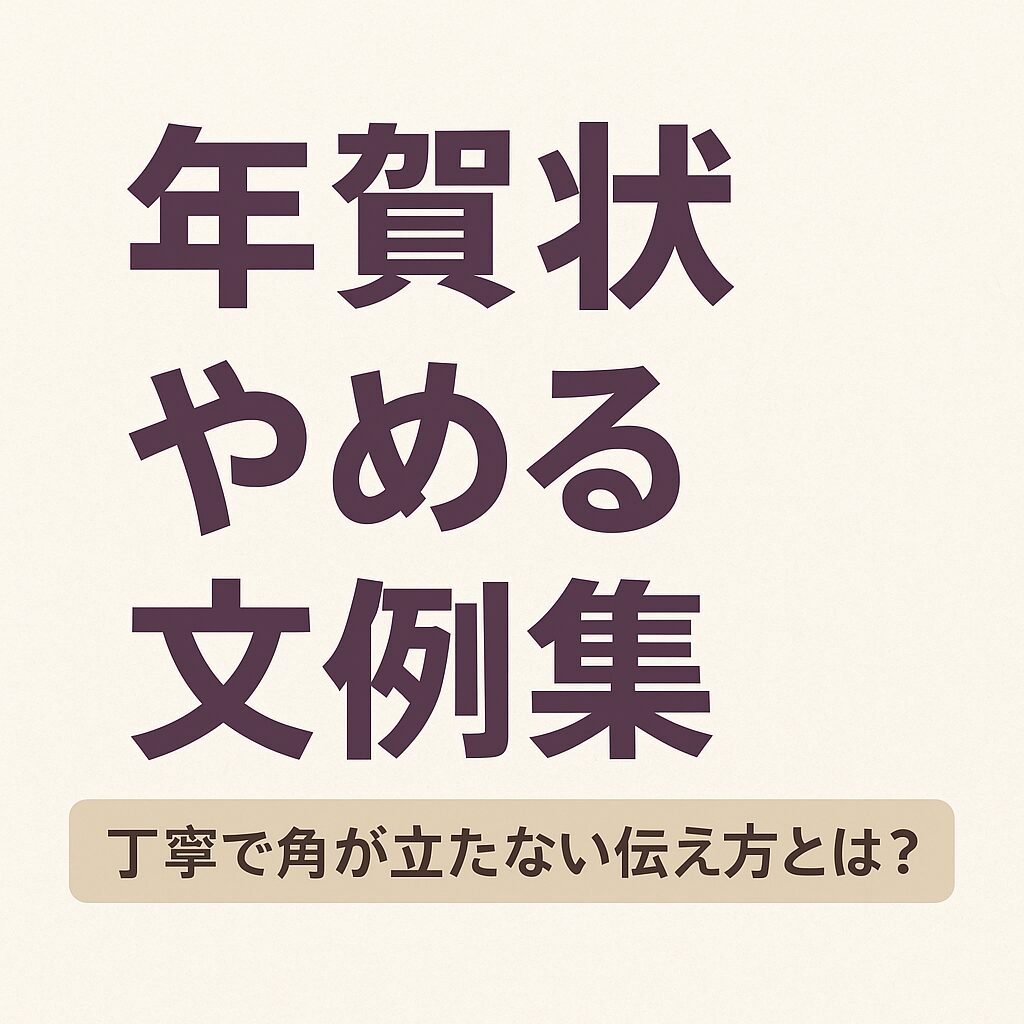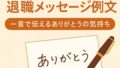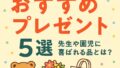年賀状をやめたいけど「失礼にならないか心配」「どう伝えたらいいのか分からない」と悩んでいませんか?
この記事では、年賀状をやめる際に使える丁寧で角が立たない文例を、個人・法人・世代別に多数ご紹介します。
LINEや寒中見舞い、SNSなどの代替手段や注意点もあわせて解説しているので、2025年から年賀状を卒業したい方は必見です。
年賀状をやめる理由
年賀状をやめることのメリット
年賀状のやりとりをやめることで、精神的にも時間的にもゆとりが生まれるのが最大のメリットです。年末の多忙な時期に印刷会社への発注、宛名書き、メッセージ記入などの作業をこなすのは大きな負担になります。とくに年末に仕事や家庭の行事が立て込む方にとっては、年賀状の準備がプレッシャーになることも。
また、コスト面でも見逃せません。印刷代や郵便代に加え、年々上がる素材費も無視できず、1回あたり数千円から一万円以上かかるケースも。これらをカットできるのは、家計にも優しい選択です。
さらに、最近はスマートフォンやSNSの普及により、「年賀状はもう出していない」「LINEで済ませている」といった声も多く聞かれるようになりました。価値観や交流スタイルの変化が、年賀状を見直すきっかけとなっているのです。
年賀状をやめるデメリット
その一方で、年賀状をやめることで思わぬデメリットもあります。
まず考えられるのは、関係性の希薄化への懸念です。たとえば毎年年賀状だけのやりとりをしていた友人や恩師とのつながりが、年賀状をやめたことで自然消滅してしまうケースもあります。
特に年配の方の中には、年賀状に「礼節」や「けじめ」を重視する方も少なくありません。「突然年賀状が来なくなって驚いた」「もう付き合いたくないのかと思った」といった受け止め方をされる可能性もあります。
また、ビジネスや地域のつながりの場面では、年賀状が“年始の第一印象”として機能することもあります。やめるにあたっては、代替手段を考えたり、文面に配慮したりといった準備が必要になります。
年賀状をやめるタイミング
年賀状をやめる際には、「どう伝えるか」と同じくらい「いつ伝えるか」も重要です。
最もスムーズなのは、最後の年賀状の中で宣言する方法です。
たとえば、
「今年をもちまして年賀状でのご挨拶を控えさせていただくことといたしました。」
と添えれば、自然で丁寧な印象を与えられます。忙しい年末でも、この一言を加えるだけで受け取る側の印象は大きく変わります。
もう一つの方法は、年賀状を出し終えた後に寒中見舞いで伝えるスタイルです。寒中見舞いは1月7日以降〜2月初旬までが一般的な時期で、「ご挨拶が遅くなってしまった」体で書くと角が立ちません。
いずれにしても、突然の中止ではなく、あくまで“区切り”として伝えることが信頼維持の鍵になります。
年賀状じまいの方法
年賀状をやめる際の連絡方法
年賀状をやめる際には、「突然出さない」よりも、相手に丁寧に知らせることが円滑な人間関係の鍵になります。以下のような方法が一般的です。
-
年賀状に「これを最後に」と明記する
最も自然でスマートな方法です。年賀状の末尾に一言添えるだけで、丁寧に意図が伝わります。
例:「本年をもちまして、年賀状でのご挨拶は控えさせていただきます。」 -
寒中見舞いやLINEで個別に連絡する
特に親しい友人や親戚には、個別に事情を伝えると誠意が伝わりやすいです。寒中見舞いで改めて丁寧に説明すれば、受け取る側も納得しやすくなります。 -
定型文+一言メッセージで丁寧な印象を残す
事務的な印象にならないよう、あえて手書きで一文加えたり、自分らしい言葉で結ぶなど、「あなたにだけ伝えたい」という心遣いが感じられると好印象です。
✅ポイント:
「やめること」よりも、「これからも良い関係を大切にしたい」という想いを添えることが大切です。
年賀状をやめるお知らせ文例
実際にどのような文面で伝えれば角が立たないのか、悩む方も多いはずです。以下の文例は、フォーマルさと温かみのバランスを意識した構成です。
【年賀状に記載する場合の例文】
本年をもちまして、年賀状でのご挨拶を控えさせていただくことといたしました。
これまでのご厚情に心より感謝申し上げますとともに、今後も変わらぬご交誼を賜れますようお願い申し上げます。
【寒中見舞いやLINEで伝える場合の例文】
ご無沙汰しております。体調などお変わりありませんか?
私事ですが、今年から年賀状でのご挨拶は控えさせていただくことにいたしました。
これからは、別の形でご挨拶できれば幸いです。
文面はあくまで「通知」ではなく、「思いやりのあるご報告」として伝えるのがポイントです。
年賀状廃止の考え方
「年賀状じまい」という言葉が定着しつつある現代ですが、それは単なる習慣の放棄ではありません。むしろ、新しい人間関係の築き方への移行とも言えます。
年賀状をやめる際に大切なのは、相手との関係性を軽視しているわけではないことを伝える姿勢です。
たとえば、
-
体調や年齢的な負担を理由にしたり
-
デジタル化への移行を背景にしたり
といった形で「納得感のある理由」を添えつつ、「感謝」と「今後もよろしく」の気持ちをしっかり伝えることが求められます。
「年賀状じまい」は、単に年賀状をやめることではなく、相手との関係を見直すきっかけにもなる行動です。だからこそ、失礼のない伝え方を選ぶことが、信頼関係の維持・深化につながります。
年賀状をやめる世代別考察
40代の年賀状辞退
子育て・仕事に追われる40代は、「年末の作業を減らしたい」という理由から年賀状を見直す動きが特に顕著です。
保育園や学校関連の行事、仕事納め前の繁忙期、年末年始の帰省準備など、年賀状にかける余力が物理的に足りないという現実的な理由が背景にあります。
さらに、LINE・Instagram・FacebookなどのSNSで日常的に近況報告ができる今、あえて年賀状で改まった挨拶をする必要性を感じないという価値観も広がっています。
実際、「今年からLINEでご挨拶させていただきます」と伝えることで、逆にフランクで気軽な関係性が築けるケースも増えています。
✅ポイント
40代は「合理性」と「ライフスタイルの変化」によって年賀状の習慣を見直しやすい世代。
ただし、職場や親世代とのやりとりでは、やめる際のマナーがより重要になります。
50代と60代の年賀状見直し
50代・60代は、「年賀状文化」への愛着と「世代交代の波」の間で揺れやすい世代です。
子どもの独立や退職・転職を機に、「人付き合いを整理したい」「年賀状のやりとりが形式的になってきた」と感じている方も少なくありません。
とはいえ、これまで何十年も年賀状で関係を築いてきた相手が多いため、完全にやめるのは躊躇されがち。
そのため「親しい方にだけ続ける」「寒中見舞いに切り替える」「今年限りのご挨拶と明記する」など、段階的な“やめ方”を選ぶ人が多いのが特徴です。
✅ポイント
形式にとらわれない柔軟な選択肢が好まれる世代。
「感謝+やめる宣言」のバランスが非常に重要です。
70代・80代の年賀状やめる傾向
高齢になると、体調や体力の問題から年賀状作業が難しくなるという声が増えてきます。筆を取るのが億劫になったり、印刷や郵送の手続きが負担になったりするケースも少なくありません。
また、親しい友人や知人との別れが増える中、「年賀状に気持ちを込めるのがつらくなってきた」という心情的な理由も背景にあります。
この世代では、「これを最後に」と書き添えることで年賀状を終了するケースが多く、受け取る側もその事情を察し、自然な形での“年賀状卒業”が受け入れられている傾向にあります。
✅ポイント
70代以降は“年賀状じまい”がより自然な選択として受け止められやすい。
ただし、長年の礼節を重んじる世代だけに、誠実で温かみのある伝え方が必須です。
世代によって「やめ方」や「受け止め方」に違いがあるため、自分の立場や相手の世代に応じた伝え方を工夫することが大切です。
年賀状の代替手段
メールやLINEでの新年挨拶
年賀状をやめたあとも、「新年のご挨拶」は続けたいという方におすすめなのが、メールやLINEなどのデジタル手段です。
これらのツールの魅力は、何と言っても手軽さと即時性。年始のあいさつとして、1月1日にサッと一言を送るだけで、気持ちはしっかり伝わります。
また、堅苦しい言葉ではなく、親しみのあるカジュアルなトーンが使えるため、友人や同僚とのコミュニケーションにも適しています。
たとえばこんな短文でもOKです。
「明けましておめでとうございます!今年もよろしくお願いします♪」
「お互い健康第一で、良い一年にしましょうね!」
さらに、家族写真や初詣の風景を添付すると、視覚的な温かみも加わり、年賀状以上に“今”を感じられる挨拶になります。
✅おすすめの使い分け:
メール:仕事関係やフォーマルな関係に
LINE:友人や親戚など親しい間柄に
寒中見舞いとその利点
寒中見舞いとは、松の内(1月7日)を過ぎたあとから立春(2月初旬)までの間に出す挨拶状です。
本来は「寒さが厳しい時期に相手を気遣うための手紙」ですが、現代では以下のようなシーンでも活用されています。
-
年賀状を出しそびれたときの代替手段
-
年賀状をやめたことのお知らせとお詫びを伝える場面
-
喪中の相手への配慮として新年の挨拶を控えるとき
たとえば以下のような文面が一般的です。
「寒中お見舞い申し上げます。
本年より年賀状でのご挨拶は控えさせていただくことにいたしました。
今後とも変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。」
寒中見舞いは、はがきでの丁寧な対応が可能なため、ご年配の方やフォーマルな関係にも適しています。
SNSを利用した新年の挨拶
SNS(Instagram・Facebook・X など)を活用した新年のあいさつは、「一度に多くの人へ挨拶できる」現代的な手段として支持されています。
例えば、以下のような投稿が人気です。
-
「明けましておめでとうございます!今年もよろしくお願いします!」のコメントとともに、家族写真や初日の出の画像を投稿すると、気軽で温かみのある挨拶になります。
また、年末年始の過ごし方を綴る投稿に近況を添えるスタイルも人気です。たとえば「今年は○○に出かけてきました」や「家でゆっくり過ごしました」といった内容に、感謝や希望のメッセージを加えると、自然なかたちで新年のご挨拶ができます。
SNSの強みは、視覚とストーリー性で人とのつながりを感じやすい点にあります。特に遠方の知人や同級生など、年賀状ではやりとりしなくなった相手にも広く挨拶が届くのが魅力です。
また、ストーリーズ機能などを活用すれば、気軽かつ温かみのある挨拶が可能に。フォロワーとの距離感を保ちながら、「つながっている実感」が得られます。
✅注意点:
プライベートを公開したくない場合は、限定公開やメッセージ機能を使う
ビジネス関係ではSNSだけで済ませるのは避け、別途フォローを忘れずに
このように、年賀状に代わる挨拶方法には多彩な選択肢があります。相手との関係性や、自分のライフスタイルに合った手段を選ぶことが、無理のない“新しい挨拶スタイル”を築く鍵です。
年賀状をやめる際の注意点
失礼にならないためのポイント
年賀状をやめる際にもっとも気をつけたいのは、「こちらの都合で勝手に関係を断とうとしている」と受け取られないようにすることです。特に長年年賀状のやりとりを続けてきた相手や目上の方に対しては、礼儀を重んじる姿勢が非常に重要です。
以下の3つのポイントを押さえると、相手に不快感を与えず、思いやりのある伝え方になります。
-
「感謝」と「ご挨拶」の気持ちは必ず添える
→「これまでのご厚意に感謝申し上げます」といった一文を添えるだけで、丁寧さが伝わります。 -
やめる理由を簡潔かつ柔らかく伝える
→「年齢的にも体力的にも負担が大きくなってきたため」「生活環境が変わったため」など、自分側の事情として表現すると、角が立ちません。 -
一方的に「やめます」と言わない
→「今後は別の形でご挨拶できれば嬉しいです」など、つながりを続けたい気持ちを添えると安心感につながります。
✅例文(年賀状に添える一文):
「本年をもちまして年賀状でのご挨拶は控えさせていただきますが、今後も変わらぬご交誼を賜れますようお願い申し上げます。」
相手の理解を得る工夫
年賀状をやめる理由がどれだけ正当であっても、それをどう伝えるかによって相手の受け止め方は大きく変わります。
そのためには、以下のような“配慮の一文”を添えるのがおすすめです。
-
「今後はメールやLINEでご挨拶させていただければ幸いです」
-
「これからも別の形で近況をお届けできたらと思っています」
-
「節目のご挨拶は今後も続けてまいりたいと考えております」
こうした表現は、「やめる」のではなく「形を変える」という印象を与えるため、相手に安心感を与える効果があります。
また、相手との関係性に応じて、デジタルでのつながり(SNS・メールなど)の案内を具体的に伝えるのも一つの方法です。
年賀状を辞退する際の言葉選び
言葉の選び方ひとつで、伝わる印象は大きく変わります。
例えば「もう出しません」といった断定的な表現よりも、やわらかく、心のこもった言い回しを使うことが好ましいです。
以下のような表現がよく使われます。
-
「年齢的にも体力的にも負担が大きくなってまいりました」
-
「生活スタイルの変化に伴い、年賀状を控えさせていただくことにいたしました」
-
「大変勝手ではございますが、本年をもちましてご挨拶は控えさせていただきたく存じます」
これらの表現は、「やめたい」という意思を表すと同時に、相手に敬意を示す言い方として非常に有効です。
✅ワンポイントアドバイス:
自分の状況や理由を少し添えるだけで、「理解されやすさ」が格段にアップします。
感情よりも事情を伝えるほうが、スムーズに受け入れてもらえる傾向があります。
年賀状をやめた後の人間関係
今後の付き合い方の考察
年賀状をやめる決断をしたとき、多くの人が「これで縁が切れてしまうのでは」と不安になります。
しかし、実際には年賀状をやめた=関係を断つというわけではありません。
たとえば、
-
普段から連絡を取り合っている友人や親戚とは、LINEや電話で自然に交流が続く
-
毎年年賀状だけの関係だった相手にも、別の機会に一言添えることで、関係をリセットするのではなく“更新”することが可能
むしろ、年賀状に頼らず、本当に大切な人とどうつながっていくかを見直すきっかけになるという考え方もできます。
✅補足:
「年に一度の義務的なやりとり」から、「必要な時に心からのやりとり」へ。
無理のない関係性が、より良い距離感を生むこともあります。
年賀状廃止によるコミュニケーションの変化
年賀状をやめると、交流が一切なくなるわけではなく、より柔軟でリアルなコミュニケーションスタイルへと移行する人が増えています。
たとえば、
-
メールやSNSで「今年もよろしくね!」とメッセージを送る
-
誕生日や記念日など、よりパーソナルなタイミングで連絡を取る
-
久々に近況を伝えたい相手には、寒中見舞いやLINEであいさつを送る
こうした形は、「年賀状よりも自分らしい」と感じる人も多く、定型文ではなく気持ちを込めたコミュニケーションへと変わってきている証拠です。
また、SNSでは「一斉に多くの人へ近況を共有」できるため、一方通行ではない双方向のやり取りが増える傾向にあります。
✅ポイント:
「一斉送信」から「個別のやりとり」へ。
年賀状を卒業することで、より“必要な人とつながる”方向にシフトできます。
友人・親戚との関係性の維持
家族や親戚、長年の友人とのつながりは、年賀状がなくても維持できます。
むしろ、年賀状だけの形式的なやりとりから、もっと実感のある関係へと深化することも。
たとえば、
-
季節ごとの写真や近況報告をLINEで共有
-
誕生日に手書きのメッセージカードを送る
-
「最近どうしてる?」と気軽に電話をかけてみる
こうしたコミュニケーションは、年賀状の一通よりもずっと距離を縮める効果があります。
また、ご年配の親戚に対しては、寒中見舞いや暑中見舞いなどを使って、「年賀状をやめたけど思っているよ」というメッセージを伝えることができます。
✅アドバイス:
年賀状に代わる“あなたらしいつながり方”を見つけましょう。
大切なのは、形式ではなく「伝える気持ち」です。
このように、年賀状をやめたあとも人間関係はしっかり保てます。むしろ、関係を再定義し、より柔らかく・より心地よくつながるきっかけにもなるのです。
法人における年賀状の存続
ビジネスシーンでの年賀状の位置付け
企業間の年始の挨拶として、年賀状は長らく「名刺交換の延長線」「年始のご挨拶の定番」とされてきました。
年賀状には、取引先への感謝と今後の良好な関係を願う気持ちが込められており、形式とはいえ無視できない文化のひとつです。
しかし近年では、次のような理由から年賀状の廃止を選ぶ企業が増えています。
-
ペーパーレス化・DX推進など、社内の業務効率化・コスト削減の一環
-
SDGsや環境配慮の観点から、紙やインク、輸送の削減を目的とした動き
-
コロナ禍以降の「非接触型あいさつ文化」の広がり
-
SNSやメールを使った、より迅速で双方向なコミュニケーションへの移行
一部の企業では、Web年賀状や公式サイトでの年始メッセージ掲載など、デジタルを活用した代替施策も進んでいます。
✅注目トレンド:
メール年賀状:画像付きのHTMLメールでの一斉配信
LINE公式アカウントでの配信
自社Webサイトのトップに掲載する「新年のご挨拶」
法人としての年賀状廃止の文例
法人が年賀状を廃止する際には、理由と配慮を明確にした文面が求められます。
ここでは、汎用性が高く、印象も穏やかなフォーマットをご紹介します。
【法人用・年賀状廃止のお知らせ文例(年限を含まない汎用版)】
拝啓 年末ご多忙の折、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、弊社では昨今の環境配慮およびデジタル化推進の観点から、今後、年賀状によるご挨拶を控えさせていただくことといたしました。
誠に勝手ではございますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げますとともに、今後とも変わらぬご厚誼のほどお願い申し上げます。
敬具
このように、形式を重視しながらも誠実な姿勢を伝える構成が理想です。
一方で、より親しい取引先には、担当者個人名でのメール送付など、個別対応を検討しても良いでしょう。
取引先への年賀状廃止の知らせ
年賀状の廃止は、形式的に見える一方で、「相手に対する礼を失さない配慮」が特に重要です。
取引先に対しては、以下のような要素をしっかり押さえた伝え方が求められます。
-
感謝の意:「これまでのご厚情に感謝申し上げます」などの一文を必ず添える
-
今後の関係性に言及:「今後とも変わらぬお引き立てをお願い申し上げます」と結ぶ
-
廃止の理由を明記:「業務効率化」や「環境配慮」など、社会的背景に基づいた理由が望ましい
-
新しい挨拶方法の提案:「メールやWebサイト上でのご挨拶に移行する」などの補足があると丁寧
場合によっては、秋頃〜年末にかけての定例文書(お歳暮のご案内など)に同封するのもスムーズな方法です。
✅ビジネス視点の一言メモ:
「年賀状をやめたことで冷たい印象になるのでは?」と懸念する声もありますが、誠実な案内を添えれば、逆に“先進的で合理的”な印象につながることも。
企業の文化や業種により対応はさまざまですが、年賀状廃止を検討する際は、“一律ではなく相手ごとに対応を工夫する”姿勢が信頼維持のカギです。
年賀状をやめる際の文面のコツ
一言で伝える文例の作成
「できるだけシンプルに、でも失礼のないように伝えたい」
そんなときに便利なのが、一文で意向を表す丁寧な定型文です。
【定番の一言文例】
今後は年賀状でのご挨拶を控えさせていただきたく、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
この一文は、年賀状の末尾に加えるだけで十分な丁寧さを保ちつつ、やめる意思を明確に伝えることができます。
特にビジネス関係や形式を重んじる相手にも安心して使える、万能なフレーズです。
✅活用シーン:
印刷された年賀状の一文として
メールや寒中見舞いの末尾に添える形で
相手に配慮した文面
年賀状をやめる理由を少し添えると、より相手に寄り添った印象になります。
特に親戚や古くからの友人、年配の方などには、こうした「背景のある言い回し」が有効です。
【やわらかい配慮型の文例】
長年のご厚情に心より感謝申し上げます。
年齢的な事情もあり、来年より年賀状でのご挨拶は控えさせていただくことにいたしました。
「年齢的に」「体力的に」というワードは、“個人的な事情”として伝わりやすく、相手に「責められている印象を与えない」配慮ある表現です。
また、「これまでのご厚情に感謝」と前置きを入れることで、突然やめることへの違和感を和らげる効果があります。
✅バリエーション例:
生活環境の変化により〜
デジタルでのご挨拶へ移行したく〜
近年の負担を考慮し〜 など、理由は柔らかくカスタマイズ可能
年賀状廃止を伝える印象良い文面
感謝の気持ちを伝えつつ、「関係は続けたい」と伝える文面は、年賀状じまいの理想的なスタイルです。
やめる意思をはっきり伝えつつ、相手とのつながりを大切にする姿勢が感じられる文例をご紹介します。
【印象の良い定番文例】
これまでのご縁に感謝しつつ、今後は別の形でご挨拶をさせていただきたく存じます。
この文例は、控えめながらも前向きな気持ちと今後の関係継続への意欲を示せる表現です。
「別の形で」と曖昧にしておくことで、LINEやメール、寒中見舞い、SNSなど、今後の柔軟な挨拶手段にも対応できます。
✅組み合わせ例(よりフォーマルに)
本年をもちまして年賀状によるご挨拶は控えさせていただきますが、これまでのご縁に感謝しつつ、今後は別の形でご挨拶させていただきたく存じます。
年賀状に代わる新しい挨拶のカタチ
新年の挨拶を楽しむ方法
年賀状をやめたからといって、新年のご挨拶をやめる必要はありません。むしろ今は、もっと自由で楽しいスタイルで挨拶を楽しむ人が増えています。以下のような工夫を取り入れることで、気持ちがより深く伝わり、相手との距離も縮まります。
-
写真付きのLINEメッセージ
おせちや初詣、家族写真など「いまの自分」を伝える写真は、文章以上に温かさが伝わるツールです。カジュアルながらも「わざわざ写真を送ってくれた」という行為そのものに、親しみが生まれます。 -
ボイスメッセージで声を届ける
声には表情や温度があり、感情がダイレクトに伝わるという魅力があります。特に高齢の親族や親しい友人には、文字よりも心に残る挨拶になります。 -
Zoomやビデオ通話で「年始のご挨拶会」
最近は、家族や親しい友人とビデオ通話を通じて「オンラインお正月会」を開く方も増加中。離れていても顔を見ながら挨拶できる時代になったからこそ、新しい形のつながり方として人気を集めています。
✅ワンポイント:
自分が楽しんで発信することで、相手も自然に笑顔になれます。形式ではなく、「気持ち」と「距離感」を大切にした方法が、これからの挨拶スタイルの主流です。
自分スタイルの挨拶文例
自分らしい言葉での年始の挨拶は、定型文以上に相手の心に響きます。以下のようなシンプルかつ温かい一言を添えるだけでも十分です。
【カジュアルな一言例】
今年もどうぞよろしくお願いします!<br>お互い健康第一で、楽しい一年にしましょう♪
【写真と合わせて使える例】
初日の出見に行ってきました!今年も元気に頑張りましょう〜!
【ボイス・動画用ナチュラルメッセージ例】
「明けましておめでとうございます!今年も笑顔いっぱいの一年になりますように!」
このように、自分の言葉で少しだけアレンジすることで、「義務感」ではなく「つながりたい」という気持ちが伝わります。
✅ポイント:
一言で十分。大切なのは“完璧さ”より“あなたらしさ”です。
今後の挨拶を考える
年賀状が当たり前だった時代から、今は形式に縛られない“想いの伝え方”を選べる時代へと移行しています。
-
「あの人とはLINEでつながっているから写真を送ろう」
-
「この人には寒中見舞いで丁寧に伝えたい」
-
「SNSで一斉に近況をシェアして、気軽に挨拶しよう」
そんなふうに、相手に合わせた“挨拶の最適化”ができる時代です。
年賀状をやめたことで、改めて「どんなふうに相手とつながっていたいか」を考える機会にもなります。新年のご挨拶は、「つながりを更新するチャンス」と前向きに捉えましょう。
✅まとめのメッセージ:
年賀状がなくても、つながる手段はいくらでもあります。
大切なのは、形よりも“気持ちが届く方法”を見つけることです。
まとめ|年賀状をやめるなら今が伝えどきです
年賀状をやめることは、生活スタイルの変化や人付き合いの見直しとしてごく自然な流れです。大切なのは、相手への配慮を忘れずに、丁寧な文面で気持ちを伝えること。
今回ご紹介した文例や注意点を参考に、自分らしい形で“年賀状じまい”を実践してみましょう。新たな挨拶のスタイルへと移行することで、より心地よい人間関係が築けるはずです。