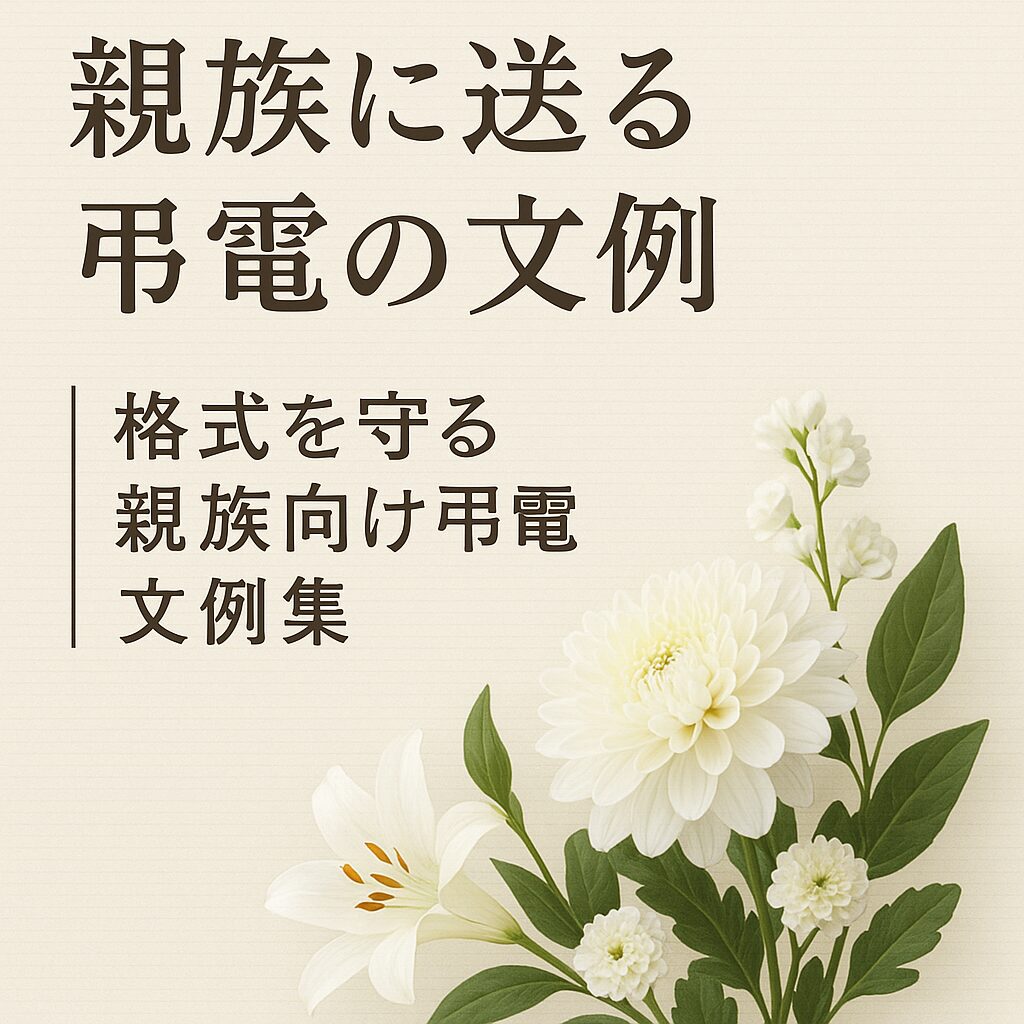親族のお葬式に参列できないとき、弔電を送ろうと思っても「親族にはどんな文章がいいの?」と悩みますよね。私も祖母のお葬式で弔電を頼まれたとき、いざ文面を考え始めると頭が真っ白になりました。親族だからこそ、きちんとした言葉を選びたいもの。
この記事では、実際に私が送った文例や、格式を守った表現をわかりやすくまとめました。これさえ読めば、いざというときにも慌てず対応できますよ。
親族への弔電はどんな場面で必要?
親族への弔電は、葬儀や告別式に参列できないときに送ります。
私も以前、子どもが熱を出してしまい、どうしても祖母のお葬式に行けなかったことがありました。
そのときは、母に「弔電だけでも送ってくれたら助かるわ」と言われ、慌てて文面を考えたのを覚えています。
正直なところ、それまで弔電なんて会社関係でしか送ったことがなくて、「親族に送る必要あるのかな?」と思っていました。
家族として気持ちは伝わっているけれど
身内だからこそ、「気持ちは伝わってるはず」と思いがちですよね。
私も当時、母にそう言われなければ送っていなかったかもしれません。
でも、喪主を務める親族からすると、弔電が届くことで「ちゃんと気にかけてくれているんだな」と感じられるものです。
実際に、伯父から届いた弔電を母が読んだときも、「ありがたいね」と涙ぐんでいました。
私はその光景を見て、弔電ってただの形式じゃなくて、ちゃんと心を届けられるものなんだな…と感じたんです。
参列できないときは必ず送る?
絶対に送らないといけないわけではありませんが、親しい親族であれば送った方が良いと私は思います。
特に喪主や遺族にとっては、弔電が届くことで気持ちが救われることもあるようです。
以前、友人のお母様が亡くなったときも、私自身は参列できず、迷った末に弔電を送りました。
後日、「忙しいのにありがとう。家族みんな喜んでたよ」と連絡が来て、送って良かったなと思いました。
この経験からも、親族であれ友人であれ、参列できないときには弔電で気持ちを伝えることが大切だと実感しています。
親族に送る弔電の文例【祖父母の場合】
ここでは、私が実際に祖母のお葬式に送った弔電の文例や、祖父への文例を紹介します。
祖父母への弔電は、両親とはまた違い、人生の長い時間を家族として寄り添ってくれたことへの感謝を込めると良いと感じています。
祖母への弔電文例
「祖母○○様のご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。
小さい頃からいつも優しく見守ってくださったお姿が目に浮かび、悲しみでいっぱいです。
本日は参列できず申し訳ありません。
遠くよりご冥福をお祈り申し上げます。」
私は、この文面にしました。
当時、息子がまだ1歳で高熱を出してしまい、どうしても参列できなかったんです。
母から「おばあちゃんはあなたのことを本当にかわいがってくれてたから、弔電だけでも送ってあげて」と言われて、泣きながらこの文章を考えました。
最後に「申し訳ありません」と一言添えることで、どうしても行けなかった無念さと、祖母への想いが伝わる気がして、この言葉を選びました。
後日、母から「読経の前に弔電を読み上げてもらったよ。みんな“孫から届いたんだね”って話してた」と聞いて、送って良かったなと思いました。
祖父への弔電文例
「祖父○○様のご逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。
在りし日のお姿を偲び、ご恩に感謝しつつ、心よりご冥福をお祈りいたします。」
祖父の場合は、感謝の気持ちを表現する文面が多いです。
私自身、祖父が亡くなったときは小学生だったので弔電は送りませんでしたが、大人になった今ならきっとこう書くと思います。
祖父母への弔電では、「いつも見守ってくれたこと」「優しくしてくれたこと」への感謝を入れると、読んだ親族の心にも響くはずです。
親族に送る弔電の文例【両親の場合】
両親の場合は、祖父母以上に近しい存在であり、より深い悲しみを込めた表現が自然です。
私も、もし両親に弔電を送る立場になったら…と想像するだけで胸が詰まります。
父への弔電文例
「父○○様のご逝去の報に接し、深い悲しみでいっぱいです。
小さい頃から大切に育てていただきましたこと、心より感謝しております。
本日はやむを得ない事情により参列できませんが、遠くからご冥福をお祈り申し上げます。」
父への弔電では、自分が子としてどれだけ感謝しているかを入れると自然です。
私自身、父がまだ健在の今でも、思い返すと「厳しかったけど、やっぱり支えてもらったな」と感じることがたくさんあります。
たとえば、進路で迷っていたときに「やってみてから考えたらいい」と背中を押してくれたことや、社会人になって一人暮らしを始めた私に毎月野菜を送ってくれたこと。
弔電にはそうした日常の小さな感謝を込めると、読む家族にも気持ちが伝わると思います。
母への弔電文例
「母○○様のご逝去の報に接し、言葉にならないほどの悲しみで胸がいっぱいです。
優しく温かい笑顔でいつも支えてくださったこと、一生忘れません。
遠くより心よりご冥福をお祈り申し上げます。」
母の場合は、「支えてくれた」という表現を入れると気持ちがより深く届きます。
私も、もし母に送るなら、家事や育児を当たり前のようにこなしながら、私のことも常に気にかけてくれていたことを書きたいです。
毎朝お弁当を作ってくれたこと、夜遅く帰っても「おかえり」と笑顔で迎えてくれたこと。
そうした一つ一つの支えがあって、今の自分があるんだと、弔電を書くことで改めて思い出すかもしれません。
親族に送る弔電の文例【兄弟姉妹の場合】
兄弟姉妹の場合も、近しい関係だからこそ、思い出や感謝を入れるといいですね。
私自身、もし兄や妹に弔電を送る立場になったら…と考えると、色々な思い出が溢れてきます。
兄への弔電文例
「兄○○様の突然のご逝去の報に接し、信じられない思いでいっぱいです。
小さい頃から何かと気にかけてくれた優しい兄の笑顔が思い出されます。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。」
兄への弔電では、幼い頃からお世話になったことや、兄ならではのエピソードを一文でも入れると気持ちが伝わります。
私も兄がいるのですが、小さい頃はよく一緒にゲームをして遊んだり、時には叱られたり…。
でも社会人になってからは、年末に帰省すると必ず駅まで迎えに来てくれる優しさに、子どもの頃とは違う兄の一面を感じていました。
もし弔電を送るなら、「いつも私を守ってくれたお兄ちゃんへ」という想いを込めたいです。
妹への弔電文例
「妹○○様のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げます。
幼い頃からいつも明るく、家族の中心だった妹を思うと、胸が痛みます。
どうか安らかにお眠りください。」
妹への弔電では、その明るさや可愛らしさ、家族の癒しだったことを書き添えると良いと思います。
私には妹はいませんが、友人が妹を亡くしたとき、「家族のムードメーカーだったから本当に寂しい」と話していました。
兄弟姉妹への弔電は、両親や祖父母とは違って、対等な立場で過ごしてきた思い出が多いもの。
「いつもありがとう」「もっと話したかった」という素直な気持ちを一言でも入れると、読む家族の心にも届くと思います。
親族に送る弔電で気をつけたい言葉選び
弔電では、普段何気なく使っている言葉でも、避けたほうがいい表現があります。
私も初めて弔電を送るとき、ネットで調べながら「えっ、この言葉もダメなの?」と驚いたことがありました。
重ね言葉は避ける
「度々」「再び」「またまた」など、繰り返しを連想させる言葉はNGです。
不幸が続くことを連想させるため、弔電では使わないようにしましょう。
たとえば、私は普段「また改めてご連絡しますね」と書くことが多いのですが、弔電で「また」という言葉は避けるべきだと知って、言葉選びの難しさを感じました。
「死」「生」など直接的すぎる表現は控える
「死」という言葉はとても直接的で、受け取った側の心に突き刺さってしまうことがあります。
弔電では、「ご逝去」「ご永眠」「ご逝去の報に接し」といった表現を使うのが一般的です。
以前、取引先への弔電文例を調べていたとき、「生前」という言葉も注意が必要だと知りました。
失礼ではありませんが、「ご生前のご厚誼に感謝いたします」など正しい使い方を確認してから書くようにしています。
不安を煽るような表現も避ける
「恐ろしい」「怖い」など、必要以上に不安や恐怖を感じさせる言葉は避けましょう。
悲しみの場に寄り添うためにも、相手の心をえぐるような強い言葉は使わないほうが安心です。
私は一度、「悲しくて辛くてたまらない」という表現を書きかけたことがありましたが、夫から「読む人が余計につらくなるかもよ」と言われ、柔らかい表現に直しました。
弔電を送るときのマナーと注意点
最後に、親族への弔電を送るときに私が気をつけているポイントをまとめます。
初めて弔電を送ったときは、「送り方を間違えたら失礼になるかも…」と不安で、何度も確認したのを覚えています。
できるだけ早めに手配する
葬儀が始まる前までに届くよう、わかった時点で手配することが大切です。
特に午前中に葬儀が行われる場合、前日までには届くよう手配するのが安心です。
私も以前、参列できないと決まった夜に、急いでネットで弔電を申し込みました。
申し込み時間によっては当日配送が間に合わないこともあるため、早め早めの対応を心がけています。
差出人名はわかりやすく
親族でも、同じ名字の人が多い場合は、名前だけでなく住所や続柄を記載しておくとわかりやすいです。
例えば、「長女」「孫」など続柄を添えるだけで、誰から届いたのか喪主や遺族がすぐに把握できます。
葬儀当日は弔電がたくさん届くため、差出人がわかりやすいと読む側も助かります。
誰宛てに送るか確認する
弔電は、喪主や遺族宛てに送るのが一般的です。
名前や肩書を間違えないよう、家族や親戚に確認してから申し込みましょう。
以前、親族間で喪主を勘違いしていたことがあり、事前確認して助かった経験があります。
「失礼がないように」と確認するひと手間が大切です。
まとめ|親族への弔電は心を込めた一文を
親族に送る弔電は、格式を守りつつも、何より「自分の言葉で気持ちを伝えること」が大切だと私は思います。文例を参考にしつつ、故人への思い出や感謝を一文でも添えると、読む側も心に響きますよ。
もし今、弔電を送ろうか悩んでいるなら、ぜひ今日中に文面を考えて、気持ちが届くよう準備してくださいね。