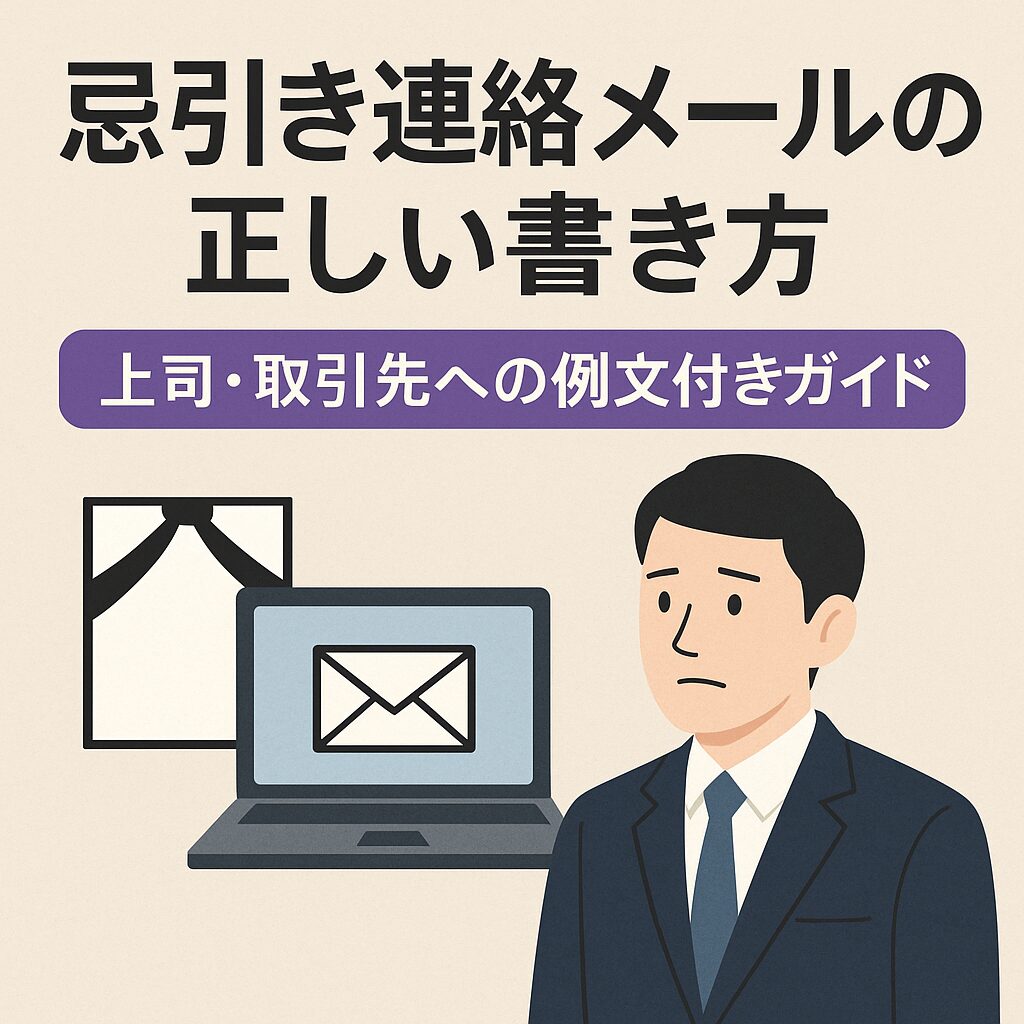身内の不幸は突然訪れるもの。気が動転する中で、上司や取引先への連絡に戸惑う方も多いのではないでしょうか。特にメールでの連絡は、マナーや文面に不安を感じやすいものです。
本記事では、「忌引き連絡メールの正しい書き方」をテーマに、状況別の例文や文面のポイント、押さえておきたいマナーをわかりやすく解説します。社会人として恥をかかず、誠実な気持ちが伝わるメールを送りたい方は、ぜひ最後までお読みください。
忌引きのための職場への連絡方法
忌引きメールの重要性とタイミング
身内に不幸があった場合、悲しみに包まれる中で職場への連絡という現実的な対応が求められます。特に就業時間が近づいている場合には、迅速な連絡が社会人としての基本的なマナーとなります。
訃報は多くの場合、突然訪れるものです。前触れなく予定を空ける必要があるため、就業開始前のできるだけ早い時間帯に、まずは電話やメールで状況を伝えることが重要です。
連絡が遅れると、無断欠勤と捉えられてしまう可能性もあるため、感情が整理できていなくても、最小限の情報を伝える勇気を持つことが大切です。その後、落ち着いてから詳しい内容を追って伝える形でも問題ありません。
上司への連絡の方法とマナー
忌引きによる欠勤の際は、まず直属の上司への連絡が最優先事項となります。形式的なメールだけではなく、できれば電話で直接話す、または出社前に口頭で伝えるなど、相手の状況に応じた対応が求められます。
特に電話では、長々と話す必要はありませんが、次のような簡潔で要点を押さえた言い方を心がけましょう。
「お忙しいところ失礼します。実は、父が本日未明に他界いたしまして、〇日から〇日まで、忌引きをいただきたくご連絡いたしました。」
このように、故人との関係性・忌引きの予定期間・お詫びと感謝の言葉を含めるのが丁寧です。その後、業務への影響や引き継ぎの件については、改めてメールなどで文面に残すと安心です。
職場での口頭連絡のメリットとデメリット
上司や同僚が近くにいる場合、直接顔を合わせて口頭で伝えることで、状況の深刻さや自分の心情をより正確に伝えることができるというメリットがあります。また、相手の反応を見ながら説明できるため、誤解も生まれにくくなります。
一方で、口頭だけでは後に記録が残らないという点がデメリットです。後日、休暇申請や勤怠管理、他部署への共有などが必要な場合、口頭の内容が正しく伝わっていなかったというトラブルにつながる可能性もあります。
そのため、口頭連絡の後には必ず、「念のためメールでも失礼いたします」といった形で文書での補完を行うことが望ましいです。
社内ルールと就業規則の理解
忌引きの範囲や休暇日数は、各会社の就業規則に具体的に定められているケースがほとんどです。たとえば、配偶者が亡くなった場合には5日間、実父母や子の場合は3日間、祖父母や兄弟姉妹は1〜2日間というように、故人との続柄によって取得できる日数が異なるのが一般的です。
また、企業によっては家族葬や遠方での葬儀参加のための移動日を含めた特別な配慮がある場合もあるため、事前に確認しておくことで、無理のないスケジュール調整ができます。
就業規則は社内の共有サーバーや社員ハンドブックに掲載されていることが多いため、落ち着いた段階で一読しておくことをおすすめします。
忌引きメールの基本的な書き方
メール件名の設定のポイント
メールの件名は、受け取る相手が一目で内容を理解できるように、端的かつ丁寧な表現を心がけましょう。たとえば、次のような形式が一般的です。
-
【忌引き連絡】忌引きによる休暇取得のご報告
-
【ご連絡】身内の不幸に伴う欠勤について
-
【私用連絡】忌引き休暇の取得について
上司や人事部など、複数の関係者に一斉送信する場合は、あえてやや柔らかい表現で「ご連絡」としておくと無難です。逆に、直属の上司など目上の方に個別に送る場合は、「忌引きによる休暇取得のお願い」といった文言も丁寧な印象を与えます。
件名であまり感情を表現しすぎず、淡々とした事務的な文面が好まれる傾向にあります。
本文に記載すべき必要事項
本文では、相手が状況を把握しやすいように、以下の5つの基本情報を簡潔に伝えることが大切です。
-
故人との続柄(例:実父、祖母など)
→ 例:「実父が他界いたしましたため」 -
亡くなった日と訃報の状況(必要に応じて)
→ 例:「昨日〇月〇日、永眠いたしました」 -
忌引きによる欠勤・休暇の日程
→ 例:「〇月〇日より〇月〇日まで、忌引き休暇を取得させていただきたく存じます」 -
業務の引き継ぎ・対応方法
→ 例:「現在担当している業務については、△△さんに引き継ぎをお願いしております」 -
緊急時の連絡手段(可能な範囲で)
→ 例:「急ぎのご用件がございましたら、携帯電話(090-xxxx-xxxx)までご連絡いただけますと幸いです」
これらの情報を過不足なく盛り込み、読み手に余計な手間をかけさせない配慮が重要です。内容が複雑な場合は、箇条書きにすることで視認性を高めましょう。
故人への敬意を表す言葉
メール本文には、故人に対する敬意を表す適切な言葉遣いが求められます。「死亡」「死去」といった直接的な表現は避け、以下のような婉曲表現(えんきょくひょうげん)を使うのが一般的です。
-
「父が永眠いたしました」
-
「祖母が逝去いたしました」
-
「叔父が他界いたしました」
-
「義父が息を引き取りました」
また、「亡くなった」「亡くなられた」も会話では使用されることがありますが、ビジネスメールのようなフォーマルな文面ではややカジュアルな印象を与えることもあるため注意が必要です。
宗教・宗派によっては「ご冥福をお祈りします」も避けたほうがよいケースがあるため、社内メールではあくまで「忌引き連絡」にとどめ、お悔やみの表現は最小限に抑えるのが無難です。
お礼の言葉とそのタイミング
最後に必ず添えておきたいのが、周囲への配慮と感謝の気持ちを表す一文です。急な休暇により、業務の負担が周囲にかかることへの謝意を伝えることで、丁寧で誠実な印象を与えることができます。
例文:
-
「急なご連絡となり恐縮ですが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます」
-
「関係各所にはご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただけますと幸いです」
-
「ご配慮に感謝いたしますとともに、何卒よろしくお願いいたします」
こうした一文があるだけで、相手に対する敬意や気遣いがしっかりと伝わり、信頼感のあるやりとりに繋がります。
葬儀や家族葬に関する連絡の注意点
葬儀の日時と式場の情報
忌引きの連絡において、通夜や葬儀の詳細を共有すべきか否かは、状況や相手との関係性によって異なります。たとえば、取引先や社外の関係者で、弔問を希望されるケースが想定される場合は、以下の情報を簡潔に記載しておくとよいでしょう。
-
通夜・告別式の日時
-
式場の名称と住所
-
喪主の氏名(故人との関係も明記)
-
参列の可否や香典対応の方針
ただし、社内のメールで広く一斉送信する場合は、詳細な日時や場所は控えたほうが無難です。情報の取り扱いには慎重を期し、「ご希望の方には個別にご案内いたします」などと添えると丁寧です。
家族葬の場合の特別な配慮
近年では、身内のみで静かに行う「家族葬」が増えており、会社関係者や友人知人の参列をお断りするスタイルも一般的になりつつあります。
そのため、家族葬を予定している場合は、あらかじめ次のような文言をメールに明記しておくと、相手の善意を無下にすることなく、誤解や行き違いを避けることができます。
例:
「なお、葬儀は家族葬のため、誠に恐縮ですがご参列はご遠慮いただいております。お気持ちだけありがたく頂戴いたします。」
このように伝えることで、相手の配慮や弔意を受け止めつつ、参列辞退の意志を穏やかに伝えることができます。
香典に関する基本的なマナー
香典についても、辞退するかどうかの方針を明示しておくと、相手の判断の負担を減らすことができます。特に会社関係者から香典をいただくと、香典返しの手配や社内対応にも影響が出るため、辞退する場合は早めに伝えておくと安心です。
例:
「香典等のお気遣いはご無用に願えればと存じます。お気持ちだけありがたく頂戴いたします。」
このような言い回しは、ビジネスマナーとしても柔らかく、失礼がありません。一方で、受け取りを希望する場合には、香典の受付に関する連絡先や手順を社内規定に従って記載しましょう。
弔意の表現方法と忌み言葉
葬儀や訃報のやりとりでは、「忌み言葉」に注意することが非常に重要です。忌み言葉とは、死や不幸を連想させる「重ね言葉」や、不適切な表現のことを指します。
避けるべき言葉の例:
-
重ね重ね(不幸が重なることを連想)
-
またまた、再び(死を繰り返す印象を与える)
-
流れる、水に流す(死を軽んじる印象)
-
消える、なくなる(命に対して失礼な表現)
一方で、お悔やみの定型表現は、社会人として身につけておくと安心です。たとえば、「ご冥福をお祈りいたします」「ご愁傷様でございます」などが一般的ですが、宗教・宗派によっては使用を避けるべき場合もあります。
社内メールでは、お悔やみの言葉は控えめに、状況連絡を中心とした文面にとどめるのが基本です。正式な場面でお悔やみを述べる場合は、宗教的背景や相手との関係性も配慮しながら言葉を選びましょう。
忌引き申請の具体的な方法
休暇の取得期間とその申請
忌引き休暇を取得する際は、会社の就業規則に基づいた日数を正しく把握し、上司や人事へ速やかに申請することが基本です。
一般的には以下のように日数が定められていることが多く、続柄によって異なります。
-
配偶者:5日間
-
父母・子:3日間
-
祖父母・兄弟姉妹:1〜2日間
ただし、葬儀の場所が遠方であったり、喪主としての務めがある場合など、実際に必要となる日数はケースによって異なるため、規定日数以上の休暇が必要な場合は、有給休暇や特別休暇との併用を検討し、事前に相談することが大切です。
メールで申請する際には、休暇の開始日・終了日、理由、代替対応の有無などを簡潔にまとめるとスムーズです。
必要な書類の準備と提出方法
忌引き休暇の申請にあたっては、企業によって証明書類の提出が求められる場合があります。提出が必要となる主な書類には次のようなものがあります。
-
死亡診断書の写し(コピー)
-
会葬礼状(葬儀後に配られるお礼状)
-
葬儀の案内状や火葬許可証のコピー
これらの書類は、勤務先の就業規則や人事担当者の指示により異なるため、事前に必要書類の有無と提出期限を確認しておくことが重要です。
また、会社によってはオンラインで申請・提出が可能な場合もあるため、社内ポータルや申請フォームの確認も忘れずに行いましょう。
提出時には、「お手数をおかけいたしますが、添付書類をご確認のほどよろしくお願いいたします」といった丁寧な一文を添えると好印象です。
部下や同僚への業務引き継ぎのコツ
急な忌引きとなると、業務の引き継ぎが十分にできないケースもありますが、最低限の情報だけでも共有することがトラブル防止に繋がります。
以下のポイントを押さえて引き継ぎを行いましょう。
-
現在の業務の進捗状況
-
締め切りが近いタスクや納期
-
特に注意すべき顧客対応や案件の詳細
-
緊急時の対応ルール
引き継ぎには、箇条書きで整理したメモやメールを活用するのが効果的です。引き継ぎをお願いする相手が決まっている場合は、指名しておくことで周囲の混乱を防げます。
例文:
「私の不在中は、〇〇さんに業務をお願いしております。詳細は以下にまとめましたのでご確認ください。」
こうしたひと手間が、円滑な業務継続と職場の信頼関係の維持につながります。
電話連絡の際の注意点
忌引き連絡の第一報を電話で行う場合、感情が乱れがちな状況でも、落ち着いて必要事項を伝えることが求められます。
そのためには、次のような準備が有効です。
-
話す内容をあらかじめメモに書き出しておく
→ 続柄・休暇期間・業務の状況など -
話す順番を整理し、無駄のない説明を心がける
-
相手の忙しい時間帯を避けて連絡する(朝一や就業直後は避けるのがベター)
例文:
「お忙しいところ恐れ入ります。実は、祖母が本日未明に永眠いたしましたため、〇日から忌引き休暇を取得させていただきたく、ご連絡差し上げました。」
電話での第一報の後は、同じ内容を改めてメールなどで文書化しておくと、記録としても安心です。
忌引きメールの例文とテンプレート
ビジネスシーン向けの文例
ビジネスシーンで忌引きの連絡をする際は、礼儀を守りつつも簡潔に状況を伝えることが大切です。社内の上司や同僚に送るメールでは、次のような文例が適切です。
件名:【忌引き連絡】忌引きによる休暇取得のご報告
宛先: 上司・チームメンバー(必要に応じて)
本文:
お疲れ様です。〇〇部の△△です。
突然のご連絡となり恐縮ですが、実父が〇月〇日に永眠いたしました。
誠に勝手ながら、〇月〇日より〇月〇日までの間、忌引き休暇をいただきたく存じます。
現在担当しております業務につきましては、〇〇さんに一時的に引き継ぎをお願いしております。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
このように、故人との関係、休暇の期間、業務引き継ぎの状況、謝意を含めることで、相手に配慮のある印象を与えることができます。
学校・学生向けのLINE・メール例文
学校やアルバイト先への連絡では、形式ばりすぎず、でも丁寧さを意識するのがポイントです。LINEなどのカジュアルな手段であっても、失礼のない文面が求められます。
LINE・メール例文(学校向け):
お世話になっております。〇年〇組の△△です。
祖父が亡くなったため、〇月〇日から数日間お休みさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。
バイト先向け:
店長、お疲れ様です。〇〇で働いている△△です。
親族に不幸があり、〇日と〇日は出勤できなくなりました。
急なご連絡で申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
トーンは柔らかく、でも必要な情報(理由・期間・謝意)をきちんと盛り込むことが重要です。
取引先への連絡テンプレート
取引先への連絡では、業務に支障が出ることを最小限に抑える配慮が求められます。個人的な事情であるため、詳細に触れすぎず、業務継続への案内を含めるのがポイントです。
例文(社外宛て):
〇〇株式会社
△△様
平素より大変お世話になっております。〇〇株式会社の□□です。
私事で大変恐縮ですが、親族の不幸により〇月〇日より〇日間、休暇をいただいております。
期間中のご連絡につきましては、弊社〇〇(部署・氏名:連絡先)までお願いいたします。
急なご連絡となり誠に申し訳ありませんが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
代理担当者の明示・連絡先の記載があれば、相手も安心して業務を進めることができます。
顔の見えない相手への伝え方
社外の関係者や、あまり親しくない相手へ忌引きの旨を伝える際は、詳細を避けつつも礼儀正しく伝える表現を選びましょう。体調不良や私用といった曖昧な言い方も可能ですが、事実をぼかさずに伝えるほうが信頼感があります。
例文(シンプルかつ丁寧なパターン):
お世話になっております。〇〇の△△です。
私事で恐縮ですが、所用により〇日より数日間お休みをいただいております。
急なご連絡となり申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。
忌引きであることを示したい場合:
お世話になっております。〇〇の△△です。
親族の不幸により、〇月〇日より〇日まで休暇をいただいております。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
このように、相手との関係性やTPOに応じて伝え方を調整することが、社会人としてのマナーとなります。
自由な表現力を高めるための知識
重ね言葉の使い方と注意点
弔事においては、言葉の選び方一つで相手に不快感を与えることもあるため、縁起を担ぐ文化的な背景を理解することが大切です。
特に「重ね言葉(同じ語を繰り返す表現)」は、不幸が重なることを連想させるため、避けるのがマナーとされています。
代表的なNG例:
-
たびたび(度重なる印象を与える)
-
ますます(不幸が増すという語感)
-
重ね重ね(繰り返しの象徴)
-
またまた(再びを意味する)
これらは日常会話ではよく使う表現ですが、弔事の文面や会話では不適切です。代わりに次のような表現を使用すると安心です。
代替表現例:
-
「あらためてお悔やみ申し上げます」
-
「深くお見舞い申し上げます」
-
「お気持ちお察しいたします」
言葉の持つ意味や語感にも配慮することが、信頼される社会人の証です。
「お悔やみ申し上げます」の具体的な使い方
「お悔やみ申し上げます」は、葬儀や訃報に接した際の最も一般的な表現のひとつですが、文脈や相手との関係によって適切な言い回しを選ぶことが大切です。
■ フォーマルなメールや手紙の場合:
ご尊父様のご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。
ご遺族の皆様に、慎んで哀悼の意を表します。
■ 社内メールでの簡潔な表現:
このたびはご愁傷様でございます。心よりお悔やみ申し上げます。
■ 宗教や宗派に配慮する場合(無宗教・仏教以外も想定):
謹んで哀悼の意を表します。皆様のご心痛、いかばかりかとお察しいたします。
なお、「ご冥福をお祈りします」という表現は仏教的意味合いが強く、キリスト教や神道では適さない場合もあるため、ビジネスではなるべく中立的な表現が望まれます。
葬儀場や斎場、アクセス情報などの扱い
葬儀に関する日時や場所などの詳細情報は、必要最小限の範囲でのみ共有するのが基本です。特に社内メールでの一斉送信など、広範囲に情報が届く場面では、個人情報保護の観点からも注意が必要です。
■ 基本的な方針:
-
式場の情報は参列の打診があった場合にのみ個別に伝える
-
メール本文に記載する際は「ご希望の方には個別にご案内いたします」と添える
-
通夜や告別式の地図・アクセス情報は添付ファイルでなく、公式サイトのURLを案内する方がスマート
■ 共有が適切なケース:
-
部署全体が参列するような慣習がある場合
-
上司や役員が弔電や供花を送る必要がある場合
情報管理が求められる時代だからこそ、慎重な配慮が信頼につながります。
困ったときの対処法と相談先
忌引きや訃報対応に関して、不安を感じたり判断に迷うことがあれば、一人で抱え込まずに社内のサポート先に相談することが大切です。
主な相談先:
-
直属の上司:業務引き継ぎ・スケジュール調整
-
人事・総務部門:忌引き休暇の日数や書類対応、香典処理の方針など
-
信頼できる同僚:急ぎの業務対応や代理調整の相談
-
社内にグリーフケア制度がある場合:心のケアに関する支援窓口の利用
中には、グリーフケア(悲しみのケア)支援やEAP(従業員支援プログラム)などを導入している企業も増えています。精神的に負担が大きいときは、「業務」ではなく「自分」を優先する勇気も必要です。
忌引き後の業務復帰の指針
復帰時の挨拶と心得
忌引き休暇から職場に戻った際には、職場の仲間に対して感謝と配慮を込めた挨拶を行うことが基本マナーです。特に上司やチームメンバーには、以下のような言葉を添えることで、丁寧な印象を与えることができます。
例文:
「このたびは急なお休みをいただき、ご迷惑をおかけしました。」
「温かいお言葉をいただき、心より感謝申し上げます。」
感情が整理しきれていない中でも、一言でも誠意ある挨拶を伝えることで職場復帰がスムーズになります。また、タイミングとしては、出社初日の午前中など、落ち着いた時間に個別に挨拶するのが望ましいです。
上司や同僚への謝意の表現
忌引き中に業務を代わってもらった上司や同僚には、感謝の気持ちを明確に伝えることが職場での信頼関係の維持に直結します。以下のような方法があります。
-
直接言葉で伝える:「お忙しい中、業務をフォローしていただき、本当にありがとうございました。」
-
お礼のメールを送る:「このたびはご対応いただき、誠にありがとうございました。おかげさまで安心してお休みをいただけました。」
丁寧なお礼は、その後の業務連携やチームの雰囲気にも良い影響を与えるため、気持ちだけでなく行動で示すことが大切です。
復帰後の業務引き継ぎの進め方
休暇明けには、まず引き継ぎを受けた業務の内容を確認し、スムーズに業務に戻れるよう整理することが重要です。フォローしてくれた方への配慮として、以下のような対応を心がけましょう。
-
受け取ったメモや報告を元に、自分の手で一度内容をまとめ直す
-
「確認しました、ありがとうございました」の一言を添える
-
業務の中で不明点が出た場合は、「〇〇の件について、念のためご確認させていただいてもよろしいでしょうか?」と感謝+確認の形で対応する
また、地域や職場によっては、菓子折りなどを持参することが習慣となっているケースもあります。形式にとらわれすぎる必要はありませんが、以下のような対応も心遣いとして受け取られます:
-
お礼の菓子折りに「このたびはご対応ありがとうございました」のメモを添える
-
チームで共有できる小分けのお菓子を選ぶと喜ばれやすい
義務ではなく「気持ち」としての対応が、円滑な関係維持に繋がります。
気をつけるべき雰囲気と配慮
忌引き後は、周囲も気を遣っている場合が多く、あなた自身の立ち振る舞いが職場全体の空気を左右することもあります。以下のような配慮を心がけましょう。
-
過度に暗くならず、無理に明るくもふるまわない
→ 普段どおりを意識しつつ、心を整えて対応を -
業務復帰を急がず、周囲のサポートを素直に受け入れる
→ 周囲との温かな関係性を築く機会にもなります -
忌引きの話題を自分から過剰に話さない
→ 質問されたときのみ簡潔に答える程度が無難です
特に、感情の整理がつかない場合は無理せず、心と体のバランスを大切にしてください。必要であれば、総務や人事に相談して、勤務内容や時間を一時的に調整してもらうのも一つの手です。
忌引きに関するよくある質問
期間や日数に関する疑問
忌引き休暇の取得可能な期間や日数は会社の就業規則によって異なるため、必ず確認が必要です。一般的な基準としては以下のような日数が多くの企業で採用されています。
| 故人との続柄 | 忌引き日数の例(目安) |
|---|---|
| 配偶者 | 5日間 |
| 父母・子 | 3日間 |
| 祖父母・兄弟姉妹 | 1〜2日間 |
ただし、実際の休暇は通夜・葬儀の準備や移動距離、喪主としての対応などで数日では足りないケースも多々あります。その場合には、以下のような調整が可能です。
- 有給休暇を追加で申請する
- 業務の繁忙状況に応じて上司と相談して調整
- 就業規則に定めのないケースでは人事と個別に交渉
休暇日数は「制度の上限」ではなく、「柔軟に相談できるもの」と考えるとよいでしょう。
休暇中の連絡方法について
忌引き期間中は原則として、業務連絡を控えるのがマナーです。とはいえ、重要な案件が進行中だったり、急ぎの対応が発生する可能性がある場合には、最低限の連絡手段を残しておくことが現実的な対応となります。
実務上のポイント:
- 忌引きの連絡時に「緊急の場合は携帯またはメールにてご連絡ください」と伝えておく
- 業務の代理担当者を明示し、「基本的には〇〇さんへご連絡ください」と補足する
- 常に返信できる体制ではないことを明記しておくと相手の配慮を促せる
例文:
「忌引き中のため原則ご連絡には対応いたしかねますが、緊急のご用件がある場合は〇〇(代理者)までお願いいたします。なお、携帯(090-xxxx-xxxx)にご連絡いただければ、可能な範囲で折り返しいたします。」
完全に遮断するのではなく、“最低限の窓口を残す”ことが社会人としての誠意につながります。
弔電や香典に関するマナー
忌引き中や葬儀に関して、香典や弔電をいただいた際の対応にも一定のマナーがあります。
■ 弔電をいただいた場合:
- 通夜または葬儀終了後、数日以内に「お礼の電話」または「お礼状」を送るのが一般的
- 式が終わって落ち着いた頃に返信するのがマナー
- 会社宛てに送られた場合は、喪主名義で返信することもあるため親族と相談を
■ 香典を辞退した場合でも:
- 辞退の意志を伝えていても、実際に受け取ってしまった場合は「香典返し」が必要になることもある
- 香典返しは「四十九日」前後に送るのが通例(地域によって異なる)
- 社内や取引先の場合、香典返しは不要とされるケースもあるが、上司や総務と相談のうえ対応するのが安心
対応に迷った場合は、自分だけで判断せず、親族や会社に相談しながら誠意ある対応を心がけましょう。
対応が必要な状況別のアドバイス
葬儀や忌引き対応には、状況ごとに適切な伝え方や行動が異なります。以下に代表的なケースとその対処法を紹介します。
参列の要望があった場合
家族葬や近親者のみでの式を予定している場合、参列を控えていただきたい旨を事前に丁寧に伝えることが大切です。
例文:
「誠に恐縮ですが、葬儀は近親者のみで執り行う予定のため、ご参列はご遠慮いただいております。お気持ちだけありがたく頂戴いたします。」
このような表現であれば、相手の厚意に対しても失礼がなく、誤解や行き違いも防げます。
会社や上司が弔電や供花を申し出た場合
- 「ありがとうございます。喪主と相談のうえ、改めてご連絡させていただきます」と一度保留して確認
- 喪主や葬儀社に確認し、受け入れ可否・送付先・名義の記載方法などを共有する
個人としての判断で即答せず、家族と協議したうえで対応するのが最善策です。
まとめ|正しいメールで誠実な対応を心がけましょう
忌引きの連絡は突然のことで戸惑いや不安も大きいですが、基本のマナーと文例を押さえておけば、落ち着いて誠実な対応ができます。
上司や取引先には、相手への配慮を忘れず、簡潔で丁寧な言葉を選びましょう。また、社内規定の確認や、葬儀の形式に応じた言い回しも大切です。
いざという時に困らないためにも、今のうちから本記事の内容を参考にして、自分なりの連絡文例を準備しておくことをおすすめします。誠意の伝わる対応が、信頼を築く一歩になります。