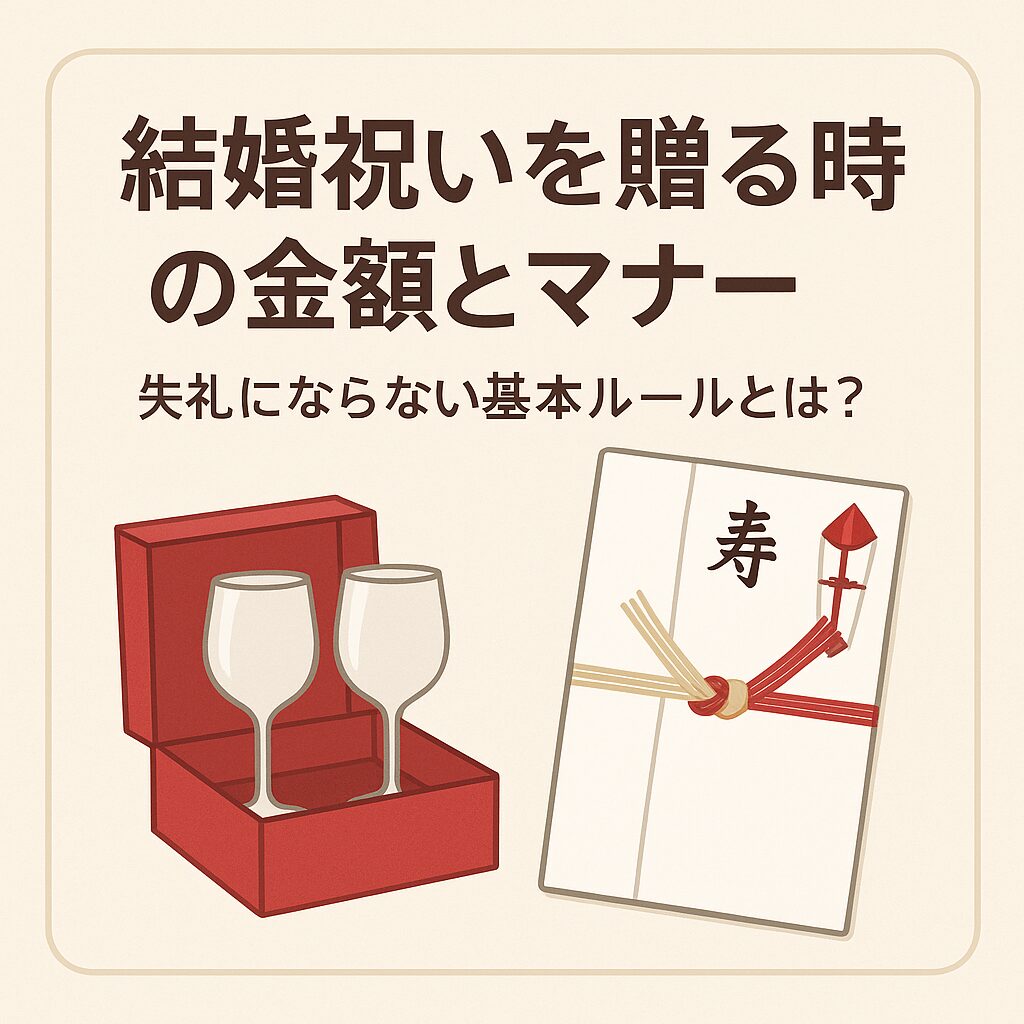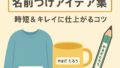「結婚祝いって、いくら包めばいいの?」「ご祝儀袋の書き方って合ってる?」
いざ贈るとなると、金額やマナーに不安を感じる方は少なくありません。特に、友人・親族・職場など立場によっても対応が異なるため、戸惑う場面も多いでしょう。
本記事では、結婚祝いの金額の相場からマナー、贈るタイミングやプレゼントの選び方まで、初めての方でも安心して準備できるように丁寧に解説します。
失礼にならず、しっかり気持ちが伝わる結婚祝いの贈り方を一緒に学びましょう。
結婚祝いの金額の相場
結婚祝いを贈る際、「いくら包めばいいのか?」という疑問は誰もが抱くものです。
ご祝儀の金額には明確なルールがあるわけではありませんが、一般的な相場やマナーを知っておくことで、失礼なく気持ちのこもったお祝いができます。
ご祝儀の一般的な金額
一般的に、ご祝儀の金額は贈る相手との関係性や立場によって変わります。以下は主なケース別の目安です。
| 関係性 | 金額の目安(目安) |
|---|---|
| 友人・同僚 | 30,000円 |
| 兄弟姉妹 | 50,000〜100,000円 |
| 親戚 | 30,000〜100,000円 |
| 上司・恩師 | 10,000〜50,000円 |
ご祝儀には「割り切れる偶数額(例:20,000円)」は避けたほうがよいとされます。これは「縁が切れる」「別れる」といった意味に通じるためです。
ただし、どうしても偶数額(2万円など)を贈る場合は、1万円札1枚+5,000円札2枚など、奇数枚数で包むことで問題は避けられます。
友人や親族別の金額の目安
友人へのご祝儀は、一般的には3万円が相場とされています。ただし、学生や社会人になって間もない若年層の場合、2万円でも十分に気持ちは伝わります。無理のない範囲で、身の丈に合った金額を選びましょう。
一方、兄弟姉妹に対しては、5万円以上とする人が多く、中には10万円を包むケースもあります。
地域によっては、現金ではなく高額な家電や家具を「プレゼントとして贈る」文化もあり、必ずしも現金にこだわる必要はありません。家族内の慣習や親との相談も大切です。
年齢や関係性による金額の変化
年齢を重ねたり、社会的立場が高くなると、包む金額も自然と上がっていく傾向があります。
例えば、30代後半〜40代で安定した職に就いている人が友人の結婚式に出る場合、相場にプラスしてもう1万円程度多く包むこともあります。
また、主賓として招かれた場合や、スピーチ・乾杯を依頼されている場合は、通常より高めの金額(+1万円)がマナーとされます。これは「式に華を添える役割を担う」立場として、心づけの意味もあるためです。
出席しない場合の金額について
結婚式に欠席する場合も、状況によってご祝儀の金額は変わります。基本的な目安は以下の通りです。
- 事前に欠席が分かっている場合:相場の3分の1〜半額程度
例:通常3万円 → 1万円〜1万5千円 - 直前にキャンセルする場合:全額(3万円など)を包むのが礼儀
これは、直前の欠席でも料理や引き出物のキャンセルが間に合わない場合があるためです。
ご祝儀は新郎新婦のための「お祝い金」であると同時に、式への参加費の意味合いもあるため、当日欠席でも費用負担が発生することを考慮しましょう。
また、欠席時にご祝儀を現金書留などで送る場合は、メッセージカードを添えるとより丁寧な印象になります。
結婚祝いのマナーと注意点
結婚祝いは気持ちが大切ですが、贈る際のマナーや形式を押さえておくことで、より丁寧な印象を与えることができます。ここでは、ご祝儀袋の選び方から渡し方、贈り物との兼ね合い、職場や友人との連携まで、押さえておきたい基本のマナーを詳しく解説します。
ご祝儀袋の選び方と書き方
ご祝儀袋にはさまざまなデザインや種類がありますが、包む金額と自身の立場に合ったものを選ぶのがマナーです。
| 金額 | ご祝儀袋の目安 |
|---|---|
| 1万円 | 水引が印刷されたシンプルなタイプ(略式) |
| 3万円 | 金銀の水引、和紙製で上質感のあるもの |
| 5万円以上 | 豪華な飾り付き、のし入りの正式タイプ |
水引の種類にも注意が必要です。結婚祝いでは「結び切り(10本結び)」の水引が適しており、「花結び(蝶結び)」は繰り返しを意味するため結婚には不向きです。
表書きは、毛筆や筆ペンを使い、濃い黒インクで書くのが正式。書く文字は以下のいずれかが一般的です。
- 「寿」(もっとも格式があり、汎用的)
- 「御結婚御祝」(やや丁寧で正式)
- 「御祝」(やや略式。相手との距離感によって使用可)
名前は水引の下にフルネームで書きます。連名の場合は、目上の人から順に右から左へ並べて記載しましょう。
現金の準備方法と渡し方
中に入れる現金は、必ず新札(折り目のない紙幣)を用意するのがマナーです。
これは「新たな門出を祝う」という意味があり、使用感のある旧札は避けたほうがよいとされています。新札は銀行窓口で両替が可能です。
現金は中袋(中包み)に以下のように収めます。
- 額面が見える向きで揃える(肖像が表側・上にくるように)
- 金額や名前、住所を中袋の所定欄に楷書で記入
ご祝儀袋はふくさ(袱紗)に包んで持参すると丁寧な印象を与えます。受付ではふくさから取り出し、表書きを相手に向けて渡すのが作法です。
一礼して「このたびはおめでとうございます」と一言添えると、さらに心が伝わります。
贈り物との兼ね合いと注意点
ご祝儀に加えてプレゼントを贈る場合は、どちらかが高額になりすぎないよう注意が必要です。
例えば、現金3万円+高価なギフトを同時に贈ると、相手が「内祝い(お返し)」に困る可能性があります。
プレゼントは新郎新婦に直接渡すよりも、事前に送るか、式後に改めて渡すほうが丁寧です。持参する場合は、引き出物と被らないよう、事前に内容を確認しておくと安心です。
また、以下のような品物は避けるのが一般的です。
- 刃物(縁を切る)
- ハンカチ(「手巾=てぎれ」と読める)
- 日本茶(弔事のイメージが強い)
友人や職場のケース別マナー
友人グループや職場の同僚と連名で贈るケースも多くあります。それぞれに適したマナーを押さえておきましょう。
職場の場合(部署・チームでまとめて贈る)
- 1つのご祝儀袋に全員の名前を連名で記入(3名以内)
- 4名以上になる場合は「○○一同」と記載し、別紙に名前を一覧で添付
- 個人で別途贈りたい場合は、タイミングをずらすなど配慮を
友人グループの場合
- お金を出し合ってプレゼントを購入するケースが人気
- 「仲良しメンバーから」という気持ちを込めて、代表者が贈る形も◎
- ご祝儀とは別に、プレゼントの品を贈る場合も、グループで1つにまとめるとスマート
いずれの場合も、一人ひとりの気持ちがきちんと伝わる工夫をすることが大切です。
結婚祝いのプレゼント選び
結婚祝いに何を贈れば喜ばれるのか、品物選びに悩む方も多いのではないでしょうか。
ご祝儀とは別にプレゼントを贈る場合は、新郎新婦の生活スタイルや趣味に配慮した実用性のあるものが好まれます。ここでは、人気ギフトから選び方のポイントまで、失敗しないためのヒントを解説します。
人気のギフトアイテム
結婚祝いとして人気があるのは、夫婦で使えるアイテムや日常で活躍する実用品です。特に以下のようなギフトは多くの新郎新婦に喜ばれています。
-
名入れグラス・食器
→ 記念に残るペアグラスや、名入りのカップなどは特別感があり人気です。 -
ペアパジャマ・バスローブ
→ 結婚生活をイメージさせる「おそろいアイテム」は、新婚気分を盛り上げます。 -
調理家電(ホットプレート・ブレンダーなど)
→ 料理好きなカップルや新生活を始める2人におすすめ。使えるギフトとして喜ばれます。 -
高級タオルセット
→ 自分ではなかなか買わない上質なタオルは、新生活にぴったりの実用品です。
どのアイテムを選ぶにしても、「大きすぎない」「収納に困らない」「重くない」など、日常使いしやすく、かさばらないものが選ばれる傾向にあります。
カタログギフトのメリットとデメリット
迷ったときの強い味方がカタログギフトです。最近ではジャンル特化型や体験型など、多様なタイプのカタログギフトも増えており、選ぶ楽しさも提供できます。
【メリット】
-
相手が自由に選べるので好みに合わないリスクが少ない
-
郵送もしやすく、遠方への贈り物にも最適
-
見栄えのよい専用BOXやメッセージカード付きのサービスも充実
【デメリット】
-
受け取る側によっては、「気持ちが伝わりにくい」と感じることもある
-
商品数が多すぎて迷ってしまう、あるいは希望に合うものが見つからないケースも
そのため、カタログギフトを贈る際は、価格帯・内容・ブランド感を意識して選ぶのがポイントです。
現金と品物の違いと選び方
「現金」か「品物」か迷う場合、それぞれのメリットを理解しておくと選びやすくなります。
-
現金(ご祝儀)
→ 実用的で、用途が自由。新居の準備や旅行など、使い道は自由自在。
→ 相手の好みが分からないときや、フォーマルな関係性には現金が無難。 -
品物(プレゼント)
→ 思い出に残る、気持ちが伝わりやすい。新婚生活の記念になる。
→ 仲の良い友人や家族など、親しい間柄ならリクエストを聞いて選ぶのも◎。
現金+品物のセットにする場合は、どちらかを控えめにするのが基本です。
また、相手に「内祝い(お返し)」の負担がかからない金額感を意識しましょう。
新郎新婦の好みに配慮する方法
せっかく贈るなら、本当に喜んでもらえるプレゼントを選びたいもの。以下のような工夫で、相手の好みに寄り添うことができます。
-
SNSでリサーチ
Instagramなどの投稿から、2人の趣味・生活スタイルが分かることも。 -
共通の友人にさりげなく聞く
本人に直接聞かずとも、友人経由で希望や避けたい物を知るのも手です。 -
挙式スタイルや新居の有無に合わせる
→ 例えば、式を挙げるホテルの雰囲気から上質なアイテムを選んだり、
→ 新居が決まっていれば、収納やインテリアに合うギフトを考えるのもおすすめです。
特に食器類はすでに揃えている可能性が高いため、注意が必要。贈る前に一言確認できると、より確実です。
結婚祝いのタイミングと方法
結婚祝いは「気持ち」が最も大切ですが、タイミングや渡し方を間違えると失礼にあたる可能性も。
ここでは、当日参加する場合・欠席する場合それぞれのシーンに合わせて、結婚祝いを気持ちよく渡すための準備とマナーを解説します。
参加する際の当日の準備
結婚式当日は、ご祝儀を持参するだけでなく、ちょっとした気遣いや準備が重要になります。
必須アイテムの確認
-
ご祝儀袋と筆記具は忘れずに持参しましょう。万が一、記入漏れがあった場合に備えて筆ペンを携帯しておくと安心です。
-
ご祝儀袋は折れや水引の乱れがないよう、ふくさ(袱紗)に包んで持ち運ぶのが正式なマナー。色は慶事用として赤系・ピンク・紫などが適しています(弔事と共用できる紫が万能)。
受付での渡し方
-
受付ではふくさからご祝儀を取り出し、表書きを相手に向けて両手で差し出します。
-
一礼しながら「本日はおめでとうございます。どうぞよろしくお願いいたします」など、一言お祝いの言葉を添えると丁寧な印象になります。
※慣れない場でも焦らず、ゆっくりとした動作を心がけると好印象です。
欠席時の贈り物の送り方
やむを得ず式を欠席する場合でも、お祝いの気持ちはしっかり伝えることが大切です。
贈るタイミング
-
一般的には挙式の1週間前〜当日までに届くように手配するのがマナー。
-
式後すぐに贈るのもOKですが、式が終わってから贈ると「忘れていた?」と思われる可能性もあるため、事前が安心です。
送り方のポイント
-
現金を贈る場合は、現金書留での送付が必要です。必ず郵便局の窓口から手続きを行いましょう。
-
プレゼントやカタログギフトなどの場合は、包装やメッセージカードの同封を忘れずに。
-
メッセージには「ご結婚おめでとうございます」「ご招待いただきありがとうございました」などのお祝いと感謝の気持ちを添えると好印象です。
事前に準備しておくべきこと
結婚式前に慌てないためには、以下の準備を早めに済ませておくのがポイントです。
-
新札の確保
→ 結婚祝いは「新しい門出」を祝う場。できるだけ折り目のない新札を用意しましょう。銀行窓口で「新札に両替してください」と依頼すれば対応してもらえます。 -
ご祝儀袋とふくさの準備
→ ご祝儀袋は金額に応じた格を選び、表書きと名前も事前に記入しておきましょう。ふくさは一つ持っておくと慶弔両用で便利です。 -
当日の交通手段や式場の確認
→ 式場の場所やアクセス方法、駐車場の有無、交通機関の時刻なども事前にチェック。遅刻は絶対にNGなので、時間には余裕を持って行動しましょう。
招待状が来た時の対応
結婚式の招待状が届いたら、返信ハガキはできるだけ早く返送するのがマナーです。以下の点に注意しましょう。
-
返信期限よりも1週間以内の返送が理想的
→ 招待側が席次表や料理の手配をする関係上、早い返信が喜ばれます。 -
欠席の場合も、失礼のない表現でお祝いの気持ちを伝える
→ たとえば「やむを得ない事情により出席がかないませんが、お二人の末永い幸せを心よりお祈り申し上げます」など、丁寧な文章を心がけましょう。 -
ハガキの表記マナーにも注意
→ 「御出席」「御芳名」などの「御」や「芳」の文字は二重敬語となるため、斜線で消すのが慣例です。
結婚祝いに関するFAQ
ここでは、結婚祝いを贈る際によくある疑問や悩みに答えるQ&A形式のまとめをお届けします。
迷ったときや不安なときの参考に、ぜひチェックしてください。
Q. ご祝儀の金額が多すぎるのはNG?
A. 一般的な相場を大きく超える金額は、相手に気を遣わせてしまう可能性があります。
特に親しい関係の場合、「そんなにもらって申し訳ない…」と恐縮されてしまうことも。
目安としては、相場+1万円以内に収めると無難です。
例えば、友人へのご祝儀の相場が3万円なら、4万円までに留めるのが理想的。
また、偶数の金額(2万・4万など)は割り切れる=縁が切れるとされるため避けるのがマナーです。どうしても偶数額になる場合は、札の枚数を奇数にするとよいでしょう(例:5千円札を混ぜるなど)。
Q. 友人の結婚式で悩みがちな選択肢とは?
現金かプレゼント、どちらを贈るべき?
A. どちらか迷ったら、本人に確認してもOKです。
特に親しい友人であれば「ご祝儀とプレゼント、どちらがうれしい?」と聞くのは失礼ではありません。
相手がすでに多くの現金をもらっていて「品物がうれしい」と言うこともあります。
遠方で出席できない場合は?
A. 出席できない場合も、何らかの形でお祝いを伝えるのが礼儀です。
おすすめは以下の2通り:
-
現金を現金書留で郵送する(1万〜1万5千円程度)
-
プレゼントやカタログギフトを配送で贈る
どちらの場合も、メッセージカードやお祝いの手紙を添えると好印象です。
Q. 内祝いとは何ですか?
A. 内祝い(うちいわい)とは、結婚祝いをいただいたお礼として贈るお返しの品です。
「内祝い=内(家)からのお祝い」という意味ですが、近年ではお祝いを“もらった側”が贈るお返しとして定着しています。
一般的には、いただいた金額の半額程度(“半返し”)を目安にお返しするのが通例。
たとえば、3万円のご祝儀をもらった場合は、5,000〜15,000円相当のギフト+お礼状を贈るのが目安です。
品物は、食品・タオル・洗剤・カタログギフトなどが多く、「消え物(使ってなくなるもの)」が好まれる傾向があります。
Q. 結婚祝いを贈る際のよくあるトラブルは?
結婚祝いにまつわるトラブルには、ちょっとした確認不足やうっかりミスが多いです。以下の点に注意しましょう。
-
名前の誤字や表書きのミス
→ 相手の名前を間違えるのは非常に失礼です。漢字や読み方をしっかり確認しましょう。 -
旧札の使用
→ 折れや使用感のあるお札は「使い回し」の印象を与える可能性があります。できるだけ新札を使いましょう。 -
渡すタイミングのズレ
→ 式が終わってからご祝儀を渡すのは避けましょう。欠席でも式の前に届くように手配するのが基本です。
トラブル回避のためには?
早めの準備+丁寧な確認がトラブル防止の鍵です。
「間に合わないかも」「これで大丈夫かな?」と思ったときは、経験のある家族や友人に相談するのも良い方法です。
結婚祝いは形式にとらわれすぎず、相手を思いやる気持ちが何より大切です。
ですが、基本的なマナーや相場を押さえておくことで、相手にも自分にも気持ちの良い贈り方ができます。
ぜひ本記事を参考に、大切な人の門出を心から祝福しましょう。
まとめ|結婚祝いの基本を押さえて、気持ちよくお祝いしよう
結婚祝いは「気持ちが大事」とはいえ、金額やマナーを知らずにいると、相手に気を遣わせたり、失礼になってしまうこともあります。
この記事では、ご祝儀の相場、関係性別の目安、正しい渡し方やプレゼント選びのポイントまで、初めての方でも迷わないよう詳しくご紹介しました。
大切なのは、祝福の気持ちをマナーにのせて、相手に心地よく届けること。
ぜひ今回の内容を参考に、安心して結婚祝いの準備を進めてみてください。