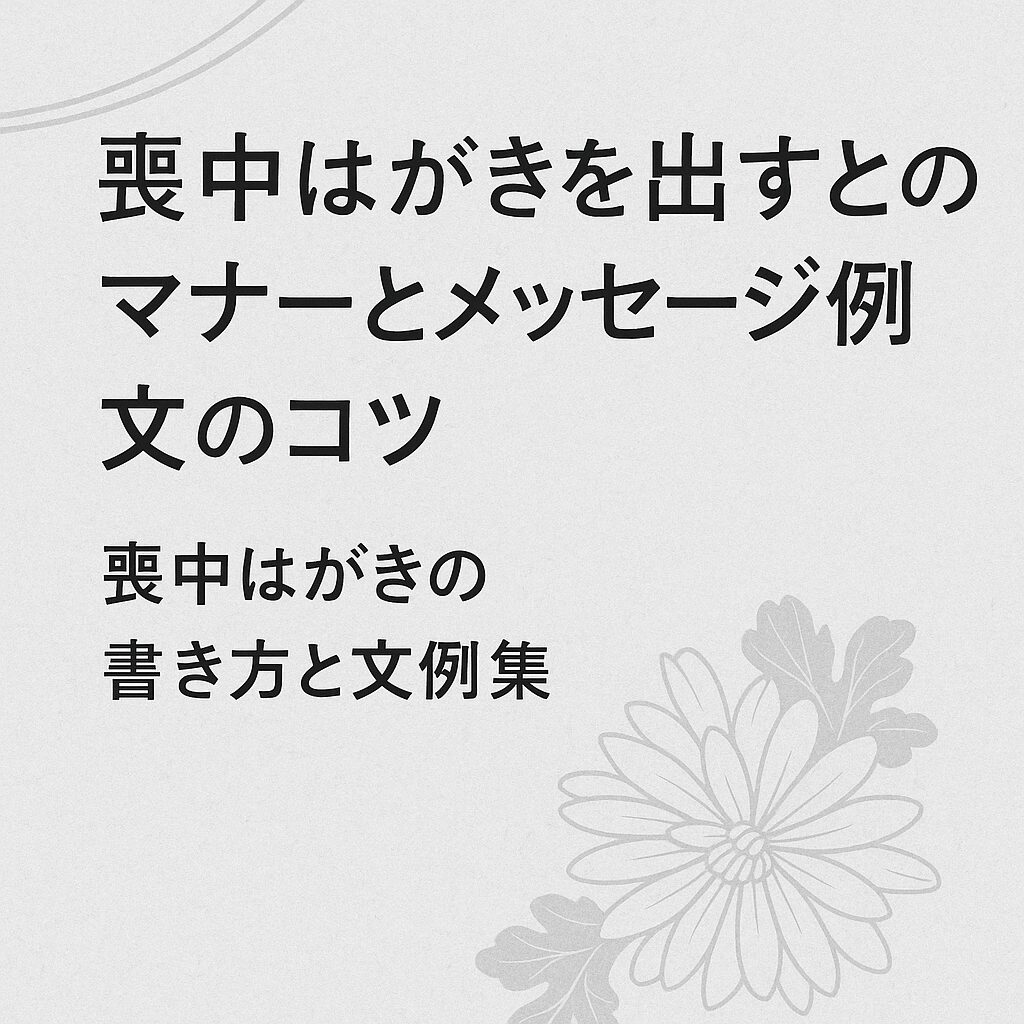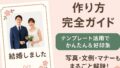年末が近づくと「今年は喪中だけど、どうやって知らせればいいの?」と悩む方が増えてきます。突然の別れに気持ちの整理もつかないまま、形式や文面に迷うこともあるでしょう。でも安心してください。喪中はがきは、故人への想いと相手への配慮を込めて、シンプルに丁寧に書けば大丈夫です。
本記事では、喪中はがきの基本マナーから、すぐに使えるメッセージ例文、文面の書き方のコツまでをわかりやすく解説します。初めての方でも失礼なく心のこもった一枚が届けられるよう、ぜひ最後までご覧ください。
喪中はがきの基本とマナー
喪中はがきとは何か
喪中はがきとは、身内に不幸があった際に、翌年の年賀状のやりとりを控えることを知らせる挨拶状です。正式には「年賀欠礼状(ねんがけつれいじょう)」と呼ばれ、年賀状を出す前の11月から12月にかけて送付されます。
このはがきは、単に「年賀状は出しません」という意思表示ではなく、故人との別れに対する心情や相手への配慮を込めた大切なコミュニケーションのひとつです。受け取った相手に「喪中である事情」を丁寧に伝え、年賀状を遠慮していただくと同時に、日頃の感謝も述べる役割を果たします。
喪中はがきの重要性
喪中はがきを送る最大の目的は、年賀状を送ってくれるであろう相手に、あらかじめ「年始の挨拶は控えさせていただきます」と伝えることです。年末ギリギリになって年賀状が届いた後に「喪中だった」と知ると、相手も戸惑いや気まずさを感じることがあります。
そのため、喪中はがきを出すことは、相手に配慮した「礼儀」としての意味合いを強く持っています。また、故人を大切に想いながらも、日常のつながりを円滑に保つという、日本人特有の気遣い文化の一部でもあります。
特に、仕事関係の方や恩師、親しい友人など、年賀状のやり取りが習慣になっている相手には、忘れずに送りましょう。
基本的なマナーとルール
喪中はがきを作成・送付する際には、いくつかの基本的なマナーがあります。
1. 喪中の対象は「二親等以内」が一般的
喪中の対象とされる親族は、両親・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母などの「二親等以内」が基準です。それより遠い親戚の場合は、必ずしも喪中はがきを出す必要はありませんが、故人との関係性やご自身の気持ち次第で判断して問題ありません。
2. デザインや色味に配慮する
喪中はがきは、派手なデザインやカラフルな色使いは避けるのが常識です。白やグレー、淡い藤色など、落ち着いた色調を選びましょう。背景に蓮の花や菊など、控えめな花柄や和紙風のテクスチャを使ったテンプレートも人気です。
3. 慶事を思わせる表現やモチーフはNG
おめでたい印象を与える松竹梅や鶴亀などの絵柄、また「おめでとう」「明けましておめでとうございます」などの言葉は、喪中はがきにはふさわしくありません。
代わりに、「年始のご挨拶を控えさせていただきます」「生前のご厚情に感謝申し上げます」などの慎ましく丁寧な表現を用いるのが適切です。
喪中はがきを送る時期
喪中はがきは、受け取った相手が年賀状の準備を始める前に届くことが重要です。そのため、11月中旬〜12月初旬にかけて投函するのが理想的です。
12月に入ってから慌てて出すと、相手がすでに年賀状を作成・投函してしまっている場合もあります。特に印刷業者などに年賀状を頼む人は、早ければ10月末から準備を始めることもあるため、できるだけ早めに手配するのがマナーといえるでしょう。
なお、年末ぎりぎりに訃報があった場合や、やむを得ず年内に出せなかった場合は、年明けに「寒中見舞い」としてお知らせをする方法もあります。
喪中はがきの文面の書き方
喪中はがきの文面は、受け取る相手に配慮した丁寧で簡潔な文章が求められます。形式に則りながらも、自分らしい言葉で気持ちを伝えることが大切です。ここでは、基本構成から言葉遣いの注意点まで詳しく解説します。
文面の基本構成
喪中はがきの文面は、以下のような5つの要素で構成するのが一般的です。
- 年賀欠礼の挨拶
冒頭で「年始のご挨拶を控えさせていただきます」など、年賀状を出さない旨をまず伝えます。 - 故人が亡くなったことの報告
「本年○月に○○が永眠いたしました」など、亡くなった方とその時期を簡潔に述べます。 - 故人との続柄や時期
「母 ○○が 享年○歳にて…」などと続柄・年齢などを伝えるとより丁寧です。伝えたくない場合は省略しても構いません。 - 日頃の感謝と今後の挨拶
「生前中に賜りましたご厚情に深く感謝申し上げます」「今後とも変わらぬお付き合いのほどお願い申し上げます」などの感謝の一文を添えます。 - 日付や差出人情報(任意)
文末に「令和◯年◯月」などの日付や、差出人の氏名・住所などを記載することで、より正式な印象になります。
【構成例】
喪中につき年末年始のご挨拶を失礼させていただきます
〇月に父 ○○が永眠いたしました
本年中に賜りましたご厚情に心より御礼申し上げます
来年も変わらぬご交誼のほどお願い申し上げます
令和◯年◯月
簡潔で伝わる文章とは
喪中はがきは、気持ちを表現しつつも、あくまで事実を簡潔に伝えることが大切です。特別に美しい表現や華やかな言い回しは必要ありません。
- 感情を押しつけないよう、淡々と事実だけを記すのがマナー。
- 長文は避け、3~5行程度にまとめるのが理想。
- 読む相手に配慮し、「○○いたしました」「○○のため控えさせていただきます」など、柔らかく丁寧な表現を心がけましょう。
特に、仕事関係者やあまり親しくない相手に対しては、形式にのっとった無難な文面にするのが安心です。
適切な言葉遣いについて
喪中はがきでは、言葉の選び方にも注意が必要です。お祝いごとや慶事を連想させる言葉は避けましょう。
使用を避ける言葉
- 「おめでとう」
- 「明けましておめでとうございます」
- 「賀正」「謹賀新年」などの新年の挨拶全般
喪中にふさわしい言葉
- 「逝去」「永眠」「他界」などの婉曲表現
※「死去」「死亡」は直接的すぎて避けるのが無難 - 「本年○月に○○が永眠いたしました」
- 「つきましては年始のご挨拶をご遠慮申し上げます」
- 「日頃のご厚情に感謝申し上げます」などの感謝の言葉
このような言い回しを使うことで、相手への配慮と、喪中にふさわしい控えめな印象を与えることができます。
句読点の使い方
意外と見落としがちなのが、「句読点(、。)を使わない」という慣例です。
これは、日本の礼状文化に由来するもので、「終わりを打たない」ことが、故人との縁が続いているという意味合いを持つとされています。また、筆書きや毛筆文化では句読点を打たないのが一般的だったことも背景にあります。
現在では絶対のルールではないものの、喪中はがきの文面では句読点を使わないのが基本的マナーとされているため、テンプレートや例文を参考にしながら、自然な形で句読点を省いた書き方を意識するとよいでしょう。
喪中はがきのメッセージ例文
喪中はがきの文面は、送る相手との関係性によってトーンや言葉遣いを調整することが大切です。ここでは、友人や親しい方、ビジネス関係者など、それぞれの関係性に応じた具体的な文例をご紹介します。場面ごとの文例を参考に、自分の気持ちに合った文章を作るヒントにしてください。
友達に送るカジュアルな文例
気心の知れた友人には、堅苦しくなりすぎず、少しくだけた表現でもマナーを守れば問題ありません。
親しみやすく、誠実な印象を与える文面が望ましいです。
今年〇月に母○○が永眠いたしました
つきましては新年のご挨拶を控えさせていただきます
これからも変わらぬお付き合いをよろしくお願いいたします
ポイント:
- 「永眠」という言葉で柔らかく事実を伝えています
- 友人関係なら「これからもよろしくね」などの言葉を加えても自然です
親しい友人への丁寧な文例
親しい関係でも、丁寧な文面で気持ちをきちんと伝えたいときには、ややフォーマルな表現を用いるのがおすすめです。
本年〇月に父○○が他界いたしました
年末年始のご挨拶を控えさせていただきますことをご容赦ください
日頃より賜っておりますご厚情に深く感謝申し上げます
ポイント:
- 「ご容赦ください」などの丁寧語で相手に敬意を表現
- 「日頃のご厚情」という言い回しで感謝の気持ちを表しています
近親者を亡くした場合のメッセージ
祖父母や配偶者、兄弟姉妹など、深い身内の死を知らせる場合は、気持ちを整えたうえで、落ち着いたトーンの文章にするのが適切です。
本年〇月に祖母○○が永眠いたしました
つきましては年末年始のご挨拶を控えさせていただきます
皆さまには穏やかな新年を迎えられますよう心よりお祈り申し上げます
ポイント:
- 相手の年始を祝う直接的な表現は避けつつ、心配りのある言葉で締めくくる
- 「皆さまには良いお年を」と言い換えたい場合に使いやすい表現です
ビジネスシーンでの例文
会社関係や取引先など、ビジネス上の相手には格式と配慮のある文面が求められます。個人的な感情を表に出しすぎず、一定のフォーマルさを保ちましょう。
喪中につき年末年始のご挨拶を失礼させていただきます
本年〇月に母○○が永眠いたしました
今後とも変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます
ポイント:
- 「喪中につき〜」という冒頭はビジネス定型としてよく使われます
- 「ご厚誼を賜る」はビジネスシーンでの丁寧な締めくくりとして最適
どの文例も、句読点は使用せず、淡々とした中に配慮を込めた表現になっていることが共通の特徴です。文章量は3〜5行を目安にまとめ、読み手に負担をかけない簡潔な構成を意識しましょう。
故人との関係に応じたメッセージ
喪中はがきの文面は、誰を亡くしたのかによって言葉選びが微妙に変わってきます。特に、亡くなった方が父母・祖父母・配偶者・友人など、関係の深さや立場が異なる場合は、受け取る側の印象や気持ちへの配慮が必要です。以下に関係別の例文とその解説をご紹介します。
父母への喪中はがき例文
父母を亡くした場合は、最も一般的な喪中はがきの形式です。文面は形式的になりすぎず、親を失った悲しみを静かに伝える言葉遣いが好まれます。
父○○が本年○月に永眠いたしました
つきましては新年のご挨拶を控えさせていただきます
生前に賜りましたご厚情に深く感謝申し上げます
補足ポイント:
- 「永眠いたしました」は柔らかい印象を与える定番表現です。
- 「生前に賜りました〜」を添えると、相手への感謝の気持ちも伝えられます。
- 母の場合も文面はほぼ同様に使えます。
祖父母への喪中はがき例文
祖父母は二親等以内の親族にあたるため、基本的には喪中はがきを出します。ただし、相手との関係や地域の慣習によっては、省略するケースもあります。出す場合は、落ち着いた丁寧な文面にするのが基本です。
祖母○○が○月に他界いたしました
年始のご挨拶は控えさせていただきますことをご了承ください
皆さまのご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます
補足ポイント:
- 「他界」はやや直接的ですが、一般的に使われる表現です。
- 最後の一文で相手の健康や幸せを祈る形にすると、穏やかで前向きな印象になります。
配偶者を亡くした場合のメッセージ
配偶者の死を知らせる喪中はがきは、非常にプライベートな内容です。そのため、形式を守りながらも、心情がにじむような穏やかな文面にするとよいでしょう。
妻○○が○月に永眠いたしました
心よりご厚情に御礼申し上げます
新年のご挨拶は差し控えさせていただきますことをご了承くださいますようお願い申し上げます
補足ポイント:
- 配偶者の死は受け取る側にも大きな衝撃を与えることがあるため、感情を抑えつつも誠実な表現を心がけましょう。
- 「御礼申し上げます」や「お願い申し上げます」で丁寧さを補うと、フォーマルさが保てます。
友人を亡くした際の文例
友人の死を理由に年賀欠礼をする場合は、個人的な感情が反映された文面になります。相手にもその事情をしっかりと伝えるため、慎重な表現を選びましょう。
友人○○が○月に逝去いたしました
大変悲しい出来事のため、新年のご挨拶を控えさせていただきます
どうか事情をご賢察のうえ、ご了承くださいますようお願い申し上げます
補足ポイント:
- 「逝去」は尊敬語にあたるため、友人や目上の方に対して使えます。
- 友人の死を理由に年賀欠礼をするのは義務ではありませんが、親しかったことを示したい場合にはふさわしい文面です。
以上のように、喪中はがきのメッセージは「誰を亡くしたか」によって表現が少しずつ異なります。ただしどの場合でも共通して言えるのは、悲しみを静かに受け止めつつ、相手への配慮と感謝を丁寧に伝えることです。
喪中はがきのサンプルとデザイン
喪中はがきは、内容だけでなくデザインにも品位や配慮が求められる特別なはがきです。派手な色使いや装飾を避け、落ち着いた雰囲気でまとめることが大切です。ここでは、印刷用のデザイン例や手書きの工夫、近年増えているLINEやメール通知についても解説します。
印刷用のサンプル紹介
喪中はがきの印刷デザインは、白地や淡いグレーを基調としたシンプルなものが主流です。文字は通常、薄墨を思わせるグレーや黒を用い、華美な装飾は避けるのが基本です。
近年では、以下のようなサービスで無料テンプレートを使って簡単に作成・注文できる印刷サイトが人気です。
主な印刷サービス例:
- 郵便局の総合印刷サービス:公式テンプレートが豊富で安心感あり
- しまうまプリント/ネットプリントジャパン/ラクスル:価格重視派におすすめ。シンプルデザイン多数
- カメラのキタムラ:写真入りや文例カスタマイズが可能なサービスあり
よく使われるモチーフ:
- 蓮の花、菊、和紙模様、霞(かすみ)などの控えめなイラスト
- 差出人名の下に「喪中につき年始のご挨拶を控えさせていただきます」などの定型文を配置
※印刷を依頼する際は、宛名印刷の有無や投函代行サービスの有無も確認しましょう。
手書きの魅力とコツ
印刷では出せない温かみや誠意が伝わるのが手書きの魅力です。特に親しい間柄や高齢の親族などには、あえて手書きで送ることで丁寧な印象を残すことができます。
手書きのコツ:
- 筆ペンや毛筆風のペンを使うと、柔らかく上品な印象に
- 文面は印刷用の例文を参考にしつつ、相手に合わせて一言添えると好印象
- 文字はゆっくりと丁寧に。句読点は基本的に使わず、改行や空白で読みやすさを調整
例文の一言追加例:
本年○月に父○○が永眠いたしました
ご心配をおかけし申し訳ありません
今後とも変わらぬお付き合いのほどお願い申し上げます
LINEやメールでの通知方法
近年では、年賀状文化が縮小してきた影響で、LINEやメールでの喪中連絡を選ぶ方も増えています。特に年賀状のやりとりがない友人や、普段からSNS中心の連絡を取っている相手には、有効な選択肢となります。
書き出しに気をつけたい一文:
- 「突然のご連絡を失礼いたします」
- 「本来であればお葉書にてご挨拶すべきところですが…」
文面の注意点:
- 相手との関係性を踏まえ、過剰に砕けた表現や顔文字などは避ける
- 必ず、「年賀状は辞退します」「新年の挨拶は控えます」などの主旨を明確にする
年賀欠礼としてのデザインポイント
「喪中はがき=年賀欠礼状」は、年賀状の代わりに出すものです。したがって、デザイン面においても華美にならず、あくまで落ち着きと節度を重視する必要があります。
デザインの基本方針:
- 背景:白・淡いグレー・生成色・和紙風のテクスチャ
- 文字:黒または灰色で、楷書・明朝体が一般的
- モチーフ:蓮の花・菊・水引の一部など、控えめな和風素材
- レイアウト:文面中央に「喪中につき年始のご挨拶を控えさせていただきます」などの主文を配置
NGなデザイン例:
- カラフルなイラストや写真(特に笑顔の集合写真など)
- 金や赤の文字
- ポップ体などのカジュアルなフォント
喪中はがきのデザインは、「故人への敬意」と「相手への配慮」の両立が重要です。内容だけでなく、見た目や質感にも心を配ることで、静かで丁寧な気持ちがより深く伝わります。
喪中通知の送り方と注意点
喪中はがきは、ただ印刷して出すだけでなく、「いつ・どのように送るか」「どこまで伝えるべきか」など、送付方法にも細かなマナーや配慮が必要です。相手に誤解や不快感を与えないように、送り方とその注意点をきちんと押さえておきましょう。
投函する際のポイント
喪中はがきは、通常のはがき形式で送るのが一般的です。封書では形式ばりすぎてしまい、かえって重たくなってしまうことがあります。
使用するはがきの種類:
- 官製はがき(通常はがき):郵便局で購入可能。63円切手があらかじめ印刷されているタイプ。
- 私製はがき+切手貼付:オリジナルの喪中テンプレートを自宅印刷する場合に使用。※切手は63円の通常切手または弔事用切手(落ち着いた色味の花柄など)がおすすめです。
注意点:
- 弔事にふさわしくない切手(派手な絵柄など)は避け、控えめで上品なものを選ぶと安心です。
- 投函は年賀状準備の前、11月中旬〜12月上旬が理想。遅くとも12月中旬までには届くようにしましょう。
到着の確認と返信の考え方
喪中はがきに対して、受け取った側から返信が来ることはあまりありません。返信がないからといって、無視されたということではなく、形式上のものと捉えるのが一般的です。
ただし、どうしても届いたか不安な場合は、以下のように控えめな確認方法を取るのがよいでしょう。
控えめな確認の例:
- 電話で「年末のご挨拶を控えた件、届いていましたでしょうか」と一言尋ねる
- メールやLINEの場合は、既読確認や返信の有無で判断する
※くれぐれも、確認を強要したり、催促のような口調にならないよう注意しましょう。
マナー違反を避けるための注意点
喪中はがきの目的は、丁寧な年賀欠礼と故人の報告です。その目的を損なわないよう、次のポイントに気をつけましょう。
よくあるNG行為:
- 投函が遅れすぎる:年賀状が届いた後に喪中はがきが届くと、相手に気まずい思いをさせてしまいます。
- 故人に関する情報が曖昧:年齢や続柄の記載ミスは失礼にあたるため、事前によく確認を。
- 相手の名前を間違える:とても失礼にあたるため、宛名・漢字は特に慎重にチェックしましょう。
その他の注意点:
- 宛名面に「様」をつけ忘れない
- 差出人情報を省略しすぎず、連絡先を明記するのも丁寧な印象につながります
香典辞退の伝え方
喪中はがきに、香典の辞退意思を明記しておくことで、相手に無用の心配をかけない配慮になります。文末にさりげなく一文添えるだけで十分です。
例文:
香典等につきましては固くご辞退申し上げます
ご厚意のみありがたく頂戴いたします
このように書くことで、相手に「送らなくてはいけないのでは」と思わせることなく、負担を軽減する配慮が伝わります。
喪中はがきは、「こちらの事情を知らせる」だけでなく、相手の気持ちにも配慮した一枚を届けることが本当の目的です。内容・言葉・タイミングに丁寧さを込めて、失礼のないやり取りを心がけましょう。
喪中はがきに使える言葉とフレーズ
喪中はがきでは、直接的な感情を表現するのではなく、節度ある言葉選びによって「感謝」「配慮」「故人への想い」を静かに伝えることが大切です。ここでは、特に使用頻度の高い「感謝の表現」「故人を偲ぶ言葉」「ご厚情へのお礼」について、文例とその使い方のコツを紹介します。
伝えたい感謝の言葉
感謝の言葉は、喪中はがきの文末に添えることで、形式的な文章に温かみと人間味を加えることができます。
よく使われる表現:
- 「日頃のご厚情に深く感謝申し上げます」
→ ビジネス関係や広く感謝を伝えたいときに最適 - 「平素のご厚誼に御礼申し上げます」
→ やや格式高めで、取引先や年長の方にも使いやすい表現
類似フレーズの例:
- 「平素より格別のご厚情を賜り、心より御礼申し上げます」
- 「旧年中はひとかたならぬお付き合いをいただき、感謝申し上げます」
ポイント:
これらの表現は、フォーマルな印象を保ちつつ、相手との関係性に応じて柔らかく調整が可能です。手紙文化に慣れていない方でも、テンプレートとして安心して使えます。
故人を偲ぶ言葉の選び方
喪中はがきの文面には、故人についての想いを直接的に語ることは少ないですが、控えめに偲ぶ言葉を入れることで、気持ちが自然に伝わります。
よく使われる表現:
- 「生前は格別のご厚情を賜り誠にありがとうございました」
→ 相手が故人と交流があった場合に最適 - 「故人も皆様のご厚意に感謝していたことと存じます」
→ 故人の人柄を思わせる、優しい印象の文面
その他の例:
- 「故人に代わり厚く御礼申し上げます」
- 「在りし日のお心遣いに感謝申し上げます」
- 「ご生前中に賜りましたご厚誼に深く感謝申し上げます」
ポイント:
故人との関係性が濃い相手には、これらの言葉を一文添えるだけで、相手の記憶や気持ちに寄り添う効果が期待できます。
ご厚情へのお礼の表現
相手からの心配や気遣いに対して、お礼やお詫びを添えることで、丁寧さと配慮を感じさせる文章に仕上がります。
よく使われる表現:
- 「皆様のご厚情に、心より御礼申し上げます」
→ あらゆる相手に使える万能な感謝の一文 - 「ご心配をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます」
→ 相手が何か気を遣ってくれた可能性がある場合に有効
その他の例:
- 「何かとお気遣いを賜りましたこと、深謝申し上げます」
- 「ご丁重なるご配慮を賜り、感謝の気持ちでいっぱいです」
- 「このたびは何かとご心配をおかけし、恐縮に存じます」
ポイント:
喪中はがきにおけるお礼は、相手の善意を認めて感謝を伝えるための礼節表現です。特別な返礼ではなく、あくまでも言葉で気持ちを整えて伝えることが目的となります。
文章に心を込めるために
喪中はがきに使う言葉は、定型である一方で、表現の一つひとつに意味と気遣いが込められています。そのため、テンプレートに頼りながらも、相手や自分の状況に応じて一言加えたり、表現を選び直すことで、より伝わる文章になります。
喪中はがきの作成に役立つリソース
喪中はがきを作成する際には、「文章の内容」だけでなく、デザイン・印刷方法・郵送の手配までをスムーズに進めることが大切です。最近では誰でも簡単に作成できるテンプレートやサービスが多数提供されており、用途や予算に応じて選べます。ここでは、便利なテンプレート、印刷の比較、発送手続きについて詳しく解説します。
無料テンプレートの紹介
喪中はがきの文例やデザインテンプレートは、無料で使える信頼性の高いサービスが多数存在します。以下におすすめの提供元を紹介します。
■ 郵便局公式サイト
「郵便年賀.jp」の喪中テンプレートコーナーでは、シンプルで落ち着いたデザインが多数掲載されています。WordやPDFでダウンロード可能で、文面のカスタマイズも可能です。
■ 民間印刷サービス(例:しまうまプリント、ラクスル、カメラのキタムラなど)
- デザインのバリエーションが豊富
- オンライン上で文面編集・プレビュー・宛名印刷まで一括対応
- 早期割引やクーポンがある時期を狙うとお得に注文可能
■ Microsoft Word の無料テンプレート
Microsoft公式やOfficeテンプレート集には、喪中はがき用のフォーマットが登録済です。家庭用プリンタで手軽に印刷したい人におすすめです。
✅ ワンポイント
Wordテンプレートを使用する場合、フォントは明朝体や楷書体などの落ち着いた書体を選ぶと印象が良くなります。
印刷方法と料金の比較
印刷方法は、依頼型か自宅印刷かで大きく分かれます。コスト・デザイン性・操作の簡便さなど、目的に合わせて選びましょう。
| サービス名 | 印刷費用(目安) | 特徴 |
|---|---|---|
| 郵便局の喪中はがき | 約2,000円〜(10枚程度) | 全国対応。オンライン注文可。投函代行も可能 |
| ラクスル | 約1,500円〜 | テンプレート豊富。編集しやすく早期割引あり |
| しまうまプリント | 約1,500円〜 | 高品質・納期早め。写真入り喪中はがきも可 |
| 自宅印刷 | 実費(インク+用紙代) | 自由度が高くコストも抑えられる。プリンタが必要 |
✅ 印刷代とは別にはがき代(1枚63円)と送料・オプション費用がかかる場合があります。
宛名印刷や投函代行を希望する場合は、注文時にオプション料金を確認しましょう。
郵便局での発送手続き
作成した喪中はがきの発送方法は、通常のはがきと同様にシンプルです。
■ 郵便局窓口での投函
最寄りの郵便局に直接持参して投函可能です。大量に出す場合や心配なときは、窓口で確認しながら発送手続きを行うと安心です。
■ ポスト投函でも問題なし
通常の郵便ポストに投函してOKです。投函後の追跡などはできませんが、普通郵便として処理されます。
■ 使用する切手について
- 喪中用の特別な切手は不要。通常の63円切手で問題ありません。
- ただし、気持ちの面で「弔事用切手(花柄などの落ち着いたデザイン)」を使用する人もいます。郵便局で購入可能です。
喪中はがきの作成は、文章だけでなく「いつ・どうやって届けるか」までを考えることが重要です。便利なテンプレートや印刷サービスを活用することで、短時間でも誠意のこもった一枚を用意することができます。自分に合った方法で、失礼のない丁寧な対応を心がけましょう。
以下に、「喪中見舞いとの違い」についての各項目を丁寧にボリュームアップした内容をご提案します。喪中はがきとの違いや、喪中見舞いのマナー・品選びの注意点まで詳しく網羅しています。
喪中見舞いとの違い
喪中はがきを受け取ると、「何か返した方がよいのか」「どう対応すれば失礼がないのか」と悩む方も少なくありません。その際に役立つのが“喪中見舞い”という文化です。ここでは、喪中見舞いの定義や喪中はがきとの違い、贈る際のマナーについて詳しく解説します。
喪中見舞いの定義
喪中見舞い(もちゅうみまい)とは、喪中はがきを受け取った側が、その内容に対して相手を気遣い、慰めや励ましの気持ちを込めて贈る挨拶状や贈り物のことです。
喪中の知らせを一方的に受け取るだけでなく、「心からお悔やみ申し上げます」という気持ちを、ささやかな形で返したいときに選ばれる方法です。形式ばったものではありませんが、思いやりを込めた心遣いとして、近年は見直されている慣習のひとつでもあります。
喪中はがきとの使い分け
混同されがちな喪中はがきと喪中見舞いですが、それぞれの役割は明確に異なります。
| 種類 | 送る側 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 喪中はがき | 喪中になった人(差出人) | 年賀状を辞退する連絡・故人の訃報の通知 |
| 喪中見舞い | 喪中はがきを受け取った人 | 相手の喪中を気遣い、お悔やみや励ましを伝える |
喪中はがきは「お知らせ」であり、喪中見舞いはそれに対する「お見舞い・気遣いの返答」という位置づけです。喪中はがきに対して年賀状を出すことはNGとされていますが、喪中見舞いはマナーに反するどころか、むしろ丁寧な対応とされます。
喪中見舞いのマナー
喪中見舞いには明確な形式はありませんが、いくつかのマナーや注意点があります。
■ 時期に注意する
喪中見舞いは年賀状の代わりではないため、年末年始を避けて送るのが基本です。
喪中はがきを受け取った直後の12月中旬〜下旬、または年明けの松の内(1月7日頃)以降、寒中見舞いとして送るのもよいとされています。
■ 贈り物の形式
- 不祝儀袋や水引のついたのし紙は不要です。
- 包装紙や箱に直接のしを付けず、控えめなラッピングで十分です。
- 表書きが必要な場合は、「喪中御見舞」または「御見舞」とするのが一般的。
■ 適した贈り物の例
- 高級すぎず、かつ実用的なものを選ぶと◎
- 日持ちのするお茶・お菓子・乾物・ジュースの詰め合わせなどが人気
- 食べ物以外では、タオル・石鹸・カタログギフトなども好印象です
- 故人との関係が深い場合は、香典代わりの金額を添えても良いが、必要に応じて確認を
メッセージ例(同封する場合)
喪中見舞いには、簡単でも構いませんので、手書きのメッセージカードや短い手紙を添えると気持ちがより伝わります。
このたびはご家族のご不幸を伺い、心よりお悔やみ申し上げます。 年末のご挨拶を差し控えさせていただくにあたり、ささやかではございますが、お見舞いの品をお届けいたします。 寒さ厳しき折、ご自愛くださいませ。
喪中見舞いは、マナーの押し付けではなく、相手の悲しみに寄り添う気持ちを形にする日本ならではの習慣です。形式にとらわれず、思いやりを大切にすることで、より深く信頼関係を築くことができます。
まとめ|心を込めた喪中はがきで丁寧に想いを伝えましょう
喪中はがきは、故人を偲びながらも、相手への思いやりを形にする大切な挨拶状です。形式や言葉選びに不安を感じるかもしれませんが、基本的なマナーを押さえ、例文を参考にすることで、誰でも失礼のない一枚が作成できます。
喪中はがきは「年賀欠礼」の意味だけでなく、自分の気持ちを整えるひとつの節目でもあります。心静かに文面を考えながら、あなたらしい言葉で丁寧に想いを届けてください。本記事がその手助けとなれば幸いです。