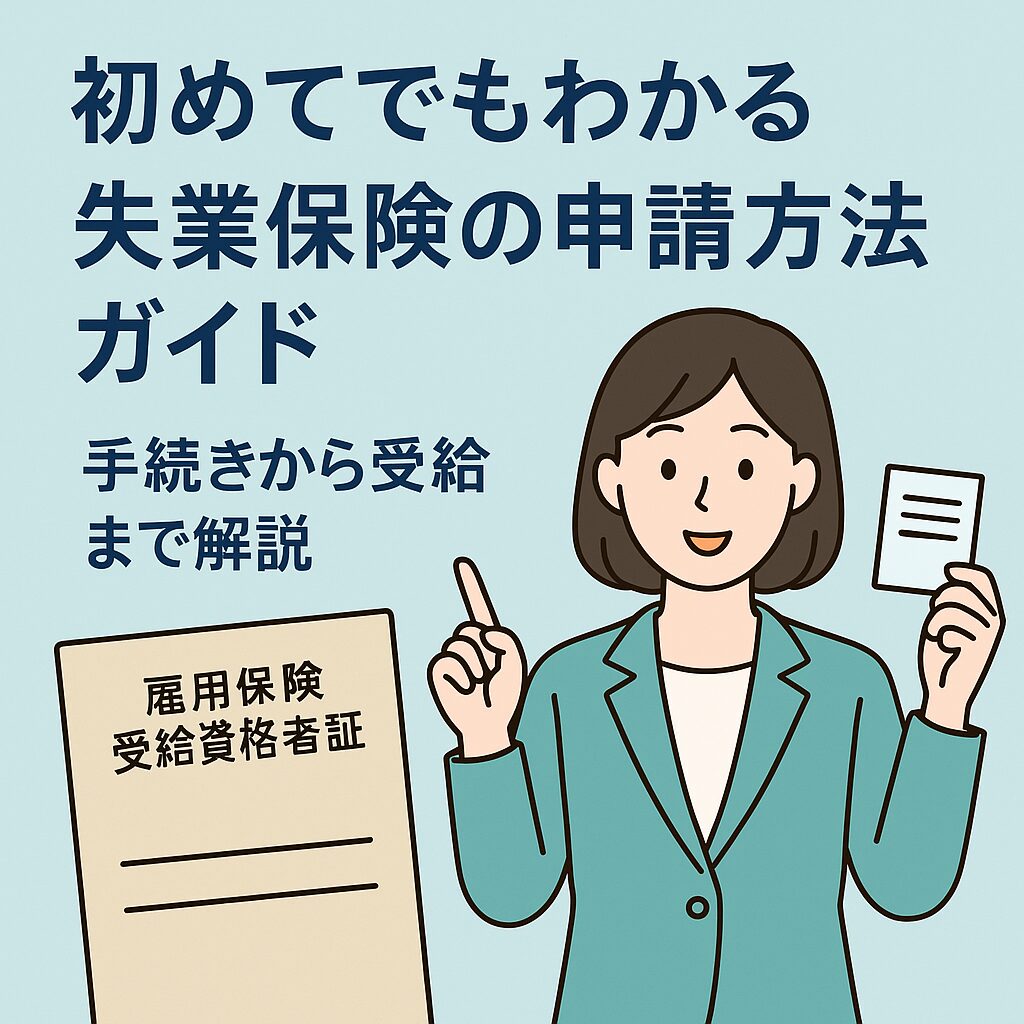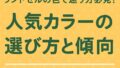失業してしまったけれど、失業保険ってどうやって申請すればいいの?」そんな不安を抱える方は少なくありません。慣れない手続きや書類の準備に戸惑い、受給までの流れがわからず悩む人も多いのが現実です。
本記事では、失業保険の申請方法を初めての方にもわかりやすく解説します。必要書類、ハローワークでの流れ、受給までのポイントをやさしく丁寧に紹介。これを読めば、迷わず一歩を踏み出せます。
失業保険の申請方法とは?
失業保険は、失業した人が次の仕事を見つけるまでの間、一定の収入を得るための制度です。正しく手続きを行えば、再就職活動中も安心して生活できる支えとなります。
特に初めて申請する人にとっては不安も多いかもしれませんが、申請手順や必要書類を事前に知っておくことで、スムーズに進めることができます。以下では、失業保険の制度の基本から、具体的な手続きのポイントまでを詳しく解説します。
失業保険の基本と制度について
失業保険とは、雇用保険制度に加入していた人が失業した際に支給される給付金で、正式名称は「基本手当」といいます。目的は、失業中の生活を一定期間支援し、安心して再就職活動ができるようにすることです。受給にはいくつかの条件がありますが、制度を理解し、正しく申請すれば、転職活動の大きな支えになります。
この制度は厚生労働省が所管し、全国のハローワークを通じて運用されています。給付を受けるには、失業していることだけでなく、「就職の意思と能力があり、積極的に求職活動をしていること」が必要です。
雇用保険の仕組みと重要性
雇用保険は、日本の社会保険制度の一部で、労働者が働けなくなったときに収入の空白期間をカバーするための公的保険制度です。会社員やパートタイマー、契約社員など、所定の労働時間を満たす多くの労働者が対象となっています。
保険料は、労働者と事業主がそれぞれ一定割合を負担しており、毎月の給与から自動的に天引きされています。これにより、失業時だけでなく、育児休業や介護休業、教育訓練の受講時にも支援を受けることができます。
この制度は、労働者の生活を守るセーフティネットとして非常に重要であり、安定した雇用環境を築く上でも欠かせない存在です。
失業手当の種類と給付内容
失業保険の給付にはいくつかの種類があります。主なものは以下の通りです。
-
基本手当:最も一般的な給付で、失業中の生活を支えるために支給されます。受給期間や支給額は、年齢や離職理由、保険加入期間によって異なります。
-
再就職手当:失業給付を受け取っている途中で再就職した場合、条件を満たせば、残りの支給予定額の一部がまとめて支給される制度です。
-
就業促進定着手当:再就職後6か月以上同じ職場で働き続けた場合に支給される、再就職支援を目的とした手当です。
-
教育訓練給付金:指定された職業訓練や資格取得講座を受講した際に、受講費用の一部が補助されます。
これらを組み合わせて活用することで、生活の安定とスキルアップの両立が図れます。
失業保険の申請に必要な書類
失業保険の申請時には、以下の書類をハローワークに提出する必要があります。準備が整っていないと手続きに時間がかかるため、退職後は早めに確認しましょう。
-
離職票(1と2):会社から退職後に発行されます。給付内容の算定に必要な書類です。
-
マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類(運転免許証・健康保険証など):本人確認および情報照合に必要です。
-
印鑑(認印):書類への捺印用。シャチハタは避けた方が無難です。
-
証明写真(3cm×2.5cm)2枚:求職申込書や雇用保険受給資格者証などに貼付します。スピード写真でも可。
-
預金通帳またはキャッシュカード:失業手当の振込先口座の確認に使用します。
これらを一式そろえて、最寄りのハローワークで申請を行います。わからない点があれば、窓口で丁寧に案内してくれるので安心です。
申請手続きの流れ
失業保険を受給するためには、ハローワークでの申請手続きが必要です。失業が決まったら、なるべく早く動き出すことが大切です。ここでは、実際に申請が始まるまでの一連の流れを詳しく解説します。
ハローワークへの訪問手順
まずは、自宅住所を管轄する最寄りのハローワークを確認しましょう。雇用保険の申請は、どこのハローワークでも可能というわけではなく、「居住地に対応する窓口」での申請が原則です。
初回訪問時には、以下のことを行います。
-
離職票の提出
-
求職申込書の記入・提出
-
本人確認書類の提示
-
ハローワークカード(求職者登録証)の発行
これらが終わると、「雇用保険説明会」の案内を受け取ります。この説明会では、制度の概要や今後の流れ、注意点について職員から詳しい説明があります。参加は原則必須であり、欠席すると受給スケジュールに影響が出ることもあります。
申請書類の提出方法
ハローワークの窓口では、あらかじめ準備しておいた離職票(1・2)や本人確認書類、通帳などを提出します。担当者による確認ののち、正式に雇用保険受給資格の有無が判断されます。
求職申込書の記入では、希望職種や就業条件(勤務時間・勤務地など)を詳しく記入する必要があり、今後の求人紹介にも影響する重要な項目です。
また、書類提出が完了したら、「初回認定日」と「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が交付されます。これらは今後の手続きにおいて非常に重要な書類なので、大切に保管しておきましょう。
認定日とは?申請後の流れ
「認定日」とは、ハローワークが求職者の就労状況を確認し、「失業の状態にある」と判断したうえで失業手当を支給するための日です。原則として4週間に1回のペースで指定され、認定日のたびにハローワークへ出向く必要があります。
認定日当日は、以下のことを行います。
-
失業認定申告書の提出
-
求職活動の報告(原則2回以上)
-
職員との面談(簡単な内容)
この認定がなければ、失業給付は支給されません。認定日に無断欠席した場合や、申告内容に不備がある場合は、支給が遅れたり打ち切られたりすることもあるため、注意が必要です。
失業保険の受給開始までの期間
実際に給付金の振り込みが始まるまでには、一定の準備期間があります。おおよそのスケジュールは以下の通りです。
-
申請直後の7日間は「待期期間」
→ この間はどんな事情があっても給付はされません。 -
自己都合退職の場合は、さらに「2〜3か月の給付制限期間」
→ いわゆる“クールタイム”として、給付開始が遅れる仕組みです。 -
会社都合退職であれば、待期期間終了後すぐに支給が開始されることも
つまり、自己都合退職の場合、申請から最初の給付金振込までに約2〜3か月かかるケースが一般的です。その間の生活資金の確保や家計の見直しが必要になります。
また、初回の給付金は「認定日から約1週間後」に指定口座に振り込まれます。2回目以降も基本的に同様のペースで支給されます。
失業保険をもらうための条件
失業保険(基本手当)は、誰でも自動的にもらえるわけではありません。一定の要件を満たし、ハローワークでの手続きを正しく行うことで初めて受給が可能になります。この章では、失業保険を受け取るために必要な「基本条件」と「注意点」について詳しく解説します。
自己都合退職と会社都合退職の違い
失業保険の給付条件は、退職理由によって大きく異なります。主に以下の2つに分類されます。
● 自己都合退職の場合
自己都合とは、「一身上の都合」で退職したケース(例:転職、体調不良、家庭の事情など)を指します。この場合、以下のような制限があります。
-
給付開始までに7日間の待期期間+2〜3か月の給付制限期間が設けられる
-
給付日数が短くなる傾向がある(例:90日間など)
● 会社都合退職の場合
倒産や人員整理、長時間労働やパワハラによる退職など、労働者の責任ではない理由での退職です。この場合は、次のようなメリットがあります。
-
給付制限がなく、待期期間終了後すぐに受給開始される
-
給付日数が自己都合より長く設定されることが多い(例:120〜330日)
特に「退職勧奨」や「契約更新の打ち切り」など、曖昧なケースでは、ハローワークが判断することになるため、証拠となる書類ややりとりの記録を残すことが重要です。
受給条件と資格者の要件
失業保険を受け取るには、次のような基本的な要件をすべて満たす必要があります。
-
雇用保険に12か月以上加入していること
離職日前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算で12か月以上あることが必要です。
※正当な理由があれば6か月で認められるケースもあり(倒産など) -
就労可能な健康状態であること
病気やけがで就労が難しい場合は「失業状態」とみなされず、給付対象外になります。
※療養中は健康保険の傷病手当金の対象になる可能性があります。 -
積極的に求職活動をしていること
実際に就職する意思と行動があることが前提です。認定日までに求職実績(求人応募・面接・職業相談など)が必要になります。 -
定められた期間内に申請を行うこと
原則として離職日の翌日から1年以内に給付日数を消化しなければなりません。遅れすぎると受給資格を失います。
受給開始のための待期期間
失業保険の申請後には、一律で7日間の待期期間が設けられています。この期間中は、失業状態であるかどうかの確認期間とされ、一切の給付は行われません。
また、自己都合退職者の場合は、この待期期間に加えて2〜3か月の給付制限期間が追加されます。これは、「すぐに再就職する意思がなかったのではないか」と見なされるためで、制度上のルールとなっています。
給付制限期間中も、認定日の出席や求職活動の実績提出は必要です。サボると更なる延長や資格喪失のリスクがあります。
受給資格を失う条件とは?
失業保険の受給中には、守らなければならないルールがあります。以下の行為をすると、給付の停止・取消しや返還命令が下されることがあります。
-
虚偽の申告や報告漏れ
→ アルバイトをしていたのに申告しなかった、就職しても報告しなかった、など -
認定日の無断欠席
→ 正当な理由なく欠席すると、その期間の給付が無効になります -
再就職後の未申告
→ 給付金を受け取りながら就職していた場合、不正受給と見なされ返金+罰則の対象に -
求職活動を行っていないこと
→ 定期的な就職活動の実績がないと、失業の状態とみなされず給付対象外になります
失業保険はあくまで「就職を目指す人を支援する制度」であることを念頭に置き、ルールを守って正しく活用しましょう。
失業手当の計算と支給額
失業保険(基本手当)で実際にどれくらいの金額が支給されるのかは、退職前の給与や年齢、雇用保険の加入期間などによって大きく変わります。この章では、基本手当の金額の計算方法や給付日数の考え方、特例措置などについて詳しく解説します。
日額の算出方法と賃金日額の関係
失業手当のベースとなるのが「賃金日額」という指標です。これは、退職前6か月間に支払われた賃金の総額を、出勤日数で割った金額です(※ボーナスなどを除く)。
【賃金日額の算出例】
月収25万円 × 6ヶ月 = 150万円
150万円 ÷ 180日(約6か月)= 約8,333円(賃金日額)
この賃金日額に一定の支給率(50〜80%)をかけたものが、「基本手当日額」となります。
- 低所得者ほど高い支給率(最大80%)
- 高所得者になるほど支給率は下がる(最低50%)
つまり、収入が少ない人ほど手厚く支援される仕組みになっています。
受給額の上限と下限
基本手当日額には、年齢ごとに上限と下限が定められており、高所得者でも一定額以上は支給されません。
※以下は令和6年度(2024年度)の例(変動あり)
| 年齢区分 | 上限額(1日あたり) |
|---|---|
| 29歳以下 | 約6,885円 |
| 30歳〜44歳 | 約7,615円 |
| 45歳〜59歳 | 約8,370円 |
| 60歳〜64歳 | 約7,186円 |
また、最低額は概ね2,000円台前半〜3,000円台が目安です。
※詳細は年度ごとの「厚生労働省の告示」を確認しましょう。
給付日数とその計算方法
失業保険の給付日数(何日分もらえるか)は、以下の3要素で決まります。
- 被保険者であった期間(加入年数)
- 離職時の年齢
- 離職理由(自己都合か会社都合か)
【例:自己都合退職の場合】
- 1年以上10年未満:90日間
- 10年以上20年未満:120日間
- 20年以上:150日間
【例:会社都合退職の場合】
- 30歳未満/1年以上:90〜180日間
- 45歳以上かつ20年以上:最大330日間
つまり、長く働いていた人や高年齢の人、会社都合退職の人ほど給付日数が多い傾向にあります。
失業給付の特例と注意点
災害・感染症拡大・倒産急増など、社会的な影響が大きい場合には、特例措置が設けられることがあります。
- コロナ禍では、給付日数の延長や給付制限の緩和が実施されました
- 地震や台風などの災害時にも、柔軟な対応が取られることがあります
ただし、これらの特例は自動的に適用されるわけではなく、申請が必要なケースも多いため、必ず厚生労働省やハローワークの公式情報をチェックすることが大切です。
申請に関するよくある質問
失業保険の申請手続きは慣れないことも多く、「どうすればいいの?」「これは大丈夫?」と不安を感じる方も多いのが現実です。ここでは、申請前後によく寄せられる疑問や注意点を取り上げ、解決のヒントをわかりやすくまとめました。
必要書類はどう集める?
失業保険を申請するためにはいくつかの書類が必要ですが、特に重要なのが離職票(1と2)です。
● 離職票の取得方法
退職後、会社(前職の雇用主)がハローワークに手続きを行った後に郵送されてくるのが一般的です。通常、退職から1週間〜10日程度で届きます。
-
もし2週間以上経っても届かない場合は、直接会社に連絡して催促しましょう。
-
会社が対応してくれない場合は、最寄りのハローワークに相談すると対応してくれることもあります。
● その他の書類
-
マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類(運転免許証など)
-
印鑑(認印) ※シャチハタ不可が原則
-
証明写真(3cm×2.5cm)×2枚
-
通帳またはキャッシュカード(振込先確認用)
提出書類に不備があると、申請が受理されず後日再訪になるケースもあるので、事前にチェックリストで確認しておくと安心です。
申請後のハローワークの役割
失業保険の手続きを行う場所として知られるハローワークですが、役割はそれだけではありません。再就職支援のための総合窓口として、さまざまなサービスを提供しています。
主な支援内容:
-
求人情報の提供(正社員・契約社員・パートなど)
-
職業相談・キャリアカウンセリング
-
履歴書・職務経歴書の添削サポート
-
模擬面接や就職セミナーの実施
-
職業訓練・スキルアップ講座の案内
特に、失業給付を受けている期間中は、求職活動実績の報告が必要になるため、ハローワークでの相談やセミナー参加は「実績」として認定される重要な行動です。
また、自治体や年齢層に応じた専門支援窓口(例:「わかものハローワーク」「マザーズハローワーク」など)もあるので、積極的に活用しましょう。
不正受給に関する注意と対策
失業保険は、就職を希望する人の生活を支える大切な制度です。しかし、その制度を故意または無意識に悪用してしまうと、不正受給とみなされ、重大なペナルティを受けることになります。
● 不正受給の主な例:
-
アルバイトや内職をしていたのに、申告せずに受給していた
-
就職が決まったにもかかわらず、失業状態と偽って申請を継続した
-
求職活動をしていないのに、虚偽の活動報告を提出
● ペナルティ:
-
不正に受け取った額の返還+最大2倍の追徴金
-
悪質と判断された場合は、受給資格の取り消しや刑事罰の対象になることも
● 対策・ポイント:
-
アルバイトをする際は事前にハローワークへ相談し、可否を確認する
-
就職が決まったら速やかに報告する
-
求職活動の記録は正確に、誠実に記入
「知らなかった」「うっかり」は通用しないため、不明点は都度ハローワークに確認を取りながら行動するのが安全です。
失業保険を利用する際のコラム
失業期間は、経済的な不安が募りがちな一方で、人生を立て直すための大事な準備期間でもあります。
受給中は、以下のような取り組みを意識すると、再就職後のスタートにもつながります。
-
生活費の見直し・家計の管理
-
資格取得やスキルアップ
-
自己分析とキャリアの棚卸し
-
ライフプランの見直し(働き方や価値観の整理)
また、心のケアも大切です。失業中は自信を失いがちですが、「自分を責めないこと」がまず第一歩です。ハローワークや地域の支援窓口、カウンセリングサービスなどをうまく利用しながら、前向きに次の一歩を準備する期間として活用しましょう。
再就職支援とサポート制度
失業保険は「単なる給付金」ではなく、再就職を後押しする支援制度の一環です。ハローワークでは、手当を支給するだけでなく、次のキャリアへ踏み出すための多彩なサポートが用意されています。この章では、求職活動の進め方や活用できる制度を詳しく紹介します。
求職活動の活動内容と提出方法
失業保険を受給するには、定期的な求職活動(就職を目指す行動)の実績提出が必要です。これは、ハローワークの「失業の認定」において最も重要なポイントとなります。
● 認められる主な求職活動例:
-
求人への応募(書類提出含む)
-
面接の実施(企業訪問含む)
-
ハローワークの職業相談への参加
-
再就職支援セミナー・就職面接会への参加
-
職業訓練の説明会や相談会への出席
● 活動実績の記録方法:
認定日に提出する「失業認定申告書」に、活動日・内容・企業名・結果などを記入します。証明書類の提出が必要な場合もあるため、求人票や応募メールの控え、セミナーの参加票などは保管しておきましょう。
原則として、認定期間(4週間)に2回以上の求職活動実績が必要です。ただし、初回認定時や特例措置がある場合は例外もあります。
教育訓練の活用と公共職業訓練
再就職を有利に進めるためには、スキルアップや資格取得も非常に有効です。ハローワークでは以下のような支援制度が用意されています。
● 教育訓練給付制度
厚生労働大臣が指定する講座(例:簿記、医療事務、介護福祉士、IT資格など)を受講すると、受講料の20〜70%が給付される制度です。
-
支給額の上限は年間10万円〜最大56万円(コースにより異なる)
-
雇用保険加入年数が1年以上(特例あり)
● 公共職業訓練(無料の職業訓練校)
失業者向けに行われる、無料または実費のみで受けられる職業訓練です。
-
事務・製造・介護・プログラミング・デザインなど多様なコースあり
-
受講中も失業給付が延長される「訓練延長給付」制度がある場合も
申し込みには事前相談・選考が必要ですが、職業訓練受講給付金(月10万円+交通費)の対象となることもあるため、積極的に活用を検討したい支援策です。
転職活動に役立つ情報
ハローワークでは、求人の紹介だけでなく転職に必要なノウハウを学べる支援も行っています。
● 主なサポート内容:
-
履歴書・職務経歴書の添削
⇒ フォーマットや記入例の配布あり -
面接対策の指導・模擬面接
-
求人検索PCの無料開放
-
企業との合同説明会・面接会の案内
-
転職支援セミナー(応募書類作成・自己分析など)
また、近年では「職業紹介を受けながら転職エージェントの利用を併用する」というスタイルも増えており、複数の支援をうまく使い分けることが再就職成功のカギになります。
年齢別の再就職支援制度
再就職支援は年齢に応じて、内容やアプローチが変わるのも特徴です。ハローワークでは、年代ごとの悩みに寄り添った専門窓口を設けています。
● 若年層(おおむね35歳未満)
-
「わかものハローワーク」や「新卒応援ハローワーク」などの専門施設あり
-
キャリアカウンセリングやインターン紹介も実施
-
就職氷河期世代への支援プログラムも展開中
● 子育て世代(20〜40代)
-
「マザーズハローワーク」では、保育所情報や育児と仕事の両立支援を提供
-
時短勤務・フレックス勤務などの求人も多数あり
● 中高年・シニア層(50代〜)
-
シルバー人材センターや中高年向け職業相談コーナー
-
自治体との連携による、再雇用・再教育支援も
それぞれの年代で、再就職の壁や悩みが異なるからこそ、「自分に合った支援窓口」を活用することが重要です。
特別なケースの申請方法
失業保険と聞くと「正社員の人向けの制度」というイメージがあるかもしれませんが、実際にはパートタイマーや高年齢者、育児や介護など家庭の事情で離職した人も対象となるケースがあります。ここでは、そうした特別な事情を持つ人に向けた申請方法や注意点をわかりやすく解説します。
パートやアルバイトの失業保険
パートやアルバイトでも、一定の条件を満たせば雇用保険に加入でき、失業保険の受給資格が得られます。
● 加入条件:
-
週20時間以上の所定労働時間
-
31日以上の雇用見込みがあること
これらを満たしていれば、雇用保険の「被保険者」として扱われます。
そのため、雇用期間中に保険料が差し引かれていた場合は、退職後に失業保険を申請できる可能性があります。
● 注意点:
-
勤務先が雇用保険に未加入だった場合、自分で申し出てもさかのぼって加入はできません
-
雇用保険被保険者証や離職票を退職時に必ずもらいましょう
-
加入期間が12か月以上ないと基本手当を受けられない点も、正社員と同様です
短時間勤務であっても、制度を理解しておけばしっかりサポートが受けられます。
高年齢者の失業保険制度
65歳以上の方は、通常の「基本手当」ではなく、「高年齢求職者給付金」という形での支給になります。
● 制度の概要:
-
原則として一時金(1回限り)の支給
-
雇用保険に6か月以上加入していたことが条件
-
ハローワークでの求職申し込みが必要
支給額は年齢・勤務期間・賃金日額などを基に計算されますが、概ね賃金日額の30日〜50日分相当が支給されます。
● 対象者の例:
-
定年退職後も再就職を希望している人
-
定年後の継続雇用契約を終了した人
-
パート・嘱託など短時間雇用から退職した人
また、地域によっては高齢者の就職支援講座や合同面接会なども開催されているため、ハローワークに相談することが第一歩です。
育児休業後の申請手続き
育児休業からの復職を希望していたが、保育園が見つからないなどの理由で復職を断念した場合、失業保険の対象となる可能性があります。
● 対象となるケース:
-
育児休業を取得後、復帰の予定だったが職場に戻れなかった
-
子どもの預け先が見つからず、働ける状況にない
-
職場との契約が終了または解除された
● ポイント:
-
「就職可能な状態であること」の証明が必要(例:保育園の申込書、求職活動の記録)
-
保育が確保され次第、求職活動が可能な意思があることを示す必要あり
-
離職票や育児休業明けの雇用契約に関する資料も準備しておくとスムーズ
制度の活用にはやや手続きが複雑ですが、育児による離職も一律で除外されるわけではありません。
介護離職と失業保険の関係
親の介護や家族の看病など、やむを得ない理由で退職した場合は、自己都合退職であっても「会社都合扱い」になるケースがあります。
● 対象となる例:
-
家族の要介護状態により、通勤・就労が継続不可能になった
-
訪問介護や施設サービスが利用できず、本人が介護を担う必要がある
-
転居を伴う介護が必要になった場合
● 重要なポイント:
-
「特定理由離職者」に該当すれば、給付制限(2〜3か月)が免除されます
-
ハローワークに介護に関する証明書(診断書・要介護認定通知書など)を提出する必要があります
-
退職理由が記載された離職票に「介護のため」と明記されているとスムーズです
離職の事情をしっかり伝え、ハローワークの担当者と相談しながら進めることが大切です。
✅ 特別なケース別|失業保険申請チェックリスト
【共通項目】すべてのケースに共通して必要
| 項目 | 内容・補足 | チェック |
|---|---|---|
| 離職票(1・2) | 退職後、会社から受け取る書類。未着なら催促。 | ☐ |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード、または通知カード+運転免許証など | ☐ |
| 印鑑 | 認印(シャチハタ不可推奨) | ☐ |
| 写真(3×2.5cm)2枚 | スピード写真可。ハローワーク提出用 | ☐ |
| 通帳またはキャッシュカード | 振込先口座確認用 | ☐ |
【パート・アルバイト】
| 項目 | 内容・補足 | チェック |
|---|---|---|
| 雇用保険加入実績 | 週20時間以上、31日以上の雇用見込みあり | ☐ |
| 被保険者証(会社から交付) | 加入していた証明となる書類 | ☐ |
【高年齢者(65歳以上)】
| 項目 | 内容・補足 | チェック |
|---|---|---|
| 雇用保険加入6か月以上の実績 | 高年齢求職者給付金の条件 | ☐ |
| 一時金制度の案内確認 | 通常の失業給付ではなく一括支給形式 | ☐ |
【育児休業後の離職】
| 項目 | 内容・補足 | チェック |
|---|---|---|
| 保育園申込書・落選通知など | 就職活動の意思と育児制約の証明 | ☐ |
| 雇用契約書・育休終了通知等 | 復職予定があったことの証明 | ☐ |
| 求職活動実績の記録 | 面談・説明会参加・求人応募履歴など | ☐ |
【介護離職】
| 項目 | 内容・補足 | チェック |
|---|---|---|
| 要介護認定通知書・診断書 | 家族の介護が必要であることの証明 | ☐ |
| 介護休業取得証明書(任意) | 離職前に介護休業を取っていた場合 | ☐ |
| 離職票の離職理由欄の記載確認 | 「介護のための退職」と記載されているか要確認 | ☐ |
▷特別なケース別の失業保険申請チェックリストをダウンロードする
申請後の受給期間と延長
失業保険の申請が完了したら、いよいよ受給期間がスタートします。しかし、この「受給期間」は無限に続くものではなく、原則として一定の期間内に給付日数を使い切る必要があります。さらに、病気や育児などのやむを得ない理由がある場合には、延長制度も用意されています。
ここでは、受給期間の基本的な考え方と、再就職時の注意点なども含めて詳しく解説します。
受給期間の開始から終了までの流れ
失業手当の受給期間は原則「離職日の翌日から1年間」です。この1年間の間に、認定を受けながら定められた給付日数(例:90日、120日など)を消化していきます。
● 例:自己都合退職・給付90日の場合
-
離職日:4月1日 → 離職翌日:4月2日 → 受給期限:翌年4月1日まで
-
この1年間で90日分の失業給付を受け取る必要がある
給付日数を使い切る前に受給期間が満了すると、残りの日数分は支給されず消滅してしまいます。早めの申請が重要です。
● ポイント:
-
申請が遅れると給付開始も遅れ、実質の受給額が減る可能性あり
-
認定日ごとの手続きは忘れずに。無断欠席や報告漏れは不支給の原因に
受給の延長について知っておくべきこと
受給期間内にやむを得ない理由で働けない状態になった場合、受給期間の延長申請をすることができます。延長が認められると、最長で3年間まで受給期間を延長できます。
● 延長が認められる主なケース:
-
病気や負傷による就業困難
-
妊娠・出産・育児(原則として子が3歳未満)
-
家族の介護
-
配偶者の転勤による転居
-
海外滞在・留学(本人の希望に基づく場合は不可)
● 申請方法:
-
延長理由が発生した日から30日以内に、所定の様式でハローワークに届け出
-
診断書や出産証明書、転勤辞令などの証明書類が必要
-
受給期間終了後の申請は受理されないため注意!
※延長は「給付日数の延長」ではなく、「給付日数を使い切るまでの猶予期間の延長」である点に注意が必要です。
再就職後の申告義務と条件
再就職が決まったら、速やかにハローワークへ報告する義務があります。報告を怠ったまま失業手当を受給し続けた場合、不正受給となり、給付金の返還や追徴が発生します。
● 再就職後の流れ:
-
ハローワークに就職の事実を報告
-
必要書類(採用通知書や雇用契約書など)を提出
-
条件を満たせば「再就職手当」が支給される
● 再就職手当の主な条件:
-
離職前と同程度の収入で雇用される(フルタイム・社会保険加入など)
-
給付日数が3分の1以上残っている
-
1年以上継続して勤務する見込みがある
-
自己応募やハローワーク紹介など、積極的な求職活動による就職
この手当は、残っている基本手当の最大70%(支給残日数に応じて)が支給される制度で、早期就職の大きなインセンティブとなります。
過去の再雇用と受給への影響
過去に在籍していた会社に再雇用され、その後再び退職した場合、失業保険の申請には以下のような影響があります。
● ポイント:
-
再雇用後の勤務期間が12か月以上あれば、新たに受給資格を得られる
-
勤務期間が12か月未満でも、特定理由離職者(例:介護・転勤など)に該当すれば6か月でも可
-
「前回の給付からどれくらい期間が空いたか」によっても影響あり
ハローワークでは、前回の離職票と新たな離職票の内容を総合的に判断して、再受給の可否を決定します。前職と同一企業であっても、条件さえ整えば再度受給することは可能です。
失業保険の活用と生活支援
失業保険は、収入が途絶える中でも生活を維持し、再就職までの準備期間を支える大切な制度です。さらに、失業保険だけでなく、自治体や国が用意する生活支援制度も併用することで、金銭的不安を軽減できます。
この章では、受給中の生活費管理から使える支援制度、注意点まで、失業中の暮らしを支える実践的な情報をまとめました。
受給中の生活費の計算方法
失業保険の給付額は、現役時代の給与に比べてどうしても少なくなるため、生活費の見直しとやりくりの工夫が重要です。
● 生活費シミュレーションのステップ:
-
基本手当日額 × 月の給付日数(約28日)を想定
例:基本手当日額6,000円 → 月収換算で約168,000円 -
固定支出を把握(家賃、光熱費、通信費など)
-
変動費(食費・交際費・レジャー費)を見直す
-
家計簿アプリやエクセルで可視化する
急な出費や延長手続きに備えて、毎月1〜2万円の生活防衛費も確保できると理想的です。
失業中の生活を支える制度とは?
失業保険だけではまかなえない場合は、以下の生活支援制度の併用も検討しましょう。いずれも条件付きで併用可能です。
● 住居確保給付金
家賃相当額(上限あり)を支給。就職活動中で収入が一定以下の人が対象。
支給期間は3〜9か月。市区町村の自立相談支援窓口で申請。
● 緊急小口資金・総合支援資金(生活福祉資金貸付)
無利子で生活費を借りられる制度。社会福祉協議会が窓口。
返済免除の特例措置が出る場合もある(災害・感染症対応など)。
● 職業訓練受講給付金
公共職業訓練を受ける人に、月10万円+交通費を支給。失業給付がない人も対象。
要件:収入・資産の制限あり。事前にハローワークで相談が必要。
生活再建のための支援制度
失業が長引いたり、経済的に厳しい状況が続く場合は、生活困窮者自立支援制度などを利用することも選択肢です。
● 生活困窮者自立支援制度の主な内容:
-
就労準備支援(身だしなみ、履歴書、面接練習など)
-
家計相談支援(債務整理・生活設計のアドバイス)
-
一時生活支援(住居喪失者への宿泊提供や食料支援)
-
就労訓練事業(段階的な働き方による社会復帰支援)
住民票がある市区町村の「自立相談支援機関」に相談することで、状況に応じた支援プランを提案してもらえます。生活保護に進む前のワンクッションとしての活用も増えています。
受給期間中の注意すべきポイント
失業保険を受給している間は、「失業状態であること」が前提です。そのため、副業・アルバイト・内職などをする場合は事前にハローワークへ申告する必要があります。
● よくある注意点:
-
内職や短時間バイトでも申告は必須
→ 収入の有無にかかわらず、無申告は「不正受給」となります -
求職活動を怠ると、次回の認定が不支給になる可能性あり
-
就職が決まったら速やかに報告
→ 再就職手当を受け取るための条件でもあります
● 不正受給になると…:
-
受給金額の返還
-
最大2倍の追徴金
-
給付の停止・取消し、さらには刑事罰の対象にもなり得ます
「申告が面倒だから」と黙っているとリスクが大きいため、必ずハローワークに相談しながら進めることが安全です。
まとめ|失業保険の申請で安心した毎日を取り戻そう
失業保険は、働けなくなったときの生活を支える大切な制度です。申請の流れや必要書類、受給条件を正しく理解することで、手続きへの不安もぐっと軽くなります。本記事を参考に、ハローワークでの申請をスムーズに進めて、受給までの準備をしっかり整えましょう。
失業中の時間は、次のステップに向けた大切な充電期間でもあります。制度を上手に活用して、安心できる日々を取り戻しましょう。