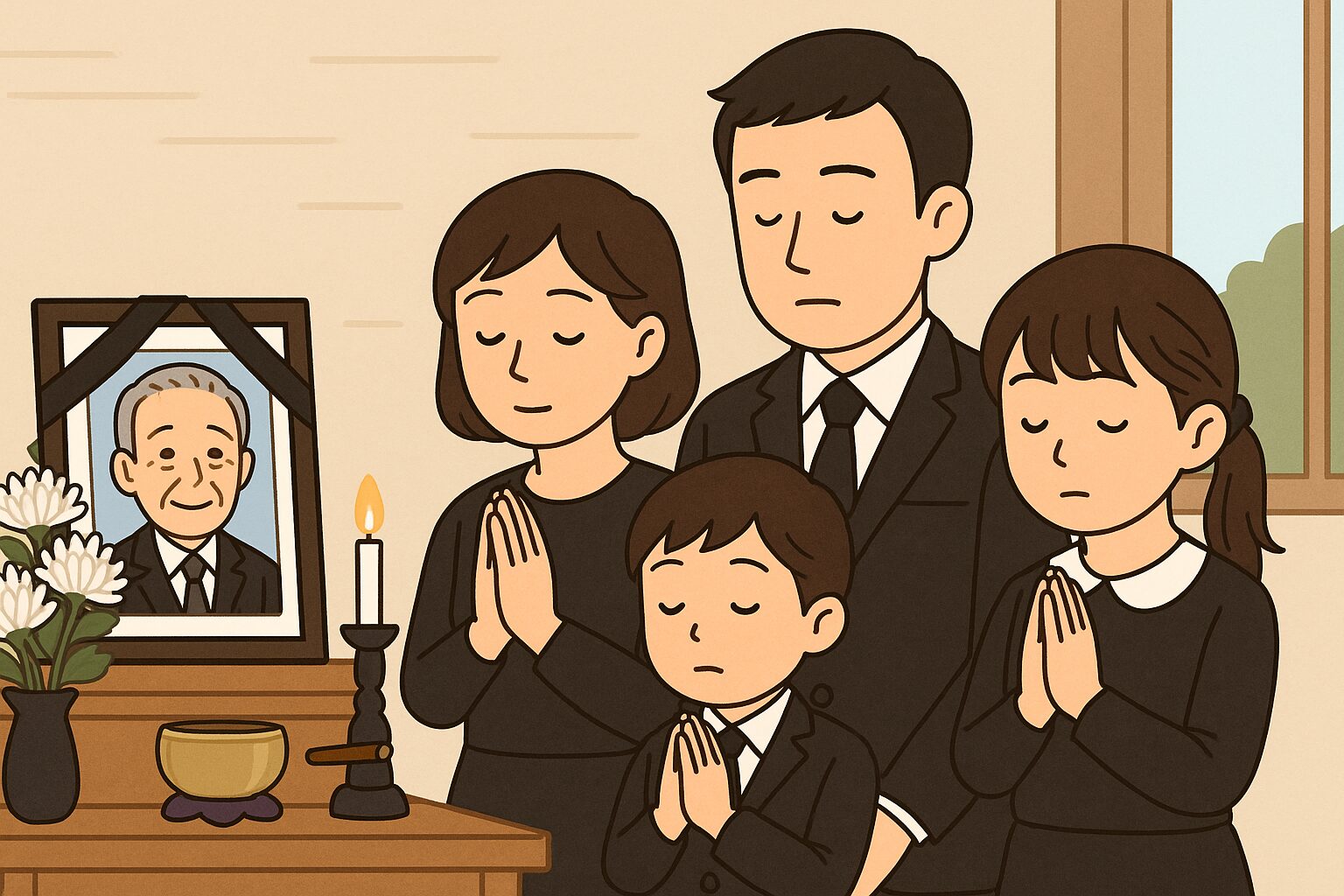「法事って、いつ頃やるのが正しいの?」――初めての準備では、時期の目安に迷う方が多いものです。命日に合わせるのが基本とはいえ、仕事や子どもの予定との両立もあり、思うように日程が取れないこともありますよね。そんなとき大切なのは、無理のないスケジュールと、家族の気持ちを大切にすることです。
この記事では、一周忌・三回忌・七回忌の時期の目安と決め方のコツを、我が家の体験談を交えてわかりやすく解説します。初めてでも安心して進められるよう、やさしくサポートします。
法事の基本|「法要」との違いをまず理解しよう
法事の基本を理解するうえで欠かせないのが、「法事」と「法要」の違いです。
この2つの言葉、同じように使われることが多いですが、実は意味が少し異なります。私も最初は「なんとなく同じようなもの」と思っていましたが、準備を進める中で、その違いを知ることがとても大切だと気づきました。
法要とは?
「法要」とは、故人の冥福を祈り、仏の教えに触れるための宗教的な儀式です。
お寺や自宅で僧侶をお招きし、お経をあげていただくことが中心となります。代表的なものには、一周忌・三回忌・七回忌などの「年忌法要」があります。
法要は、単なる形式的な儀式ではありません。僧侶の読経を通して、故人を思い出し、改めて感謝の気持ちを心に刻む機会でもあります。
たとえば、一周忌の法要では「もう1年が経ったんだね」と家族で振り返る時間になり、三回忌では「少しずつ前を向けるようになったね」と気持ちの節目を感じることもあります。
お寺で行う場合は、読経後に法話(説法)を聞けることもあり、仏教の教えを通して“命”や“感謝”を見つめ直す貴重な時間となります。
法事とは?
一方の「法事」は、法要に会食や親族の集まりを含めた総称です。
つまり、「法要+食事や挨拶、引き出物の準備」など、全体を含めた行事が「法事」となります。
法事の準備には、お経だけでなく、以下のような多くの段取りが含まれます。
-
親族・知人への案内状の送付
-
会場や会食の手配(お寺・自宅・会館・料亭など)
-
お供え物やお花の準備
-
お布施・お車代・御膳料の用意
-
引き出物の手配
-
当日の進行や挨拶の準備
初めてのときは、私も「お経をあげてもらうこと」だけを考えていましたが、いざ準備を進めると、やることの多さに驚きました。親族への連絡一つとっても、スケジュール調整が必要で、誰を招くか、会食をどこで行うかなど、決めることがたくさんあります。
「法要」は“心の供養”、法事は“形を整える供養”とも言えます。
この2つをうまく組み合わせることで、故人をしっかりと偲び、家族・親族みんなが心を通わせる機会になるのです。
家族で相談しながら進めることが大切
法事は一人で進めるよりも、家族で話し合いながら進めることが大切です。
「どんな形式にするか」「どの程度の規模で行うか」「どの親戚を招くか」などを相談しながら決めていくと、後悔のない形に近づけます。
私の家庭でも、一周忌の準備をするとき、義母から「お寺の予定は早めに聞いておいたほうがいいよ」とアドバイスをもらいました。義父は「お供え物は季節の果物がいいな」と意見を出してくれて、みんなで役割分担をしながら少しずつ準備を進めました。
結果的に、当日は滞りなく進み、家族全員が「やってよかった」と感じられる時間になりました。
地域や宗派による違いにも注意
また、法事の進め方は地域や宗派によって異なる場合があります。
たとえば、ある地域ではお寺で読経のあとすぐに会食を行うのが一般的でも、別の地域では後日改めて集まるケースもあります。
浄土真宗では「故人を悼む」のではなく、「仏の教えに感謝する」という考え方が重視されるため、進行や言葉遣いも少し違うことがあります。
迷ったときは、菩提寺(お世話になっているお寺)や年長者に相談するのが一番です。
「この地域ではこうするのが普通」「お寺さんがこうしてくれたら安心」など、経験に基づいたアドバイスをもらえるはずです。
そして、“供養の気持ちをどう形にするか”を家族で話し合い、無理のない形で進めることが何より大切です。
年忌法要の時期の目安|一周忌・三回忌・七回忌のタイミング
「法事はいつが正解なのか」。私も最初に迷ったのはここでした。命日は大切な基準ですが、実際には親族の予定や会場の空き、お寺さんの都合も重なります。ここでは迷いがちな一周忌・三回忌・七回忌以降について、具体的な決め方と準備のポイントを整理します。
一周忌法要の目安
一周忌は亡くなった翌年の“同月同日”を基本に、原則として命日前の土日へ前倒し(繰り上げ)で行うのが一般的です。
例として、2024年3月10日に逝去の場合は、2025年3月10日が一周忌。命日が平日なら、前の週末に設定して集まりやすさを優先します。うちも平日命日だったため、土曜にお寺の時間を確保してもらいました。
準備は早めが安心。私の体感では次のスケジュールが現実的でした。
-
3か月前までに候補日を家族で共有(学校行事や繁忙期を把握)
-
2か月前までにお寺・会場・会食の仮押さえ
-
1か月前に案内連絡と引き出物の目星、参列可否の回収
-
2週間前に人数確定と仕出し・席次、当日の流れ確認
避けたいのは「命日後の繰り下げ」。どうしても難しい場合は菩提寺に相談し、読経のみ命日に近い日にお願いし、会食は別日にするなど柔軟な方法もあります。六曜は本来関係しませんが、年長の親族が気にする場合は配慮しました。なお、うるう年の2月29日命日の場合は2月28日または3月1日に前倒しで行う家庭が多いです。
三回忌法要の目安
三回忌は「数え方」が要注意。亡くなった年を“1”と数えるため、三回忌は没後2年目にあたる点をまず押さえておきます。
例として、2024年3月10日没なら、2026年3月10日が三回忌。ここでも前倒しの週末実施が基本です。
三回忌は参列範囲や規模を見直す良いタイミングでした。
-
参列者の範囲を「近親者中心」に絞るか
-
会食を会館で行うか、読経のみで解散するか
-
遠方の親族には供花・供物やお布施の郵送で参加してもらうか(オンライン配信を併用する家も増加)
私の家では、小さな子ども連れが多かったため、読経を30〜40分に収め、会食は個室で短時間に。小さな折詰と心ばかりの品を用意して、移動の負担を減らしました。繰り返しになりますが、案内は1か月前を目安に。返信用フォームや家族LINEを使うと人数確定が早まり、無駄のない手配ができます。
七回忌以降の目安
七回忌は満6年後、つまり7年目の命日に行います。以降は十三回忌(12年後)→十七回忌(16年後)→二十三回忌(22年後)→二十七回忌(26年後)→三十三回忌(32年後)と続き、三十三回忌を“弔い上げ”の目安とする家庭が多いです。
近年は核家族化や高齢化で、三回忌や七回忌を一区切りにするケースもめずらしくありません。私の家でも、七回忌以降は「法要は簡素に、気持ちは丁寧に」を合言葉に、読経と小さな会食に留める方針にしました。お彼岸やお盆の時期に合わせて寺院の合同法要へ参列する方法もあり、次のような利点と注意点があります。
-
利点
-
日程調整がしやすい、費用や準備の負担が軽い
-
遠方の親族が帰省に合わせやすい
-
-
注意点
-
観光シーズンは移動費・宿泊費が高騰
-
会場が混み合い待ち時間が発生しやすい
-
七回忌以降は、写真の小さな展示や、思い出の品を1点だけ持ち寄るなど、家族の“らしさ”を残す工夫をすると、形式に流されず心に残る時間になります。参列できない人には当日の様子を写真で共有し、香典や供花へのお礼状を忘れずに。年長者の意向を尊重しつつ、無理のない頻度と規模を家族で話し合うのがいちばんだと感じています。
命日当日以外に行うのはOK?|日程調整の考え方
共働きや子育て家庭では、命日ぴったりの実施が難しいこともしばしば。私も仕事や学校行事、親族の移動を考えながら、最善の折り合いを探りました。原則は「命日前の週末に繰り上げ」、やむを得ない場合はお寺に相談して無理のない形で行うと覚えておくと迷いにくいです。
命日より前の「繰り上げ法要」が基本
基本マナーは命日前の実施。命日が平日なら前の土日、三連休が近ければその初日など、集まりやすさを優先します。前倒しの幅は地域差があるため、直前週末を第一候補にしつつ、どうしても合わない場合は2週間ほど前までを目安に検討。年長の親族が六曜を気にすることもあるので、カレンダーの見え方に配慮し、事前に意向を確認しておくと安心です。
命日を過ぎた場合の対応
体調不良や天候、急な出張などで過ぎてしまうこともあります。その場合も焦らず、まずは菩提寺へ相談を。読経だけ命日に近い日でお願いし、会食は別日にする、同月内で日を改めるなど、柔軟な選択肢があります。案内文では理由を簡潔に添え、香典・供花を事前送付いただいた方には、当日の様子やお礼を丁寧にお伝えすると気持ちが伝わります。
候補日の出し方と調整のコツ
最初にお寺の空き枠を確認し、家族・親族には二〜三つの候補を提示。学校行事や繁忙期を避け、出欠の締切日をはっきり伝えると決定が早まります。私は返信フォームや家族LINEを活用し、1か月前に人数概算、2週間前に確定という流れにすると、仕出しや引き出物の過不足が出にくくなりました。
お盆・彼岸・長期連休をどう扱うか
寺院や会館が混みやすい時期は予約が取りづらく、移動費も高くなりがち。一方で帰省と合わせやすい利点もあります。遠方の親族が多い場合は、あえて繁忙期を外し、交通費の負担を下げるほうが参加率が上がることも。混雑期は時間帯の前後ずらしや、読経のみ→短時間会食の構成にすると負担が軽くなります。
六曜や年長者の意向への配慮
仏事は六曜に左右されないとされますが、気にする方がいるのも事実。カレンダー上の印象や語感を気にかけ、「皆が気持ちよく集まれる日」を優先。日取りに関する価値観は世代差が出やすいので、最初の段階で希望を聞き、折衝の余地を残しておきます。
小さな子ども・高齢者がいる場合の工夫
読経の時間は30〜40分程度に抑え、会食は個室や短時間に。ベビーカー置き場、段差の少ない動線、トイレの位置など、当日の動きやすさを確認しておくと安心です。遠方の祖父母にはオンラインで読経の様子を共有し、後日あらためて小規模な食事会をする方法も選べます。
会食と法要を分ける選択肢
全員の予定がどうしても合わないときは、読経は近親者だけで執り行い、会食は別日・別場所で実施する二段構えに。折詰を手配してお持ち帰りにする、参列できない方へは引き出物とお礼状を送るなど、参列の形は一つでなくて大丈夫です。
うるう年や特殊日程の取り扱い
2月29日が命日のケースは、2月28日または3月1日に繰り上げる家庭が多め。大型連休や学期末が重なる場合は、寺院の空きと親族の移動都合を天秤にかけ、無理のないほうを選びます。台風シーズンは予備日を一つ設定し、交通機関に影響が出た場合の連絡方法を先に決めておくと混乱しません。
スケジュール例(私の進め方)
-
2〜3か月前 家族と候補週末を共有、寺院・会場の仮押さえ
-
1か月前 案内送付、出欠回答の締切設定、引き出物の目星
-
2週間前 人数確定、席次・配車・当日役割の確認
-
前週〜前日 供花・供物の手配最終チェック、当日の導線確認、天候対応の連絡網整備
日取りに“絶対の正解”はありません。命日を軸に「皆が無理なく集まれること」「故人を穏やかな気持ちで偲べること」を最優先に、現実的な落としどころを家族で見つけていけば、準備そのものが供養の時間になります。
年忌法要の種類と回数|どこまで行えばいい?
「法事って、いつまで続けるのが正解なんだろう?」
私も最初の頃、終わりの目安がわからずに悩みました。親世代や地域の慣習を聞いてもまちまちで、どこまで行うかは家庭ごとに判断が分かれるところです。
ここでは、年忌法要の一般的な流れと考え方、そして宗派や家族の事情に合わせた柔軟な選び方を紹介します。
一般的な年忌法要の流れ
仏教の教えに基づく年忌法要は、故人を定期的に偲び、感謝を伝える大切な機会です。
故人を思い出し、「今の自分たちがあるのは先代のおかげ」と感じることで、家族の絆を再確認できる時間でもあります。
代表的な年忌法要は以下の通りです。
-
一周忌(1年後)
-
三回忌(2年後)
-
七回忌(6年後)
-
十三回忌(12年後)
-
十七回忌(16年後)
-
二十三回忌(22年後)
-
二十七回忌(26年後)
-
三十三回忌(32年後)
この中でも、一周忌と三回忌は親族全員が集まりやすく、比較的丁寧に行うケースが多いです。
七回忌以降は、少しずつ規模を縮小し、家族中心の法要に切り替える家庭が増えています。
特に三十三回忌は、「弔い上げ(とむらいあげ)」と呼ばれる節目で、一区切りとすることが一般的です。
弔い上げとは?
「弔い上げ」とは、故人が“仏さま”として成仏し、家の守り神となる節目を意味します。
三十三回忌をもって供養を一区切りにすることで、
「これまでの感謝を伝え、これからは日常の中で供養していく」
という気持ちへと切り替えることができます。
私自身も、祖母の三十三回忌を終えたとき、「これで一区切り」と家族みんなでホッとした気持ちになりました。
長い年月をかけて故人を偲び続けたことが、心の中で大きな“感謝の積み重ね”になっていたと感じます。
現代の流れ|七回忌・十三回忌で締める家庭も増加
近年はライフスタイルの変化に伴い、すべての年忌法要を丁寧に行うのが難しいという声もよく聞きます。
仕事や子育て、遠方の親族との距離など、現実的な事情を踏まえ、次のような形を選ぶ家庭が増えています。
-
七回忌までを目安に一区切りとする
-
十三回忌まで行い、以降はお盆やお彼岸でまとめて供養する
我が家でも、祖父の法要は「七回忌を家族全員で行い、それ以降はお盆の集まりで供養する」という形にしました。
大切なのは、“回数”よりも“気持ち”。
形式にとらわれず、「感謝の心をどう表すか」を軸に考えれば、家庭に合った供養の形が見つかります。
地域差・家族構成による違い
法要の回数や規模には、地域性や家族構成が大きく影響します。
たとえば、地方の旧家や寺院とのつながりが深い家庭では、五十回忌や百回忌まで丁寧に供養を続けるところもあります。これは、代々のご先祖様を大切にし、家の歴史を受け継ぐ文化が息づいているからです。
一方、都市部や核家族世帯では、
-
お墓参りや日々の供養を重視
-
家族の予定や距離感を考慮した無理のない頻度
といったスタイルが主流になりつつあります。
また、高齢の親族への負担を軽くすることや、若い世代が参加しやすい形にすることも、現代の法要では大切なポイントです。
「集まることが目的」ではなく、“想いを伝え合うこと”が目的であることを意識すると、自然と家族に合った形式が見えてきます。
宗派による考え方の違い
宗派によって、年忌法要に込める意味や回数の考え方が少しずつ異なります。
どの宗派にも共通しているのは、「故人を偲び、感謝の心を忘れない」ことが本質という点です。
-
浄土真宗
故人の冥福を祈るというよりも、仏の教えに触れ、感謝の心を深める時間として位置づけます。命日そのものよりも、「教えを聞く場」としての意義が重視されます。 -
曹洞宗・臨済宗(禅宗系)
修行や感謝の意味を大切にし、静かに故人を偲ぶ厳かな法要が特徴。命日を重んじ、読経や焼香を通じて心を整える機会とします。 -
真言宗・天台宗
故人の成仏を祈り、節目ごとの法要を丁寧に重ねることに意義を見出します。七回忌や十三回忌など、年忌法要を大切にする傾向が強いです。
宗派や地域の慣習によって細かな違いがあるため、迷ったときは菩提寺(お世話になっているお寺)に相談するのが一番確実です。
「わが家の宗派ではどうすればよいか」を確認すれば、家族全員が納得できる形で進められます。
家族での話し合いが何より大切
法要の回数やタイミングに“正解”はありません。
私が感じたのは、「どうすれば家族みんなが心から“やってよかった”と思えるか」が一番の基準だということ。
親世代・子世代・孫世代、それぞれの立場で価値観や感じ方が違うからこそ、「どのように受け継ぎたいか」「次の世代にどう伝えるか」を話し合うことが大切です。
そうすることで、法要は単なる儀式ではなく、“家族の記憶をつなぐ時間”に変わっていきます。
「無理なく続けられる形で」「感謝を伝える気持ちを大切に」。
この2つを意識するだけで、自然と“わが家らしい供養”が見えてきます。
家族や親族との日程調整|我が家の体験談
法事の日程を決めるとき、意外と大変なのが「親族とのスケジュール調整」です。
特に共働き家庭や遠方に住む親族がいる場合、「この週は無理」「その日は出張」「子どもの行事と重なる」など、全員の予定を合わせるのは至難の業。私の家でも、最初の一周忌ではこの調整にかなりの時間をかけました。
候補日はお寺の予定をベースにするのがスムーズ
最初は「みんなの都合を聞いてから決めよう」と思っていたのですが、全員の希望を聞いていたら日程が決まらず、話が堂々巡りに。
そこで私は、「まずお寺さんの空き日程を先に確認」してから調整を進める方法に切り替えました。
具体的には、
-
「〇月〇日(土)と〇日(日)のどちらかで予定を組みたいのですが、ご都合いかがですか?」
といったように、候補を2~3日に絞って提示しました。
選択肢を絞ることで返信もしやすくなり、「どちらかに合わせます」という返事が多くなりました。
「いつがいいですか?」と自由回答で聞いてしまうと、かえって決まらないことが多いので、“選べる形式”で提案するのがコツです。
また、年配の親族には電話で伝え、若い世代はLINEやメールで確認するなど、世代に合わせた連絡方法を使い分けるとスムーズです。
特にお寺さんは人気の日(仏滅や大安の週末など)から埋まるため、早めに仮予約しておくと安心。
会場・会食の空き状況も合わせて確認
お寺の日程が決まったら、次は会場の手配です。
近年は法要会館や料亭も混み合うため、お寺・会食・親族の予定を並行して調整するのがポイント。
私は一度、「お寺は空いているのに会場が取れない」という失敗を経験しました。
それ以来、仮押さえの段階で「お寺→会場→親族」の順に確認をとるようにしています。
“動かせない予定”から先に確定させるのが、段取り上とても効率的です。
小さな子どもがいる家庭への配慮も忘れずに
法事は大人の行事というイメージがありますが、子どもにとっても「家族のつながり」を学ぶ大切な場。
ただし、長時間に及ぶと退屈してしまうこともあります。
我が家では、子どもがまだ幼かったので、
-
読経は30分程度に短くお願い
-
会食は個室で1時間以内に終了
-
事前に絵本や静かな遊び道具を持参
といった工夫をしました。
子どもが途中でぐずってしまっても、個室なら周囲を気にせず対応できます。
さらに、「静かにしていなさい」よりも、「一緒におじいちゃんにありがとうを伝えようね」と声をかけることで、子どもも自然に“参加者”としての意識を持てるようになります。
「手を合わせる=ありがとうの気持ちを伝える時間」と教えると、子どもなりに真剣な表情で臨む姿が印象的でした。
遠方の親族・高齢者への配慮も忘れずに
親族の中には、遠方から来る方や高齢で移動が大変な方もいます。
そうした場合、法事の時間を午前中に設定して「日帰りができるようにする」など、移動の負担を減らすスケジュール設計が大切です。
私の家では、遠方の伯母に「宿泊が必要ですか?」と事前に聞き取り、必要に応じて駅近くのホテルを紹介しました。
また、季節によっては雪や台風などのリスクもあるため、天候リスクの少ない時期を選ぶことも忘れずに。
家族の役割分担で負担を軽減
スケジュール調整や準備を一人で抱え込むと、想像以上に大変です。
我が家では、
-
お寺・会場の手配:夫
-
親族への連絡・返信管理:私
-
引き出物やお供え物の準備:義母
といったように、役割分担をしてチームで進めるようにしました。
「自分だけが動く」のではなく、「家族全員で作り上げる行事」という意識を共有すると、自然と協力体制が整います。
家族みんなが心を合わせられる日を
法事の日程調整は、思った以上に気をつかうもの。
でも、「全員の気持ちが揃う日を選ぶ」ことが一番のポイントです。
お寺の予定を基準に、候補日を2〜3日に絞って提案すれば、スムーズに決まりやすくなります。
家族や親族が無理なく集まり、子どもも自然と参加できるように整えることで、あたたかい時間が生まれます。
法事の準備チェックリスト|時期が決まったら進めたいこと
日程が無事に決まったら、次のステップは「準備」です。
法事は思っている以上にやることが多く、直前になって慌ててしまう方も少なくありません。
特に子育て中の家庭では、日常のスケジュールと並行して進める必要があるため、「早めに動く」「家族で分担する」のが成功のカギです。
ここでは、我が家の経験も交えながら、時期ごとに押さえておきたいポイントを整理しました。
1〜2ヶ月前|基本の段取りを固める時期
まずは、法事の骨格をつくる大切な時期。お寺・会場・親族の予定を押さえましょう。
-
菩提寺(お寺)に連絡し、日程・読経料の確認
お寺さんの予定は早い段階で埋まることがあるため、「命日から逆算して2ヶ月前」には相談しておくのが理想です。
あわせて、読経料(お布施)やお車代、御膳料の金額感も確認しておくと安心。 -
会場(自宅・会館)の予約
自宅で行う場合はスペースや駐車場、イスの数などを確認。
会館や法要専用施設を利用する場合は、お寺との距離・設備・送迎の有無もチェックしましょう。 -
会食場所・仕出しの手配
近年は「法要+会食」を一体化したプランも人気。
小さな子どもや高齢の親族がいる場合は、個室や椅子席を選ぶと負担が少なくなります。 -
参加者リストの作成・招待連絡
誰を招くかを家族で話し合いましょう。
目安として、一周忌・三回忌は親族や親しい友人まで、七回忌以降は家族中心が多いです。
招待は1ヶ月前を目安に。メールやLINEで済ませる場合も、年配の方には封書で案内状を送ると丁寧です。
この時期に「軸となる予定(お寺・会場・参加者)」を決めておけば、後の作業が一気にスムーズになります。
2〜3週間前|細かな準備を整える時期
全体の枠が固まったら、次は当日に必要なものを一つずつ準備していきます。
-
引き出物の選定・注文
一般的には、2,000〜5,000円程度の品物を選ぶ家庭が多いです。
タオルセット、カタログギフト、和菓子など、幅広い世代に喜ばれるものが安心。
数に余裕をもって手配し、当日急な参加にも対応できるようにしておきましょう。 -
お布施・お車代・御膳料の準備
それぞれの金額や包み方、表書きを事前に確認。
お布施袋は白無地または「御布施」と書かれたものを選び、筆ペンや毛筆で丁寧に記入します。
お車代・御膳料は別封筒に分けておくと分かりやすいです。 -
服装や持ち物の確認(子ども用も忘れずに)
喪服は事前にクリーニングを済ませ、靴やバッグもチェック。
子どもは黒やグレー、紺の落ち着いた服装を選び、靴下の色も確認しておくと安心です。
「前日に慌てない」ために、家族全員分を一度並べてチェックしておきましょう。
この時期に“モノの準備”を終わらせておけば、直前は気持ちの余裕を持って過ごせます。
前日〜当日|最終確認と気持ちの準備
いよいよ当日が近づいたら、最後の確認を行いましょう。
-
お供え物やお花の準備
季節の花や故人が好きだったお菓子などを用意すると、より心のこもった供養になります。
生花を注文する場合は、前日の午前中までに依頼しておくと確実です。 -
会場の掃除や設営
自宅で行う場合は、仏壇周りの清掃や座布団の準備を忘れずに。
会場利用の場合も、受付や席次表、引き出物の配置などを確認しておくと安心です。 -
当日のスケジュール確認
読経・焼香・法話・会食までの流れを家族で共有しておきましょう。
誰が受付をするか、挨拶は誰が行うかなど、「当日の役割分担」を明確にしておくことが大切です。
また、法事は準備が整うほど「慌てず、穏やかに」進められます。
特に小さな子どもがいる家庭では、絵本や軽食などを準備しておくと、待ち時間も安心です。
家族で分担して、チームで動くのが成功のコツ
法事の準備は一人で抱え込むと大変です。
我が家では、
-
パパ → お寺との連絡
-
私 → 引き出物・会食手配
-
義母 → 親戚への連絡
というように、家族で役割を分担しました。
チェックリストを共有し、誰が何を担当しているか見える化すると、抜け漏れも防げます。
最近ではスマホのメモアプリや共有ToDoリスト(Googleスプレッドシートなど)を使うのもおすすめです。
「早めの確認」と「家族での協力」さえ意識しておけば、当日は心穏やかに故人を偲ぶ時間を迎えられます。
まとめ|法事の時期は「命日前の週末」を目安に、心を込めた準備を
法事は、故人を思い出し、家族や親族の絆を深める大切な時間です。
難しく考える必要はありません。「命日の前の週末に行う」ことを基本に、家族の事情に合わせて柔軟に考えれば大丈夫です。
そして、形式よりも「ありがとう」の気持ちを伝えることが何より大切。
我が家も回を重ねるごとに、「みんなで集まれること」そのものが一番の供養だと感じるようになりました。
少しずつ慣れていけば、次の世代にもしっかり伝えていけます。
忙しい日々の中でも、心を込めた法事を行えるよう、早めの準備を心がけていきましょう。